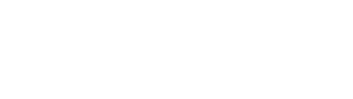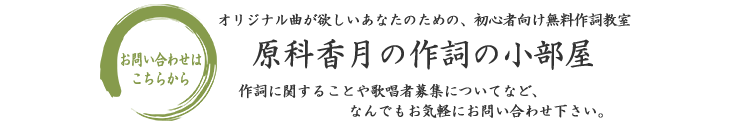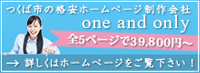創作の小部屋「函館物語」第2回
2022年01月29日
 創作の小部屋「函館物語」第2回
創作の小部屋「函館物語」第2回
現在29日の午前7時です。つくば市の外気温はマイナス1℃です。2階の自室で、ストーブをつけ、コーヒーを飲みながらのアップです。
ここずっと、オミクロン株が猛威を振るっています。この先どうなるのでしょうか?アメリカのニューヨーク州では、オミクロン株感染のピークが過ぎたと見られているいるようです。感染者が減り始めており、これに伴い入院患者も減少傾向とのことです。
日本も早くそうなって欲しいものです。ですが、オミクロン株が消えても、また新種のウイルスが出現しないかと危惧してしまいます。
アイキャッチ画像は、SAMさん撮影の「凍結した鶴の噴水池」です。下の画像は、私が家の近くで撮った「雪の翌日」です。中央に筑波山が見えます。
それでは、前回約束しました、「函館物語」の主人公が家具製造会社の作業員から、放射線技師になった経緯、また坂本真知子さんとの出会いまでを記していこうと思います。
創作の小部屋 函館物語
第2章 放射線技師の誕生と真知子との出会い
〖作業員から放射線技師へ〗
私は、昭和45年に函館のある道立高校を卒業すると、東京の都心からやや南に位置する、ある中堅の家具製造会社に就職した。その頃は高度経済成長期で、私たちは金の卵ともて囃された。私は、内地に憧れていた。一度、故郷から出てみたかった。若いうちに、日本の首都・東京での生活を経験してみたかった。
きっと私の人生に、何かを与えてくれるものと信じていた。ただ、いつかは故郷に帰るつもりでいた。私は長男なのだ。1年半が経過し、仕事にも、この都市の空気にもやっと慣れたと思われた頃、福島生まれの仕事仲間から、ある相談を持ち掛けられた。
「高橋、おまえ、この工場で一生を終えるつもりか?それが悪いという訳じゃないが、一度きりの人生だ。もう少し夢のある、もっと張り合いのある仕事をしてみないか?」
この友人の名前を伊藤智之と言った。この伊藤の話は、「診療放射線技師」になってみないかというのだった。資格を取ると、患者さんのレントゲン写真を撮ったり、その他にも病気の診断に必要ないろいろな放射線の検査をさせて貰えるという。待遇も、将来性も、工場で働くよりもずっと恵まれるという。
※診療放射線技師が現在正式名称ですがだが、ここでは、当時は「レントゲン技師」が一般的な呼称だったので今後は「レントゲン技師」とさせていただくことにする。
その資格を取るために、「レントゲン技師」の養成専門学校が夜間もあるという。働きながら2年の間勉強し、国家試験に見事合格すれば、間違いなく大きな病院でも採用されるという。私を誘ったのは、一人では心細かったのかも知れなかった。
だが私は、その伊藤の提案に喜んで乗った。直接人と接し、その人の役に立てるという仕事には生きがいがある。それに、故郷の親にも喜ばれるに違いない。幸い、寮からその専門学校までは電車で30分の距離であり、授業開始には充分間に合うという。
それから、専門学校の受験用の教科書を探し、二人で遠くの書店まで出かけたりした。やっと必要な本を数冊見つけることが出来た。節約の意味だけではないのだが、二人は同じ教科書を使い回した。寮のお互いの部屋を行ったり来たりしながら、結構遅い時間まで勉強に熱中した。しばらく勉強などしたことがないため、数学が特に難しく、一人では多分続かなかったと思う。お互いに励ましあい、教えあいながらの勉強は確かに効率が良かった。
翌年の早春、レントゲン技師の夜間専門学校の入学試験に二人とも合格することが出来た。合格と知った晩、嬉しくて二人でこっそり乾杯した。
工場の仕事と夜間学校の両立は、確かに辛かった。ただ授業を受けていれば良いというものではなかった。「レントゲン技師」の国家資格が取れなければ、せっかくの時間と授業料が無駄になる。眠い目を凝らしながら、必死に授業に食らい付いた。仲間には、既に総合病院に採用されており、職場にて午後3時頃までレントゲンの助手をし、それから通学して来るという恵まれた者もいた。そうした者は、殆んど近県からの通学者だったが。
工場の上司にも、二人のことは知られたが、特に注意を受けることもなかった。係長は授業に間に合うように、残業を極力減らしてくれたり、何かにつけ支援してくれた。とても有難かった。いつだったか、係長は二人を前にして話してくれたことがある。
「私は、大学を出て、図書館司書になりたかったが、家が貧しかったので諦めた。お前たちは立派だ。頑張れ!」
風邪をひいて私が寝込んだときは、伊藤はおかゆを作ってくれ、また授業内容を記したノートを見せてくれた。私もそのお返しをしながら頑張った。2年間の月日ははアッという間に流れ、二人は無事卒業し、併せて国家試験にも合格することが出来た。
伊藤は、東京のある有名な総合病院に就職したが、私は函館の総合病院に就職することになった。長男である私は、田舎の実家から通うつもりだった。他の仲間は、殆んど東京に残ったが、地方へと帰って行ったものも少なくない。誰彼ともなく、10年置きに同窓会をしようという話が持ち上がった。
不思議でならない、自分の意志というより、他人のたった一言が私の生きざまを変えた。私の人生を変えた。私の場合は、とても幸運だった。伊藤には、感謝しかない。生涯の友人となるだろう。
〖真知子との出会い〗
私は東京から帰り、北斗の実家から函館の総合病院に勤め始めた。病院には職員用の駐車場が用意されていたが、私は車を買う余裕はなく、バスを利用しての通勤となった。家から最寄りのバス停までは自転車で10分程だったが、雪が降る頃までには車が欲しいと思った。
勤務初日、私はレントゲン室の技師長に連れられ、院内各部署に挨拶に回った。病院の中がこんなに広いとは知らなかった。医局には、数人の医師がいたが、他の医師は既に病棟の患者さんの回診をしていると、頭頂部の薄くなった40代後半と思しき医師が話してくれた。それぞれの医師の机の上には、書類が乱雑に積み上げられており、患者から全幅の信頼を受ける医師の意外な一面に、私は驚いた。
薬局に行くと、一部の人は何やら準備をしているようだったけれど、他の二十人近い薬剤師たちは、立ちっぱなしで雑談を交わしていた。もう就業時間が過ぎているのにと、私が怪訝そうな面持ちでいると、女性の薬局長が話してくれた。
「まだ、外来が始まらないので、仕事が出来ないのですよ。診療が始まって、処方箋が回ってきてからが、私たちの真剣勝負になります。医療に携わる者は全て当然のことですが、万が一でも誤りは許されません。でも、人間ですからいくら注意していても、体調などで間違いを犯さないとは限りません。それなので、薬剤師同士が必ずダブルチェックをしています」
病院勤務初日の私でも理解できた。放射線技師長と薬局を出ようとした瞬間、走りながら部屋に入ろうとした若い女性と私は肩が当たった。無防備だった私は、一瞬よろめいた。
「ごめんない。遅刻してしまい、慌てて走ってしまいました。大丈夫ですか?」
私は大丈夫ですと言うと、放射線技師長の後を追った。ふと思った。今の女性は誰かに似ている。誰だったろうか?
そんな感傷に浸っている余裕はなかった。その後は検査室に向かった。室内には、女性だけかと思われたが、何人か男性の姿も見られた。
病棟に回ると、若い看護婦が二人ずつ組になり、何やら話し合っていた。その棟の婦長がやはり説明してくれた。話している看護婦が昨夜の夜勤者で、日勤の看護婦に患者さんの昨夜の様子を説明しているという。インターホンの音に、ある看護婦が慌てて走っていった。
一通り院内を回った後、技師長は私に今日の仕事の指示を出した。胸部レントゲンの撮影と、その仕事が切れた時間帯は暗室に入り、フィルムの現像をするようにとのことだった。撮影の方法は学校で何度も練習していたので特に問題はなかったが、この病院の暗室に入るのは初めてである。20代の若い技師に、私に要領を教えるようにと技師長は指示してくれた。若い技師は渡辺と言い、丁寧に教えてくれた。
混雑したときは冷や汗もかいたが、そんなこんなで、何とか長い一日が終わった。
「疲れたろう。今日は、もういいから家でゆっくり休んで、また明日元気に頑張ってくれよ。」
技師長は40代後半と思われた。赤ら顔の少し太った、人柄の良さそうな人物だった。
家路を急ごうとして、ハッと気付いた。明日は雨が降るようだと、誰かが言っていた。長靴がないと自転車では革靴が濡れてしまう。通り掛かりの人に教えて貰った商店街は少し遠かったが、周りを散策しながら歩いて行った。ある店に入ると、高齢の女性が愛想よく出迎えてくれ、私の足に合う長靴を探してくれた。傘も勧められたので一緒に購入した。
放射線技師としての初の勤務の日だ。もちろん疲れてはいたが、このまま真っすぐ家に帰るのは何か物足りないという風に、何故か急に気持ちが変わった。
放射線技師たちは背広、あるいはジャケットを着て通勤しているようだ。私も一着しかない背広を着て、今日は出勤した。それで気付いた。私にはネクタイが1本しかなかった。毎日同じネクタイという訳にはいかない。
同じ商店街を歩きながら、紺と黄色のストライブの手軽な値段のネクタイを購入した私は、やっとバス停に向かった。しばらく歩きバス停に着くと何人かが並んで待っていた。最後尾に並んだ私は、時計に目をやると既に6時を過ぎていた。随分歩いたなと感心してしまった。
前に並んだ女性の後から乗り込むと、既に空いている席は二つしかなく、その女性と隣り合わせに座ることになった。何気なく辺りを見渡した私は驚いた。隣の女性は、今朝、薬局の入り口で私と肩が当たった女性だった。
私は、これから生涯勤めるであろう職場の人なら、無視する訳にはいかないと思った。
「あのう、薬剤師の方ですよね。今朝は失礼しました。肩は大丈夫でしたか?」
女性は、「あっ」と小さく叫び、とたんに真っ赤な顔をした。
「放射線の技師の方ですね?今朝は、私が遅刻して、慌てて部屋に飛び込んでしまったものですから。申し訳ありませんでした」
彼女は、顔を私に向けたまま、頭を下げた。
私は、どうして遅刻したのか、その訳を聴こうとしたが止めた。そうだ、今朝、誰かに似ていると思ったが、やっと思い出した。中学生の時、同じクラスで学級委員をしていた中村和子だ。色白で、目の大きい、とても気立ての良い女性だった。私は、密かに憧れていた。だが、高校生になってからは会うことはなかった。
「あのう、今日、僕、初出勤で緊張していたものですから、本当は避けられたのに、僕の方こそすみませんでした」
私が早口で言うと、女性は下を向いて、首を振って笑った。正確には、これが真知子さんとの出会いの初めだった。
放射線技師長は、まだ勤務についたばかりの私を、暫くは就業時間内で帰してくれた。私は、意識的に以前訪れた商店街で時間をつぶし、6時15分頃にバス停に着くように調整した。そうすると2日に一度は、彼女と同じバスに乗ることが出来た。彼女は私と会っても、いやな顔は見せない。私は少し厚かましいかとも思ったが、いつも隣りの席に座った。空いていない時には、近くに立ったまま、特に意味のない天気のことなどを話しかけた。
まだ名前はお互いに知らない。薬局に挨拶に行った時の自己紹介の場には彼女はいなかった。私には名前を聞く度胸はなかった。
「よく会いますね。どこまで帰られるんですか?」
彼女は私の顔を見ながら言った。それだけ言うと、いつかのように顔を赤くして正面に向き直した。
「ぼ、僕、五稜郭から、バスを乗り換えて上磯のバス停で降り、そこから自転車で家まで帰ります。あの、僕は、高橋晴彦と言います。宜しくお願いします」
多分、私の顔も赤く染まったに違いない。真知子さんは少し可笑しそうに、白い歯を手で覆った。それから、少ししてから言った。
「私は、坂本真知子と言います」
こうして、私と真知子さんは、暫くの間、僅か10分にも満たないバスの中でのデートをした。いや、それは私の一方的な解釈で、彼女は同じ病院に勤務する、単なる職場仲間の一人にしか過ぎなかったのかも知れない。10分ばかりだったのは、彼女の家は二人で乗ったバス停の3つ先だったからだ。今日の私は心が高揚し、何故か幸せな気分で満たされた。
私は、一度行きたかった「立待岬」に真知子さんを誘ってみたいと思ったが、なかなか誘う勇気がなかった。
だが、私と真知子さんの二つの心は、少しずつではあるけれど、次第にその距離が近づきつつあるのを感じていた。 つづく
〖注〗次回は、二人の心の変化を記して見たいと思います。内容はフィクションですが、昭和50年前後を想定しております。一番下の画像は「立待岬」です。ウィキペディア様より拝借いたしました。