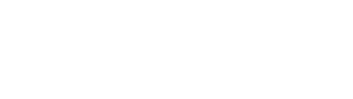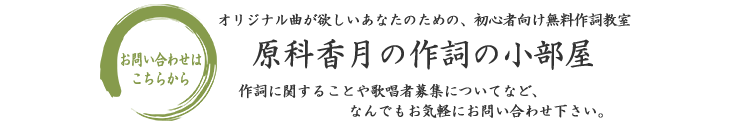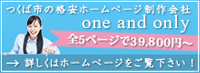課題テーマ「室蘭 トッカリショ」第3回
2016年05月24日
 作詞「トッカリショの伝説」第3回
作詞「トッカリショの伝説」第3回
前日に続いて、本日5月24日も仕事が休みですので、今朝も4時過ぎから後半を書き始めました。
前回の「トッカリショの伝説」で、お話ししたいことがあります。私は、まだアイヌの人達のことや生活の事などを、断片的に調べたに過ぎません。ですので僅かの知識ですが、第1章・第2章の中でそれを生かした部分をご説明したいのです。
昔のアイヌの女性は、口や顔の部分に刺青を施しています。口の刺青は大きなものです。手足の普段見える部位にもしています。女性のみしていることから、他民族からの襲撃の際、女性を守るためとの一説があります。ですが、はっきりしたことは分かっていないようです。
顔の刺青で独身か既婚かが分かるそうです。そしてまた年齢も分かるとのことです。女性の名前には、日本人の女性に「○○子」と付けるように、「○○マツ」と最後に「マツ」を付ける習慣があるそうです。
アイヌの人たちの分布は、今の日本の領土のみならず広範囲に渡っており、その地域ごとに習慣が違うので、すべてのアイヌ人には当てはまらないそうですが。
私は、この「トッカリショの伝説」で使っていますアイヌ人の名前は、適当に付けたのではありません。実際にあった名前の中から、少しでも使い易い名前を選びました.
このブログをご覧の方で、間違いに気付いたことやアドバイス等ががありましたら、ぜひご教授下さいますようお願いいたします。
予定では、第4章で終わらせるつもりでしたが、少し伸びてしまいました。第3章・第4章・第5章そして終章を一気にご覧いただきます。
創作「トッカリショの伝説」後半
第3章 イサエマツの父の戯れ
イサエマツを男手一つで育てたアイヤニは、セルゲイに対し娘の命の恩人という以上に、娘の近い将来の婿として実の親になったように感じていました。
ですが、幼い時からどれほど苦労して育ててきたかを意識せずとも、一人娘の心を虜にしたセルゲイに対し、嫉妬のような感情が芽生え始めていたことに、アイヤニはまだ気付いていませんでした。
ある日、遊びに来たセルゲイと3人での夕餉の時に、少し稗のお酒が回っていたアイヤニは、半分笑いながら言い出しました。
「セルゲイ、わしが大事に育てたイサエマツを嫁にやるんだから、わしの頼みも聞いてくれ。セルゲイの住むトッカリショの沖には、幻の魚と言われている金色の魚が泳いでいると聞いたことがある。セルゲイ、生きている間にどうしても、その幻の魚を見てみたい。わしのために捕って来てくれ!」
セルゲイとイサエマツはびっくりして、顔を見合わせました。確かにセルゲイも金色の幻の魚の話は聞いたことはありましたが、一度も見たことはありません。
ですが、少し稗のお酒に酔っていたセルゲイは、思わず言ってしまいました。
「分かりました。必ず捕ってきます。今から家に帰り、明日の朝早くに船を出します。待っていて下さい。」
セルゲイのことばに、イサエマツは驚いて止めました。
「幻の金色の魚は、誰も獲ったことがないんでしょ?お父さん、何でそんな無理なことを言うの?セルゲイさん、お願いだからそんなことやめて!」
アイヤニも本当に、セルゲイが幻の魚を捕りに行くと返事をするとは思ってもいませんんでした。軽い冗談というより、ちょっとセルゲイを困らせて、苛めてみたかっただけなのでした。言ってしまってから失敗したと反省しました。
若いセルゲイは、男が一度口にしたことを撤回することは恥と考えていましたので、後戻りは出来ないと腹を括りました。
イサエマツとアイヤニに止められたセルゲイは、「心配しないでも大丈夫。」と夜道を我が家に引き返しました。後から、イサエマツが追って来ましたが、優しく言い聞かせました。
「イサエマツちゃん、男が一度口にしたからには、出来なくとも挑戦しないと恥ずかしい。もし、どうしても駄目なときは観念して、お父さんに謝るから心配しないで大丈夫。数日で戻るからね。」
そのことばにイサエマツは父親の元に帰りましたが、夜、床に入っても寝付かれないイサエマツでした。何か言いようのない不安に駆られるのでした。
第4章 にわかに荒れ出した海
セルゲイは、前の晩にイサエマツの父親に話したように、夜明けを待って船を出すことにしました。イサエマツの家から我が家に辿り着いたのは、夜明けの数時間前でした。セルゲイの母親も妹のイコレイレマツも無理だからやめた方がいいと反対しましたが、イサエマツに話したように二人に話し、説得しました。
船に積んだのは、2日分の干物の食料と水、それに釣竿と網、それに塩漬けした餌用のイカとサバの切り身だけでした。トカリッショの夜明けは、それは美しいものでした。海は黄金色に輝き、陽の当たらない、モリのように尖ったような岩陰は、濃い藍色をしていました。
波はなく、セルゲイの船は滑るように沖に向い進み続けました。
「幻の金色の魚って、どんな魚なのだろう?」
セルゲイは想像しながら、ただ沖に向って漕ぎ続けました。
大分陽が高くなってきた頃、セルゲイは船を止め、竿を出すことにしました。何しろ初めての事ですから、エサは何が良いのかもわかりません。とにかくイカの切り身を針先に付けて竿を出し、しばらく様子を見ることにしました。
やっと一段落し、朝から何も食べていないことに気づきました。すると急にお腹が鳴りだしました。水を飲み、予め焼いたおいた干物を食べると、ひと心地がつきました。
いきなりです。ググッと竿先がしなり、何かが掛かりました。セルゲイは、漁師です。慌てることなく、ゆっくり獲物が弱るまで竿を立てて待ちました。
やがて水面に姿を現した魚は、約40cmの真鱈でした。もちろん初めから幻の金色の魚を期待していた訳ではありませんが、少しガッカリしました。
今度は、サバの切り身を針先に付け、また竿を振り出しました。まだ竿を出して僅かな時が流れたに過ぎず焦る必要はなかったのですが、イサエマツが心配していると思うと、何とか早く釣り上げたいものだと思わずにはいられませんでした。
塩漬けのイカとサバを替えながら、セルゲイが何度も竿を出す度に、何かしらの魚が釣れましたが、今まで何度も釣り上げたことのある魚ばかりで、金色の魚が掛かることはありませんでした。
時も大分たった頃、取りあえず今回は諦めることにしました。今日は無理でも、また明日もある。セルゲイは、そう考えました。
ふと見上げた空が、異常に黒い雲に覆われ始めていることに、竿先に集中していたセルゲイは、初めて気が付きました。この黒い雲が、今は静かな海を荒れ狂う海に豹変させることを、セルゲイは今までの経験から知っていました。
竿をしまい、急いでトッカリショの浜に向い漕ぎ出しました。黒い雲は、セルゲイの小さな船のことなど一切無視するように、空一面に張出ました。
「これは、暴風雨になる。一時も早くトッカリショにもどらなくては!」
セルゲイは、必死に漕ぎ続けました。しかし、何とか幻の金色の魚を釣りたい一心で、相当沖合まで来てしまいましたので、そう簡単にトッカリショの海岸に帰ることは出来ませんでした。
普通ならトッカリショの岬が見え始める海で、セルゲイの船は1枚の木の葉のように、嵐の中でただ成り行きにその身を任せていました。
「イサエマツに会うまでは、乗り越えなくては!何としても生き延びなければ!イサエマツを悲しませることだけはしてはならない!」
セルゲイは、神に祈りました。
・・・愛する人に合わせて欲しい。
愛する人を悲しませないで欲しい。・・・
荒れ狂う海からは、トッカリショの岬は見えず、セルゲイの船は大きく上下左右に飛び交いながら、浮かんでいました。
その時です。一際大きな波が、セルゲイの船を襲いました。
第5章 哀れイサエマツ
イサエマツは、自宅近くの山で山菜採りをしていましたが、強い風が吹き始めたので家に帰りました。
「セルゲイさんは、今日沖に出ている筈だけれど、大丈夫かしら?」
どうしようもない不安に、胸が押しつぶされそうなイサエマツでした。
次の日、イサエマツは眠れぬままに朝を迎え、セルゲイの家に向いました。父親のアイヤニも目を真っ赤にし、イサエマツを送り出しました。
セルゲイの家では、母親と妹のイコレイレマツがやはり一睡もせずに、夜明けと嵐の収まるのを待っていました。イサエマツが、セルゲイの家に着くころは、皮肉にもトッカリショの海はいつもの美しい姿のままでした。
3人は、浜に出てみましたが、特に変わったことはありませんでしたが、いつもなら置いてある筈のセルゲイの船は、小屋の中にも浜にもありませんでした。涙を流しながら、セルゲイの母親が言いました。
「イサエマツちゃん、心配しなくても大丈夫だよ。セルゲイは、きっと生きている。イサエマツちゃんを残して、死ぬはずがない!必ずどこかで生きている。だから諦めないで!」
そのことばは、イサエマツだけではなく、イコレイレマツに、そして自分に言い聞かせているようでした。3人は、いつまでも、いつまでも沖を見つめて佇んでいました。
あの日から、10日が過ぎました。セルゲイは、やはり帰っては来ませんでした。イサエマツは、セルゲイの家に泊まったり、家から通ったりしながら、トカリッショの浜で、沖を見続けました。
食べ物も喉を通らず,美しい容姿もふっくらとしたピンクの頬も肉が削げ、もはやすっかり以前の面影を失くしてしまいました。今日も、家からこのトッカリショの浜にやって来ましたが、その足取りは老婆のようでした。
それから数日して、イサエマツは浜で待つことを止めて、トッカリショの岬の上に登りました。岩にかじり付くようにしてやっと上ったイサエマツの瞳の中には、大きな決心が秘められていたのでした。
「だれが悪い訳ではないけど、私の愛する人は、もうこの世にはいないの?もし、今日逢えないなら・・その時は・・その時は・・!」
イサエマツは枯れたはずの涙をまた流しました。ただじっと沖を見つめて泣いているイサエマツの姿は、哀れを超えていました。
とても永い間、水平線の彼方を見つめていました。やがて夕闇が迫ろうとしていました。
「あの人は、ついに帰って来なかった。遠い所に行ってしまったのなら、私の方から逢いに行かなければ・・・!!」
イサエマツは、擦り切れそうな草履を脱ぐと岩陰に揃えて置きました。
終章 二つのお墓
岬の上の岩陰に揃って置いてある草履に気付いたイサエマツの父アイヤニは、イサエマツが覚悟のうえで飛沫の中に消えたことを知りました。
アイヤニは、せめて娘の亡骸を葬ろうと必死に浜や岩陰を探しましたが、いくら探しても見つかりませんでした。
「わしは、何と罪深い男なのじゃろう!このわしの愚かな戯れで、若い二つの命を奪ってしまった。わしは、この先どう生きて行けば神に許されるのだろうか?」
アイヤニは、トッカリショの岬の隅に、小さな亡骸のない二つのお墓を作りました。墓といっても、浜から拾った石を二つ並べ、二人の形見を埋めただけの粗末な墓でした。それでも、アイヤニ・セルゲイの母・セルゲイの妹イコレイレマツの3人は、両手を合わせました。3人の願いは同じでした。
― セルゲイとイサエマツが あの世で きっと幸せになっていますように! ―
その墓石の辺りには、蝦夷黄菅(エゾキスゲ)の黄色い花が、二人を見守るようにたくさん咲いていました。
アイヤニはその後、この二つの墓に週に一度は通い、セルゲイとイサエマツに詫びながら二人の墓を守り続けました。それは、アイヤニが82歳で亡くなるまで続いたとのことです。(終わり)
2日間に渡って、「トッカリショの伝説」を創作いたしました。これは、実際の伝説ではなく、わたし原科香月の創作です。わたしは「トッカリショ」の美しい海岸を背景に、作詞のために物語を創作したのです。特に深い意味はありません。ですが、この話を書きながら、涙ぐんだのも事実です。このわたしの創作を読んで頂き、僅かでも皆さんの心に響くものがありましたら、わたし原科香月にとってこれ以上の幸せはありません。
この物語から、次回は作詞に入ります。皆さま方の暖かいご支援をお願い申し上げます。