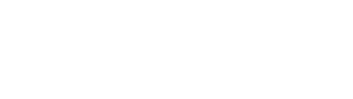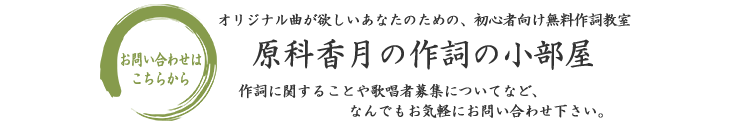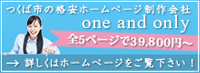創作の小部屋第9回「従 妹」
2018年07月01日
 創作の小部屋第9回「従 妹」
創作の小部屋第9回「従 妹」
もう50年も昔の思い出が忘れることなく、夏になると甦ります。当時私は高校2年生でした。二つ下の従妹がとっても好きでした。彼女は東京からお盆の時期に数年に一度、母の実家である私の家にやって来るのでした。
彼女と最後に逢ったのは、18歳の時で高校を卒業したばかりの時でした。当時、東京に住み始めたばかりの時に、従妹の家に遊びに行ったのです。従妹には逢えましたが、アルバイトに出かけるところだったらしく一言挨拶をしただけでした。
私が結婚してからも、子どもが生まれてからも、彼女は夢に何度も現れました。その都度目が覚めては、妙に胸が苦しくなりました。
もう50年も昔のことですので、当時同人誌に記載した短編小説『従妹』をアップしたいと思います。
「従 妹」
その①
「こうやりゃ、ここへくるんでしょう? 分かってるわよ。ウフフッ」
「分かってんならいいんだよ。」
僕は、恥ずかしそうに小さな声で言った。
洋子は何のためらいもなく、その美しい声で話す。
「やっぱりそうきたの?じゃ、しかたないわ。はいっ。」
「ウウン、エエト。アッ、こっちの方が危険だよ。そっちのほうは、心配いらないよ。」
「分かってんのよ。馬鹿じゃないからねぇ。誤魔化されないわよ。じゃあ、はい!」
「えへへ・・。はい、どうぞ。」
駒を一つ動かすと、僕は一瞬洋子の顔を見て笑った。
「そうですか?しつこいね。あんまりしつこいのはいやね。」
「ハハハハ、女のしつこいのも考えものだよ。」
「言ったわね。ここへ入っていらっしゃい。いいんだよ、いいんだよ。そのままおいでったら。歓迎するから。」
「恥ずかしいんだよ。」
「恥ずかしいなんて、柄じゃないくせに。ヒヒヒヒヒ。」
洋子は、茶目っぽく笑った。
僕と洋子は先ほどから、将棋をして遊んでいた。あいにく洋子は挟み将棋しかできなかった。僕はあまり好まなかったけれど、洋子ができないなら、仕方がなかった。それ以外に、楽しく遊ぶ方法がなかったのだから。
今日は家に洋子、祖母、そして僕の3人しかいなかった。あとのものは、何処かに出かけていた。祖母は昼寝をしていたので、実際は僕と洋子の二人だけ戸同じだった。
将棋を終えると。話しが急に途切れた。将棋をしていたときのあの親密さは消えて、お互いに無口になった。僕は洋子と話しがしたくて、何か言おうとするのだが口が動かなかった。
洋子は下を向いて、何か推理小説に目を通していた。僕は、縁側から庭に降りた。庭から門を出て、筑波山を眺めた。大きなあくびを一つして、空を見上げた。空は雲で覆われていた。どんよりとした雲だった。再び庭に戻って、花壇の花を見た。名も知らない花が、いくつか咲いている。匂いをかいでみると。何となく親しみのある香りがした。
縁側に腰をおろした。また空を見た。同じ雲だった。洋子の方を見た。やはり小説に視線を当てていた。座敷に上がった。洋子は、横にしていた身体を急にもたげて、正しく座った。僕は、何もすることがないので、畳の上を少し歩いて、立ち止まった。何か話そうと思いつつ言葉が出なかった。
洋子のいる部屋からちょっと離れた自分の部屋に入り、鏡を見た。光線の関係か、妙に美男子に写った。洋子に嫌われまいと思った。笑った。鏡も笑った。やはり自分で自信の持てる容貌であった。僕は、一瞬不安に思った。人は誰でも、自分のことは良く見えるものである。洋子は、果たして自分をどんな風に見てくれているのかが気になった。僕はこのとき、肉体だけが人間の全てではないことを、全く忘れていた訳ではないのだが。
洋子は、縁側に腰を下ろしていた。小説を右手に持っていた。近づいて洋子の方を見た。洋子は、多くの視線を浴びているかのような面持ちで、その表情をやっと保ち続けているのが分かった。僕は、やっとの思いで口を開いた。
「推理小説、面白い?」
「ウウン、あんまり推理小説って好きじゃない。」
洋子は、僕の顔を見ずに空間を見つめて言った。
「文学作品なんか読まない?」
「エエトネ、今嵐が丘を読みかけてるの。」
洋子はやはり空間を見つめたままだった。
「野菊の墓って、読んだことある?」
僕は、ちょっと恥ずかしさと期待の入り交じった声で聞いた。
「ウン、ある。」
今度は、一瞬僕を見て言った。
「泣かなかった?」
僕は、笑いながら聞いた。洋子は、恥ずかしさの交じった声で笑って応えなかった。
「あんなになりたいと思う?」
不意に洋子が、笑いながら尋ねた。
「ウン!」
僕は、反射的に応えた。
洋子は、さもおかしそうに笑った。僕も今言ったことが、おかしくなって笑った。
門を出て、筑波山を見た。何気なしに応えたその言葉を、お互いに理解し合えたのが、あまりに嬉しくて仕方がなかった。
野菊の墓の主人公の正夫と民子はいとこ同士、洋子と僕もいとこ同士だったから。
その②
僕はいつ頃から洋子を意識し始めたのか、よく覚えていない。おそらく小学生の頃からだったと思う。
僕が中学一年の夏休みに、洋子は母に連れられて家に来たことがあった。洋子は僕より二つ年下だから、小学5年生だった。洋子の母も何処かに出かけ、家には洋子と二人だけになった。
僕は恥ずかしさから、話しをすることができなかった。ただ遠くから、洋子の姿を眺めてばかりいた。何と洋子と楽しく過ごしたかった。しかし、何の考えも浮かではこなかった。
仕方なくいつか作った竹馬に乗ったりして、一人遊んだ。洋子が僕の方を見て笑っている。洋子には、おてんばいやお茶目といった方が適当だろう。そんなところがあった。
僕が止めると、洋子は真似をして、竹馬に乗った。ふらふらして、2,3歩進むと倒れそうになった。洋子は僕を見ながら、黄色い声を出して笑った。僕も洋子を見て笑った。このとき初めて笑いを交わした。洋子は、竹馬を隅に立てかけた。
またしても沈黙、お互い話しをする勇気もなく避け合った。
次の日、洋子は母親と東京の家に帰った。
洋子たちが帰るとき、僕は寝ころびながら、テレビを見ていた。ときどき洋子の方を盗み見た。洋子は何か元気がなかった。それにもまして、僕は悲しかった。洋子たちが、家族に別れの挨拶をしている。僕は、洋子のほうを見た。さようならということばすら忘れていた。洋子たちが帰ると両親も出かけ、家には祖母と二人だけになった。すべて失ったように、呆然と畳の上に突っ立っていた。ただそうしていた。そして、洋子の触れた竹馬を見つめていた。その後、その竹馬には触れなかった。そのままの位置を保ち続けておきたかったのだった。
その③
今度も洋子は母親に連れられてやってきた。僕は、友だちの家でアルバイトをしていた。そのお金で、長野の聖高原に旅行に行くつもりであった。
僕は妙な予感を抱いて家に帰ったのだが、予感は的中していた。自転車を小屋に入れて玄関に向かうと、洋子の母の声がした。
「ほら、帰って来たよ。」
ニコニコ笑っていた。僕は微笑みながら、会釈をした。家の中に入り、部屋の中を見回した。洋子の母、祖母、姉、そして祖母の背に隠れて誰かよく見えなかった。祖母が座敷に上がれと言ったが、ズボンを変えると庭に出た。
洋子でありますようにと拝む気持ちで、筑波山を見た。しかし、こころの隅では、そうでないことを祈った。
洋子と会うのがこわかった。4年振りに会う洋子の成長を知るのが恐ろしく、また自分の成長を知られるのが恐かった。
洋子は随分身体が大きくなり、顔形もずっと大人らしくなったように思えた。
大きな目、花のような唇、本当にきれいだと思った。なんだか急に寂しくなったしまった。洋子が、自分から遠い存在になってしまったように思えて仕方がなかった。
でもこの気持ちも、次の日には消えていた。
全く変わってしまったと思った洋子は、昔の面影を少しも変えてはいなかった。
かわいい容姿のまま、やさしくそして思いやりのこころも、そのままだった。
洋子が来た日の夕食での出来事。
夕食にしようという母の声で、僕は食卓に着こうとした。既に丸い卓袱台には、祖母・洋子・洋子の母と着いていた。ちょうど祖母と洋子の間に僕が入る形になっていた。僕がちょっとためらっていると、祖母が洋子に言った。
「洋子ちゃんは、お母さんの隣に座ったら?」
すると洋子は小さな声で、このままでよいと言った。僕はおずおず洋子の隣に座った。
「いただきます。」
みんなが食べ始めた。じっとしていられず、僕は妙な早さで箸を運んだ。全く不自然だった。少したつと、洋子が席を立った。洋子の母は心配そうに、「もういいの?」と聞いた。
僕は興奮で胸が詰まり、食欲は全くなかった。もしかしたら、洋子も同じだったのかも知れない。しかし、僕は洋子がどんな態度を示そうとも、洋子が僕のことを好きなのだという確信は少しも持てなかった。
その夜、洋子とは少しも言葉を交わすことはできなかった。
次の朝、僕はあまりに息苦しく、5時半に起きた。昨夜は、全く熟睡することができなかった。洋子がいる、それだけで胸が苦しく眠れなかったのだった。
登校日だったので、7時半頃家を出た。
学校から帰ってくると、近所のおばさんが孫を連れて遊びに来ていた。洋子がその女の子を遊ばせていた。何の飾り気もなく、洋子は真からその子を可愛がっている。子ども好きのようであった。
僕が服を変えて縁側に行くと、洋子は将棋の用意をして待っていた。背中にその子が乗っていた。洋子は微笑みながら、その子をあやしていた。ぼくの中の恋心が、また大きく芽生え始めたことに気付いたけれど、それは誰にも止める権利のない僕の自由だと思った。
「将棋、する?」
僕は快く返事をすると、駒を並べ始めた。僕は、何度も何度も洋子の顔を見た。いつも洋子は微笑んでいた。洋子の指先は、細く白かった。
不意にそこやらないでと、洋子は笑いながら声を出して言った。そして駒を打とうとした僕の右手をつかもうとし、すぐ意識してその手を引っ込めた。意識してなど手に触れることさえ出来ない僕には、とてもこのような偶然が本当は嬉しかったのだけれど。
しばらくすると、洋子の背中の女の子がぐずりだし、将棋を続けることが出来なくなってしまった。
少し経って洋子と女の子がいなくなったのに気付き、僕は畑の方だろうと犬を連れて行ってみると、背中に女の子を背負った洋子が見えた。
僕は小さな勇気を出して、洋子に向かって歩いた。
「散歩?」
「ウン、三歩じゃなくて四歩だよ。」
「もう、四歩より、歩いたんじゃない?」
声を出して、お互いに笑った。僕と犬の後から、洋子は女の子を背負って付いてきた。僕は嬉しかった。
「高校、もう決まった?」
僕が聞いた。
「ウウン、まだ私たちなんか、まだ全然平気なの。誰もそこまで考えてないみたい。かえって、親たちの方が心配しちゃて。」
少し歩くと、二つに分かれている道になった。
「どっちに行くの?」
「こっちに行こうか。」
曲がろうとしたとき、雨が降ってきた。洋子と家に帰ることにした。背中の女の子が重そうだった。
「俺が、負ぶっていくよ。」
女の子を洋子から受け取って、背中に乗せようとしたとき、女の子は大きな声で泣き出した。仕方なく、洋子が背負って歩いた。
洋子の後ろを歩いた。女の子を背負っている洋子と筑波山が調和して、一つの絵画になったとき、また別な新鮮な魅力を感じた。
その④
今、野菊の墓の正夫と民子のようになりたいかという洋子の質問と、それに対する自分の返事を思い出し、くすぐったいとでも言おうか何か気恥ずかしさのような思いがした。
本当に好きでならない洋子と自分とが、民子と正夫にだぶって思えたからであった。が、決して失恋という形では終わったりしたくないと強く思った。僕は、このとき洋子との結婚ということを思った。
このような素晴らしい人と一生を過ごせたとしたら、例え世界中でどんなに美しく気立てのよい人が存在しようとも、僕は一生涯洋子を愛し通せそうな気がした。
僕は、もっと洋子と親しく仲良く過ごしたいという欲求から、何か楽しいことをしようと考えた。そして、ビール瓶の口の上にマッチ棒を乗せ合うゲームを思い付いた。
ビール瓶とマッチ棒を持って、洋子のいる部屋に行くと、もう推理小説は読んでいなかった。
「これ、やる?」
「どうするの?」
僕が要領を簡単に説明すると、洋子はすぐ理解した。また、将棋の時の親密さに戻った。何もしていないときこそ言葉を交わすことのない二人だが、こういうときは、お互い何の遠慮もなく言い合うことができるのである。
「あっ、あぶない。どうしようかな?」
洋子はそう言いながら、おそるおそるマッチ棒を乗せていった。
「キャー、アアアー、もうだめだ。負け!」
洋子は残念そうな顔で言った。
「これ、そっちのでしょ。はいっ、遠慮しないで貰っといたら!」
洋子は、自分のマッチ棒をわざと僕のだと言って渡した。
「これ、俺のじゃないからいらないよ。増えたって徳にならないから返すよ。」
そういうとすかさず
「たくさんあるときは、分けてあげなさいって。私、欲がないから欲しくないの。これ、あげる!」
僕たちはすっかり打ち解けた時間を、しばらく過ごすことができた。今が一番幸せなのだと自分の心に言い聞かせつつ、僕はその楽しさの中に心身共に酔っていった。今の僕は、もう完全に洋子に魅了させられていた。
洋子が来てから、今日で3日目である。今日も午前中は学校で過ごし、午後から洋子と遊んでいるのである。洋子は明日帰ってしまう。僕は洋子を土浦駅まで送ってやりたいものだと考えた。アルバイトに行かずとも、そうしたいと思った。しかし、洋子のことが好きだから、わざわざ送ったりするのだと、洋子の母や家族の者に思われるのが恥ずかしく、また別れが余計に悲しくなるのでは考えた。
やはりいつものように、朝早くアルバイトに出かけてしまうことにした。
その晩も将棋やトランプを二人でして、楽しい時間を送った。
「さあ、寝ようか?」
洋子の母がそう言ったとき、僕は強い寂しさに襲われた。もう、これで分かれてしまうことになる。明日は、一言も話せず出かけなければならないと思ったからである。
洋子を見た。紅色の唇が濡れていた。真っ白な胸元がのぞき、中央のあたりが低く隆起していた。
また明日から、孤独な日を送るのか!また明日からな目的のない空虚な日を送るのか!自分の部屋に入ると、急に目頭が熱くなった。
本当に、洋子が好きでならない。たまらないほど洋子が好きでならない。さようなら。
朝が来た。まだ時間は早かった。みんな寝ていた。一人朝露の畑道を歩いた。
筑波山は、霞んでいた。
僕が洋子を好きなのは、偽りのない真実だ。しかし、洋子が僕を好きだという確証はない。僕のような外見の良くない人間が好かれる筈はないかも知れない。
だけど人間は外見が全てではない。いや、そんなことは、人間を判断する一つの手段にもなりはしない。
僕が、心から洋子が好きなら、僕は人格を向上さえなければならないはず、本当に好きなら。それが愛というものではないか
僕が洋子のように、いやそれ以上に人格を向上させなければ、洋子を愛する資格がないのではないか。
ひとり考えながら歩いた。
家に着くとみんな起きていた。洋子は、洋子の母の髪の毛を梳いていた。
その姿は、母の深い愛情の中ですくすく育つ天使の如き優しさに満ちていた。
僕は、激しくなる胸の鼓動を押さえきれぬまま、一冊の日記を洋子に与えた。
洋子は一瞬驚いたようであった。
行かねばならない時間が来た。
「それじゃ、またいつか来てよ。」
僕は洋子と洋子の母に向かってそう言った。
洋子の母は、また来るねと僕に言った。洋子は、寂しそうな顔で僕を見ていた。
僕は笑顔を装って、もう一度洋子の方を見た。やはり寂しそうであった。
自転車を走らせた。門を出た。ペダルを思いっきり踏んだ。
精一杯の早さで走った。何も考えたくなかった。何も思い出したくなかった。過ぎたことは、過去のことと割り切ろうと思った。
洋子・・・思わず口に出した。
すると急にたまらなくなった。頬を一滴の涙が走った。自転車を夢中で飛ばし続けた。 (おわり)
今読み返しても、昨日のことのように、その一瞬一瞬を思い浮かべることができます。そして、また胸が苦しくなります。青春の日の思い出は、生ある限り私の脳裏から消えることはありません。