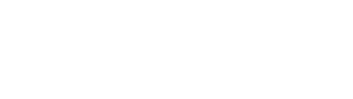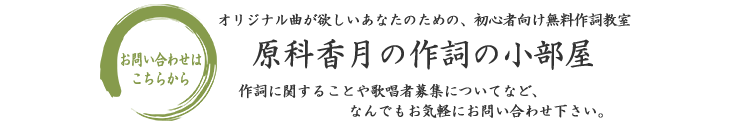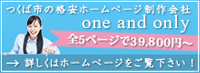創作の小部屋「函館物語」第5回
2022年02月13日
 創作の小部屋「函館物語」第5回
創作の小部屋「函館物語」第5回
本日13日は、また大雪の可能性ありとの気象庁から、注意の喚起がありました。先日の雪は、つくばは夜半に降りましたが、翌日は普段通りの生活が出来ました。祝日だったことも幸いしたと思います。都会ですと交通網に影響が出て、仕事や帰宅に困難が生じることが良くあります。
ところで、北京冬季オリンピックのノルディックスキージャンプ混合団体で、規定違反により高梨選手など相次いで失格者が出た問題ですが、選手の競技が終わってからの計測ではなく、競技に入る前にすべきだと思います。もし規定違反なら、スーツを取り換えさせるという方法がベターだったと思います。ましてや、全選手を対象としない計測などあり得ない話です。高梨選手には笑顔で帰ってきて欲しいと思います。
羽生弓弦選手の4回転半のジャンプへの挑戦は、見事だったと思います。これまで故障に悩まされながらも苦しい研鑽を積み、敢えて挑んだ未踏の世界への挑戦。その気持ちは金メダル以上の価値があったのではないかと思います。
創作の小部屋「函館物語」第5回
第5章 未来への一抹の不安
まだ、昼までは少し早かったけれど、私は真知子さんの作ってくれたお弁当をご馳走になった。ありふれた言い方しかできないけれど、とても美味しかった。ゴマをまぶしたおにぎり・鳥のから揚げ・卵焼き・ウィンナーソーセージ・それからトマトとキューリの生野菜。見た目もすごくきれいだった。真知子さんは、使い捨ての紙容器にそれらを載せて、私に「どうぞ」と言って渡してくれた。野菜には和風のドレッシングをかけてくれた。
今でこそ、お弁当の定番かも知れないが、当時はとても珍しかった。
「このお弁当は、私が小学生の頃、家族で五稜郭公園や函館公園とかにお花見に行くとき、いつも母が作ってくれたお弁当なの。だから、私はこのお弁当が今でも大好きなの」
私は幼いころから、決して贅沢な食事はしたことがなかった。母は漁師から、小さすぎて売れない小魚などをいつも貰ってきては、煮たり焼いたりしておかずにしてくれた。真知子さんのお母さんのような洒落たお弁当を食べたことはなかった。
「真知子さん、とても美味しいよ」
私は、おにぎりを頬張りながら言った。真知子さんは、とても嬉しそうだった。
「今度は、おにぎりじゃなく、サンドウィッチにしょうかな?晴彦さんは、どっちがいい?」
「僕は、真知子さんが作ってくれるなら、何でも嬉しいよ」
二人にとって至福の時間が流れた。津軽海峡の沖は、太陽の光を浴びて銀色に輝いている。タンカーらしき船が、水平線の眩しさの中を航行していた。
「真知子さん、お弁当を食べ終え少し休んでから、大森浜に一緒に行かない?」
私が遠慮がちに言うと、真知子さんは笑って言った。
「大森浜に?アッ、分かった。東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる。 ねえ、そうでしょ?」
この啄木の歌は、大森浜で詠んだものと言われているが、一説によると当時は大森浜には蟹はいなかったらしい。それでも私は勝手に、大森浜で啄木は涙を流したと解釈している。生活苦のためか、世に認められぬ自分が惨めだったのか?
暫くして私と真知子さんは、お弁当を食べた後片付けをし大森浜に向かった。来るときに見た啄木一族のお墓を通り、途中から住吉漁港に向かって右折した。後は大森浜まで一直線だ。ここからは、多分10分も歩けば着くはずだ。
「真知子さん、僕が我がままを言い出したものだから、随分と歩かせちゃってゴメンね」
「私は、運動は得意じゃないけど、歩くのは大好きよ。晴彦さんと一緒ならよけいにね!」
真知子さんはそう言うと、私の手を引っ張り、先を歩き始めた。男の私が、女性に手を引かれて歩く姿は自慢にならないけど、真知子さんなら大歓迎だ。私は、前から聞こうとして言い出せないことがあった。今なら、平気かなと思った。
「真知子さん、今更聞きづらいんだけど、僕が今の病院に就職した時には、既に真知子さんは働いていたよね。僕よりお姉さんになるのかな?別に、たいしたことじゃないんで、聞かなかったんだけど」
真知子さんは、一瞬戸惑った表情を浮かべたが、すぐ笑顔になって言った。
「多分、生まれた年は同じで、私が早生まれ。だから、学年は私の方が一つ上になるかも」
真知子さんは、それがどうしたのという風に、私を見つめて言った。
「いや、別にどうでも良いことなんだけど。一応、知っておきたいと思っただけ」
そう答えた後、僕は愚かにも、まだ話題にもすべきでないことを口走ってしまった。
「そういえば、真知子さん、一人っ子だったよね。両親から、何か言われているの?」
真知子さんが気分を害するかも知れないことを、少しのためらいはあったけれど、無遠慮にも聞いてしまったのだ。
いつもニコニコ笑顔の絶えない真知子さんだったけれど、この時ばかりは一瞬顔を曇らせた。
「私の父は、建設会社を経営しているの。私は薬剤師だから、家業は継げないし。父は、いろいろ考えているみたい。いずれお婿さんを貰って、お婿さんに会社を任せたいようなことを、私が中学生の頃言ったことがあるわ。でも、今の私は、そんなことは考えられないわ。私は、好きな人と一緒になりたい」
私は、真知子さんといるときは、心から幸福感で一杯になる。このまま二人で一生を過ごせたら、私の人生はどれだけ輝けるものになるだろう。だが、この時の私は、果たして二人に明るい未来が待っているのだろうかと、少し不安になった。よそう、そのことを今考えるのはよそう!まだ、ずっと未来の話だ。もし、そういうことで悩む日が訪れても、乗り越える方法はきっとある。二人で考えれば、最良の道が必ずある。そう信じることにした。
また、仲良く手を繋ぎながら、あまり意味のないことを話し合いながら歩いていくと、いつの間にか大森浜に着いた。ここには、啄木小公園がある。地元の人が何人か歩いていたが、公園の啄木像には目もくれず真っすぐ海岸に歩いて行った。余り関心がないのかと思った。
啄木の坐位の銅像をみた。本で見るいつもの写真の顔と少し違ったように感じた。啄木が過ごした明治40年頃とは、どういう時代だったのか?また、啄木への感慨に浸り、真知子さんをほんの一瞬だけ忘れた。
二人で啄木小公園から砂浜に降りる途中で、真知子さんは私の顔を覗き込むようにして言った。
「晴彦さんは、本当に石川啄木が好きなのね。でも、今度は、私が行きたいところでもいいでしょう?見晴公園は、秋の紅葉の時期に何度か行ったことがあるけど、人が多すぎて疲れちゃうの。今の季節なら、新録がきれいで、人も多くなく、静かでゆっくりできると思うの。どう、晴彦さん?」
私にはもちろん異存がある筈はない。しつこいかも知れないけど、私は真知子さんと一緒ならどこでも楽しいのである。見晴公園、とても良い名前の公園だ。私は、一刻も早く真知子さんと訪れたくなった。
「了解しました。喜んで、お供させていただきます。嬉しいな、いつにする?」
もう私は、すっかりその気になっている。真知子さんは、目を丸くして言った。
「随分、気が早いのね。私も、母と買い物や、これでも何かと忙しいのよ。でも、晴彦さんを先ず第一に優先するわ」
大森浜の沖を見つめながら話していると、いつの間にか、周りには人の気配がなくなり、二人だけの世界になった。啄木の像の後ろには、さっきまでいた立待岬が見える。
「今日は、疲れたでしょう?僕のせいで、大分歩いたし。そろそろ帰ろうか?」
そう言うと、真知子さんは少し寂しそうに言った。
「まだ日暮れまでには時間があるし、もう少し、晴彦さんとこうして一緒にいたいわ」
真知子さんとは手を繋いでいるので、手繰り寄せれば、彼女は私の腕の中だ。大好きな真知子さんを抱きしめて、口づけをしたいという欲求が血潮となり、私の全身を駆け巡った。だが、私は意気地のない男だ。もし、嫌われたらと思うと、行動に移せない。彼女は私にとって初めての女性だ。私には、女性の気持ちが分からない。迂闊には動けなかった。
それから、二人は帰宅の途に就いた。朝、待ち合わせた函館駅前で別れた。次回のデートの日は決めてなかったが、私は毎日でも二人だけで逢いたかった。
函館駅からの帰りのバスの中で、どうしても気になることがあった。私が長男で彼女が一人っ子のことだ。何とかなる!そう信じようとしたが、一抹の不安を拭い切れなかった。 つづく
※ 「啄木小公園」の啄木像と大森浜、それに見晴公園の画像は、函館市公式観光情報さまよりお借り致しました。今後のストーリーですが、お互いがどんなに好きであっても、それだけでは思い通りにはならないという筋書きになりそうです。