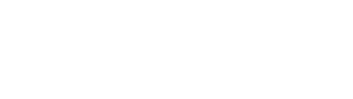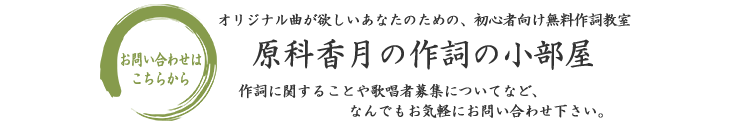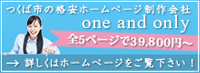創作の小部屋「函館物語」第11回
2022年03月22日
 創作の小部屋「函館物語」第11回
創作の小部屋「函館物語」第11回
先日の春のような陽気が嘘のような今日の雪です。まさか雪が降るとは思っていなかったのでびっくりしました。アイキャッチの薄紅色の梅の花と、これからアップします画像は、昨日近所を散歩をしていて撮ったものです。昨日の天気と比べ、本当に驚きです。
道路わきに咲くスイセンの花です。
菜の花ではなく白菜の花です。風でブレてしまいました。
両側の石灯籠の間から筑波山を撮りました。
本日、私の住む茨城県からは「電力需給ひっ迫に伴う節電のお願い」という内容の通知が携帯に入りました。どういう事情か良く分かっていないのですが、とにかくエアコンを止めました。それから万が一の停電に備えて早めの入浴をしました。
「函館物語」も多分残すところもう数回で幕となりそうです。第11回をさっそく始めさせていただきます。
創作の小部屋「函館物語」第11回
第11章 初めてのペアリング
私は9月より消化管造影検査室配属となった。私は少しでも早く、この仕事のプロにならなければと考えた。医師の正確な診断に役立つ仕事をしなければと、私は休日も専門書を読み続けた。
平日は、土井先輩にお願いし技術的な指導を受けた。土井先輩は、将来の放射線科を担う器の大きな人だ。きっと辛い思いして得たに違いない、貴重な知識と技術を欲しげもなく私に提供してくれたのだった。
それだけではない。検査を受ける患者さんの心理までをも丁寧に教えてくれた。思いやりを込めた、たった一言の言葉掛けが患者さんの不安と恐怖を和らげると、真剣な眼差しで自らに言い聞かせるように土井先輩は話してくれた。
土井先輩のような技師に検査をして貰えたら、患者さんも安心して身を任せることが出来るに違いない。私は土井先輩に心から尊敬の念を抱いた。
そう言えば、真知子さんとはしばらくデートもしていない。
今朝も疲れから10時過ぎに起きだし、遅い朝ご飯を食べると、私は病院から借りてきた分厚い専門書を開いた。だが、開いては見たものの、真知子さんの顔が浮かんで集中できない。困った私は、電話器の前でしばらく悩んだが、思い切って真知子さんの家に掛けてみることにした。鼓動の激しさを感じつつダイヤルを回すと、真知子さんの明るい声が聞こえてきた。私は、ホットして言った。
「もしもし、あのう勉強するのが疲れちゃって・・・」
そこまで言うと、私に任せなさいと言わんばかりに真知子さんは言った。
「どうしたの?疲れちゃったの?私が上磯までポットにコーヒーを入れて届けてあげる」
私は、普段着のまま上磯の駅に向かった。
真知子さんは優しい。真知子さんの届けてくれたコーヒーを、漁港の堤防でペンキの剥げた長椅子に座って飲んだ。その前に、私は彼女のスカートが汚れないように、ポケットから少し色あせたハンカチを取り出し、真知子さんの座る位置に置いた。
「真知子さん、僕は普段あまりコーヒーは飲まないんだけど、このコーヒーは香りもいいしコクがあって美味しいよ」
私は自分の味覚が正しいのか自信はなかった。
「へえ~ 晴彦さん、なかなかコーヒー通なんじゃない。私もこのコーヒーが大好きで、いつもこのメーカーに決めているの。これインスタントなのよ。そうは思えないでしょ?」
真知子さんは、函館で名の売れている洋菓子店のクッキーをバックから取り出した。
「勉強して頭が疲れたときは、甘いものが良いのよ。残ったら持って帰って後で食べてね」
私の手を取り、私の右手にクッキーを乗せてくれた。
「このコーヒーにクッキー、とても合うよ。ありがとう、真知子さん」
港も今日は日曜日だ。遠くで何人かが釣りをしていたけれど、誰も二人など眼中にはなく、竿先の彼方を見つめているようだった。
真知子さんは、いつかのように私の肩に上体を預けた。私は日中にも拘わらず、真知子さんの体を引き寄せ、口紅が薄く引かれたピンクの唇に自分の唇を重ねた。
二人は暫くそうしていた。私は、これが青春なのだと心に言い聞かせた。これが青春を謳歌するということなのだと自らに言い聞かせた。彼女と唇を合わせることは、世界で一番素晴らしい人を私一人が独占し、これからの人生を彼女守って生きていくのだという覚悟の儀式のように思われた。
私を心から信頼し、私の胸に身を委ねる彼女はたまらなく愛しい。だが、いつまでもこうしている訳にはいかなかった。私は、時計を見た。時計の針は、もう直ぐ午後1時を指している。私はいつかの約束をふと思い出して言った。
「真知子さん、もう午後1時だよ。お腹すいたでしょ?これから、通りの食堂でお昼を食べて、それから指輪を買いに行こう!」
私は真知子さんに耳元へ優しく言った。
「エッ ほんとう!うれしい!」
真知子さんは私から身を離し、私の顔を覗き込むようにして言った。それから、再び私の胸に顔をうずめた。少しして顔を上げた真知子さんの頬には涙が光っていた。
上磯駅前は、私の庭のようなものである。よく行く中華屋さんに入った。真知子さんは味噌ラーメンを食べたいと言った。私は、中華丼にした。暫くして味噌ラーメンと中華丼は運ばれた。真知子さんは美味しいと言いながら麺をすすった。彼女は食べ方も上品だ。私のように大きな音を立てたりはしない。ふと、私は財布の中身が気になりだした。これから二つの指輪を買おうとしている。まだ給料を貰ったばかりだけれど、当然大金など持ち合わせている筈はなかった。
貴金属を売っている店の前は何度か通ったことがある。だが、入るのはもちろん初めてだ。この店には真知子さんの気に入る指輪はあるだろうかと、私は心配になった。店のドアを開けて、私は真知子さんを先に入れた。真知子さんは、とても嬉しそうだ。お嬢さん育ちの真知子さんには、私のように財布の中身を心配することはないのだろうか?
陳列棚の奥にいた20代と思しき女性は「いらっしゃいませ」と言いながら、笑顔で二人の前に歩み寄った。
「ご婚約かご結婚の指輪をお探しですか?」
私が言葉に詰まっていると、真知子さんが答えてくれた。
「いえ、まだ婚約をしている訳ではないんです。でも、二人揃いの指輪が欲しいと思いまして」
女性店員は金額の張る指輪から順に、二人を案内した。それらの指輪に付けられた値札を見ると、私の給料ではとても手が届かないものばかりだった。私の顔色を見た真知子さんは店員に向かって言った。
「あのう、先ほどお話ししましたように、結婚指輪とか婚約指輪とかじゃないんで、高価なものじゃなくても良いんです。ちょっと他のも見せて貰っても良いでしょうか?」
奥の隅にある陳列棚へと真知子さんは私の手を引いた。
「この金額くらいで、私たちに合う指輪が欲しいんですが」
真知子さんが、女性店員に指で示した指輪の値札は、1万円に満たないものだった。いつも思うことだけれど、いかなる場所でも真知子さんは物怖じしない。何の知識も度量も持ち合わせていない私は、末広町でのお寿司屋さんの時のように、真知子さんに任せるしかなかった。男として少し情けないと思った。
安物と言える指輪でも、二人にとっては貴重なものである。真知子さんは、いくつもの指輪をケースから出して貰ったりしたが、なかなか決められなかった。女性店員は、他にお客がなかったためか、二人の我儘に愛そう良く接してくれた。
暫くしてから、やっと二人の指に合うお揃いの指輪に巡り合えた。可愛いケースに入れて包装してくれ、赤と青のリボンもサービスで付けてくれた。私はレジに行き財布を開いて思わず慌てた。
「赤いリボンの指輪は、晴彦さんからのプレゼントとして頂くわ。青いリボンの指輪は、私からのプレゼント。だから、お金はそれぞれ出し合いましょう!」
真知子さんは私の財布の中が見えたのか、とにかく私は半額の支払いで恥を掻かずに済んだ。お店を出ると、真知子さんは私に寄り添いそっと腕組みをして来た。私の胸は思わずキュンとなり、私はますます真知子さんが愛しくて堪らなくなった。
それから二日後、病院からの帰りにいつものバス停で私が待っていると、真知子さんは私の姿が見えたのか走って来た。今日もバスの席は空いていて、二人は仲良く並んで座った。
「あのね、あの日晴彦さんと上磯駅で別れて帰った夕方にね、台所で指輪のことを母に話したの。そしたらとても喜んでいたわ。その晩、父は会合とかで遅くなるらしかったけど、私たちのこと話したみたいよ」
真知子さんの表情は明るかったので、私の危惧していたことは、単なる杞憂かと安堵したのだった。
不思議なことに、その頃から真知子さんの様子が変わった。帰りのバスで会うことが少なくなり、会っても真知子さんの表情は暗く沈んだ様子だった。私が掛ける言葉も上の空のようで、下を向いて今にも泣きだしそうだった。
私は、ただオロオロするばかりで、何が何だか分からなくなった。 つづく
※ 漁港の画像はイメージです。北斗市の漁港ではありません。