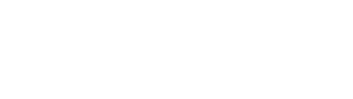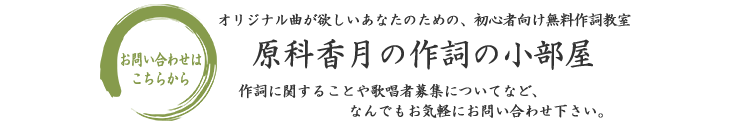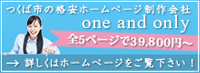創作の小部屋「函館物語」第12回
2022年03月30日
 創作の小部屋「函館物語」第12回
創作の小部屋「函館物語」第12回
アイキャッチ画像は、次回の「霞ケ浦物語」の下見を兼ねて先日撮った「土浦港」です。土浦駅東口から歩いて僅かの所にある港です。漁港ではなく、たくさんのヨットが並んでいるヨットハーバーです。
つくばは桜が満開です。本日は生憎曇り空でしたが、つい誘われてしまいました。
この花はシドミでしょうか?鮮やかな赤色です。
この「函館物語」もあと数回で終わる予定です。いつも書き終えたら直ぐアップという形を取っていますので、後から修正が必要になると思っています。一番心配なのは、脈絡と整合性です。ですので、時々読み返したりしながら書き進めています。
真知子さんと主人公を幸せのまま終わらせたいとは思います。ですが現実に、愛し合いながらも添い遂げられない悲恋というものが存在するのも事実だと思います。
創作の小部屋「函館物語」第12回
第12章 こころの叫び
月日の流れるのは早い。もう10月も半ばだ。私はもう半月近くも真知子さんと言葉を交わしていない。病院の薬局の奥に一瞬その姿を捉えることはできたが、顔を合わせることはなかった。
函館は8月から9月によく雨が降る。だがこの頃に何度もデートをしたり逢ったりしたが、雨に降られることはなかった。だが、10月に入り真知子さんと逢えなくなってからはよく雨が降った。
私はひとりバス停で真知子さんを待ったが、今日も真知子さんは来なかった。空いている席に座った私は、ぼんやり外を眺めていた。すると窓ガラスに水滴がしたたり落ちて来た。今日もまた雨である。
9月の初旬に、きじひき高原に行った時の真知子さんの言葉を思い出した。その時彼女は弾んだ声で言った。
「晴彦さん、私と一緒の日はいつも晴れね!私は晴れ女なのよ。私と一緒にいれば、一生、雨に濡れる心配はないわよ」
確かに彼女と一緒にドライブしたきじひき高原の時も、彼女の家に初めて伺った時も雨は降らなかった。二人でペアリングを買った日もそうだった。だが、彼女の言う通り、真知子さんのいない私一人の時には、どうしてこうも雨が降るのだろうか。この雨は、真知子さんが泣いているのか、真知子さんの涙なのか。それにしても真知子さんは一体どうしてしまったのだろう?
先月、上磯までコーヒーを届けてくれた日に彼女が言ったことばを私は思い出した。
「あのね、あの日晴彦さんと上磯駅で別れて帰った夕方にね、台所で指輪のことを母に話したの。そしたらとても喜んでいたわ。その晩、父は会合とかで遅かったらしかったけど、私たちのこと話したみたいよ」
その時の真知子さんの声は、確かに弾んでいた。それから彼女に何があったのだろう?真知子さんに心変わりがあったとは思えない。私は家に帰り、深夜に寝床に入ってからも考えていた。ふと思った。私が危惧していた、彼女のお父さんが原因ではないのだろうか?
私は、仕事中も気になって仕方がなかった。ある日の水曜日、私は5時ちょうどに私服に着替えて、職員通用口の近くで真知子さんの姿を待った。どうしたのかと訝しげに見つめる職員の姿もあったが、それどころではなかった。
暫くすると、真知子さんは通用口に現れた。私の姿を見ると驚いて、一瞬立ちすくんだ。私が「一緒に帰ろう」というと、頷いてハイヒールに履き替えた。バス停まで二人とも無言だった。少し待つとバスが時刻通りに現れた。バスの中は空いていたが、私はもちろん真知子さんと並んで座った。
真知子さんの表情は暗く沈んだ様子だった。私が掛ける言葉も上の空のようで、下を向いて今にも泣きだしそうだった。私は、どうしていいのか分からず、オロオロするばかりだった。真知子さんの降りるバス停が近づいた時、私は予め考えていた言葉をやっと伝えた。
「真知子さん、今度の日曜日、市電函館ドック前で午後2時に待っているよ。必ず来てね!」
他に客は数人いたが、私は真知子さんの横顔に少し大きな声で言った。真知子さんは小さく頷いたように見えた。それから日曜日までが長かった。早く真知子さんから事の真相を聴きたかった。だが、真知子さんを疑う気持ちは微塵もなかった。バスの中の真知子さんは、私の胸の中で思いっきり泣きたがっているのが私には分かったからだ。
ちょうどその頃、私の父が出勤途中で交通事故を起こし、救急隊の力により近くの総合病院に入院したのだった。幸い大きな怪我ではなかったが、それでも2週間の入院を余儀なくされた。私は仕事帰りに父の病室に寄り、洗濯物を届けたりと持ち帰ったりと、心の余裕を少し失いかけていた。
私の一方的にお願いだったので、約束とは言えなったが、真知子さんは必ず来ると私は信じていた。
(画像は、函館港です。ウキペディア様から拝借致しました)
真知子さんと会う日の午後、赤く腫らした瞼のまま、私は市電函館ドック前で降りた。私の告げた2時にはまだ随分時間があった。私は最近食欲がない。当然だった。母はそんな私に気付いたのだろう。今日も、出かけるならご飯を食べてからにしろ、と命令口調で言った。既に成人になった息子であっても、母は言葉を掛けずにはいられなかったのだろう。
雨が今にも降りそうだった。私は、折り畳み傘を2本用意して来た。辺りを散策していると、釣りをしている人が結構あちこちにいた。釣り人同士の会話から、狙いはアイナメやサバのようだった。私も釣りが大好きで、幼いころから近くの漁港の堤防でよく竿を振った。雑魚ばかりだったが、持ち帰ると母は焼いてくれたり煮てくれて、おかずの足しにしてくれた。あの頃が妙に懐かしくなり、私は目頭を押さえた。
漁港を歩いていると、時は確かに流れていた。真知子さんが市電から降車する時間が近づいた。私は市電函館ドック前に急いだ。何人かの釣り人が降り、最後に真知子さんが降りてきた。私は、精一杯の笑顔で声をかけた。
「真知子さん、今日は来てくれてありがとう」
真知子さんの綺麗にまとめられた髪の、その後れ毛が風でなびいた。真知子さんは、厚手のセーターにスカート姿だったが、いつもの華やかさはなかった。私に向けられた瞳には輝きがなく、視線は彷徨っていた。
私は、真知子さんの手を握り、どこに行くという当てのないまま歩き出した。結局先ほどの堤防の辺りに向かった。私は独り言のようにつぶやいた。
「毎日がつまらない。あれ程頑張ろうとしていたレントゲンの仕事もつまらなくなった。僕は、真知子さんが傍にいないと何もできないし、生きている意味が分からなくなってしまう。毎日、真知子さんはどうしたのだろうと、そればかりを考えて夜もよく眠れない」
私が話していると、真知子さんはいきなり嗚咽し始めた。私は驚いて漁港の傍の小さな公園に真知子さんの手を引いた。長椅子に座ろうとした真知子さんを止めて、私は自分でアイロンをかけた青い縞模様のハンカチを敷いた。
真知子さんは泣き続けている。私は、どうしていいのか分からなかった。ただ、真知子さんは私が嫌いになった訳ではないと知った。
「真知子さん、どうしたの?僕は、心に大きな穴が開いたようで、毎日が辛くてしょうがないよ!」
私が言い終わる前に真知子さんは体を私の方に向け、私の胸に顔を埋めた。大粒の涙が溢れているのが分かる。今まで我慢していた辛さを、そして悲しさを、ありったけ私の胸に吐き出しているかのようだった。
私は真知子さんの体を抱きしめたまま、泣き止むのをじっと待った。ポケットからティッシュを取り出し、真知子さんの頬をそっと拭った。
どの位そうしていただろうか?少しは気が晴れたのだろうか?真知子さんの泣き声が消えた。
「真知子さん、お父さんに何か言われたの?」
私の質問の答えではなかったが、真知子さんはやっと言葉を発した。
「私は、晴彦さんが大好き。死ぬまで一緒にいたい・・」
真知子さんは赤く腫らした眼差しで、私に言った。
「真知子さん、どうして仕事帰りにバスに乗らないの?」
私の問いに今度は黙ったままだった。多分、私を傷付けたくないのだろうと思った。私は、踏み込んだ言葉を発した。
「真知子さん、僕と結婚してくれる?」
やはり真知子さんは答えなかった。だが、私を見つめる瞳が、どうして私をそんなにいじめるのというふうに答えていた。
私は、また独り言のように話し出した。
「僕は、何度も誓ったんだ。真知子さんを一生守って生きて行くって。そして必ず幸せにして見せるって!真知子さんと僕はまだ大人の関係はないけれど、僕はとっくに決めていたんだ。真知子さんは世界で一番素晴らしい僕のお嫁さんだって。僕には真知子さんしかいない。真知子さんと結婚できないのなら、僕は生涯独りで生きる。真知子さん以外の女性なんて考えられない!」
真知子さんは、また私の胸に顔を埋め号泣した。それでも私は、私の心の奥底に仕舞い込んでいた熱情を止められなかった。
「僕の家は貧しいけれど、父も母も、僕と妹を精いっぱいの愛情で育ててくれた。お腹が空くことはあったけれど、寂しいとか、誰かが羨ましいなんて一度も思ったことなんてなかった。父と母が僕を産んでくれたんじゃなくて、僕が父と母の子どもに産まれるように神様に頼んだんだ。
真知子さん、僕のように、僕と真知子さんの子どもに産まれたがっている子がいるんだよ。僕はそう信じている。僕はその子を守ってあげたい。もし、僕と真知子さんが結婚しなければ、その子の小さな願いを夢を潰してしまうんだ!」
私は、何の根拠もない、だがいつも心に思っていたことを、真知子さんに叫ぶように話した。真知子さんは、私の胸の中で何度も頷いていた。真知子さんも私と同じなのだ。いつか私の顔中は涙と鼻水でくしゃくしゃになっていた。真知子さんは私の体にもたれていた体を起こし、香水の香りのするハンカチで私の顔を拭ってくれた。その顔は、やはり涙で溢れていたが、瞳はいつの間にか澄み切っていた。
「よく分かったわ。私たちの子どもに産まれたがっている可愛い子を裏切るなんてできないわ。私、頑張る!」
真知子さんが、何に対して頑張ろうとしているのかは不明だったが、私たちの心に綻びは微塵もなかった。真知子さんはいつもの笑顔を取り戻した。
「晴彦さん、今日はありがとう」
潮の香りのする風が二人の頬を撫でて行った。夕闇がせまり、灯台の白い明りが沖の船の姿を波の上に浮かび上がらせている。私と真知子さんは抱き合って口づけをした。信じ合えた喜びに、私は真知子さんの体を強く抱きしめた。いつの間にか西の空は茜色に染まっていた。 つづく