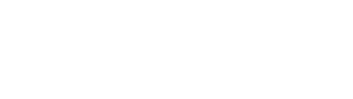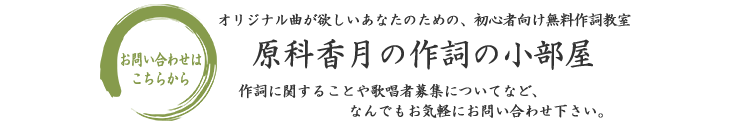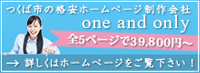創作の小部屋「函館物語」総集編
2022年06月07日
 創作の小部屋「函館物語」総集編
創作の小部屋「函館物語」総集編
「函館物語」が先月の5月2日に終了しましたので、総集編として纏めたいと思います。「函館物語」は1月22日が初めての投稿でした。それほど長くなるとは思わずに、指先の自由な動きに任せました。少なくとも10回位までには終えると考えていましたが、結局最終回は20回目となり、5月の月初めまで掛かってしまいました。大雑把な構想はありましたが、各章ともパソコンの前に座ってから思い付くままに書き進めました。ただ、脈絡と整合性はいつも気になっていました。
【第1章 故郷への回帰】
昨夏、古希を迎えた私は、一度も結婚したことがない。恋愛の経験がないわけではない。若い日、私はある人に夢中になった。彼女も私に好意を持ってくれ、将来を誓い合った。だが、結ばれなかった。彼女の名前は、坂本真知子と言った。
今、私は函館山の頂上にいる。彼女と一緒に登ったのが最後だから、実に半世紀近くの歳月が流れただろうか?私は、この思い出の地である函館に、東京のマンションを引き払い数日前に帰ってきたばかりだった。
函館に帰った私は早々に、昔の職場の友人の佐々木に、私の愛した彼女の近況が知りたくて電話を掛けた。友人は私からの電話に大喜びをした。しばらくは、昔話に花が咲いた。私も友人との会話は懐かしく、いくら時間があっても足りないと思えた。しかし、彼女が今どうしているか、それが早く知りたかった。
「聞いた話なので詳しいことは分からないが、彼女は一生を独身で通したようだ。60歳を少し過ぎた頃に乳がんを患い、かつての病院に入院していたが、暫くしてから亡くなったらしい」
友人は私と真知子さんのことは知らない。過ぎた昔話のように感情のない話し方だった。
話しの途中ではあったが、溢れ出る涙に、一言礼を言って私は急いで電話を切った。
彼女も、生涯を独身で通したのだ。あの時の二人の愛は確かなものだった。それ故に、結婚してもよいと思える異性には、私も彼女も生涯巡り合えなかったのだ。いや、比較などではない。どんな異性も、恋愛の対象とさえもなり得なかったのだ。
今見つめる函館山からの夜景は、眩し過ぎる光が函館駅を中心に輝いている。その美しさは、あの日とほとんど変わらない。その光が歪んだ。辺りには人影がなく、私は頬を伝う涙を拭おうとはせず、流れるままに任せた。友人から彼女の死を聞いたあの時から、私はなぜもっと早く帰らなかったのかと自責の念で一杯だった。
彼女との函館山での思い出が昨日のように私の脳裏に蘇る。
「真知子さん、本当にこの函館山からの夜景は素晴らしいですね。僕は、今日のこの美しさを生涯忘れないつもりです。今日は、付き合ってくれて本当にありがとう」
真知子さんは、キラキラした瞳をうつむき加減にして微笑んだ。
「私も、忘れないわ。私は、この夜景は幼い日から何度も見ているけれど、今夜の夜景が一番輝いて見える」
真知子さんは、私の目を真っ直ぐ見ながら言った。
いつの間にか、二人は手をつないでいた。私は、抱きしめたかったけれど、付き合い始めて日が浅く、まだ早いと自らを律した。真知子さんの手の指は、細くて白かった。
「真知子さん、あまり遅くなると、お家の人が心配するといけないから、そろそろ帰ろうか」
私は、本心ではなかったけれど、つい口に出した。真知子さんは、腕時計を見ながら言った。
「あら、こんな時間?じゃあ、次のロープウェイで降りましょうか」
ロープウェイの乗り口に差し掛かるまで、お互いに無口だった。近くには誰もいなかった。不思議なことに、彼女がいきなり私の胸に顔をうずめた。
「私、帰りたくない。このまま、ずっといたい」
彼女の唐突な態度に、私はたじろいだけれど、両手で彼女を抱きしめた。私も、ずっとこのままいたかった。それでも私は、冷静だった。今は、彼女の家族に嫌われるような、心配をかけるようなことは、極力避けるべきだと考えた。私と彼女の生きる世界が大きく違っていたからだった。
「真知子さん、今度の日曜日、もし用がなかったら、五稜郭を案内して貰えない?中学生の時に一度、友達と行ったことがあるけれど、ワイワイ騒ぎながらだったんで殆んど記憶にないんだ」
彼女は、私の胸から顔を上げた。
「大丈夫、10時ころ五稜郭タワーの前で待ってるわ」
真知子さんの顔は、周りのライトに照らされて、薄桃色に浮かび上がった。
その時の声は、今でも鮮明に覚えている。思い出は後からあとから、溢れる涙と共に浮かんでくる。彼女の甘い香りが鼻先に漂うような錯覚がし、言いようのない寂寥感に襲われた私はいつまでも泣き続けた。
確か「夜景の函館山」でのデートは、この時が3回目だった。初めてのデートは、「立待岬」だった。
私の名前は、高橋晴彦。生まれは、函館の西側に隣接する町で、現在は北斗市と呼ばれている。生家は海岸に近く、幼いころは夏になると真っ黒になりながら、岩陰の小魚を捕り、短い夏を楽しんだ。
父親は、家からそう遠くない小さな町工場にオートバイで通勤していた。母は近くの小さな漁港で、漁師が捕ってきた魚の選別や雑役などをしていた。決して裕福な家庭ではなかったが、父も母も私たち兄妹を、愛情たっぷりに育ててくれた。
真知子さんは、函館生まれで、大きな邸宅に住む資産家のお嬢さんだ。父親は、数十人の社員を持つ建築会社を経営していた。また函館商工会議所でも一目置かれる存在だった。当時は好景気で、益々会社は成長していたようだ。彼女は、一人っ子として両親の寵愛を受けて育った。
私と真知子さんは、同じ函館市内の病院で働いていたのだった。私は放射線技師で、彼女は薬剤師だった。
私は、放射線技師になる前は、東京の南に位置するある家具製造会社で働いていた。次回は、工場の作業員からなぜ放射線技師になったのか、そして真知子さんとの出会いまでを、記憶を手繰り寄せながら記してみたいと思う。
【第2章 放射線技師の誕生と真知子との出会い】
〖作業員から放射線技師へ〗
私は、昭和45年に函館のある道立高校を卒業すると、東京の都心からやや南に位置する、ある中堅の家具製造会社に就職した。その頃は高度経済成長期で、私たちは金の卵ともて囃された。私は、内地に憧れていた。一度、故郷から出てみたかった。若いうちに、日本の首都・東京での生活を経験してみたかった。
きっと私の人生に、何かを与えてくれるものと信じていた。ただ、いつかは故郷に帰るつもりでいた。私は長男なのだ。1年半が経過し、仕事にも、この都市の空気にもやっと慣れたと思われた頃、福島生まれの仕事仲間から、ある相談を持ち掛けられた。
「高橋、おまえ、この工場で一生を終えるつもりか?それが悪いという訳じゃないが、一度きりの人生だ。もう少し夢のある、もっと張り合いのある仕事をしてみないか?」
この友人の名前を伊藤智之と言った。この伊藤の話は、「診療放射線技師」になってみないかというのだった。資格を取ると、患者さんのレントゲン写真を撮ったり、その他にも病気の診断に必要ないろいろな放射線の検査をさせて貰えるという。待遇も、将来性も、工場で働くよりもずっと恵まれるという。
※診療放射線技師が現在正式名称ですがだが、ここでは、当時は「レントゲン技師」が一般的な呼称だったので今後は「レントゲン技師」とさせていただくことにする。
その資格を取るために、「レントゲン技師」の養成専門学校が夜間もあるという。働きながら2年の間勉強し、国家試験に見事合格すれば、間違いなく大きな病院でも採用されるという。私を誘ったのは、一人では心細かったのかも知れなかった。
だが私は、その伊藤の提案に喜んで乗った。直接人と接し、その人の役に立てるという仕事には生きがいがある。それに、故郷の親にも喜ばれるに違いない。幸い、寮からその専門学校までは電車で30分の距離であり、授業開始には充分間に合うという。
それから、専門学校の受験用の教科書を探し、二人で遠くの書店まで出かけたりした。やっと必要な本を数冊見つけることが出来た。節約の意味だけではないのだが、二人は同じ教科書を使い回した。寮のお互いの部屋を行ったり来たりしながら、結構遅い時間まで勉強に熱中した。しばらく勉強などしたことがないため、数学が特に難しく、一人では多分続かなかったと思う。お互いに励ましあい、教えあいながらの勉強は確かに効率が良かった。
翌年の早春、レントゲン技師の夜間専門学校の入学試験に二人とも合格することが出来た。合格と知った晩、嬉しくて二人でこっそり乾杯した。
工場の仕事と夜間学校の両立は、確かに辛かった。ただ授業を受けていれば良いというものではなかった。「レントゲン技師」の国家資格が取れなければ、せっかくの時間と授業料が無駄になる。眠い目を凝らしながら、必死に授業に食らい付いた。仲間には、既に総合病院に採用されており、職場にて午後3時頃までレントゲンの助手をし、それから通学して来るという恵まれた者もいた。そうした者は、殆んど近県からの通学者だったが。
工場の上司にも、二人のことは知られたが、特に注意を受けることもなかった。係長は授業に間に合うように、残業を極力減らしてくれたり、何かにつけ支援してくれた。とても有難かった。いつだったか、係長は二人を前にして話してくれたことがある。
「私は、大学を出て、図書館司書になりたかったが、家が貧しかったので諦めた。お前たちは立派だ。頑張れ!」
風邪をひいて私が寝込んだときは、伊藤はおかゆを作ってくれ、また授業内容を記したノートを見せてくれた。私もそのお返しをしながら頑張った。2年間の月日ははアッという間に流れ、二人は無事卒業し、併せて国家試験にも合格することが出来た。
伊藤は、東京のある有名な総合病院に就職したが、私は函館の総合病院に就職することになった。長男である私は、田舎の実家から通うつもりだった。他の仲間は、殆んど東京に残ったが、地方へと帰って行ったものも少なくない。誰彼ともなく、10年置きに同窓会をしようという話が持ち上がった。
不思議でならない、自分の意志というより、他人のたった一言が私の生きざまを変えた。私の人生を変えた。私の場合は、とても幸運だった。伊藤には、感謝しかない。生涯の友人となるだろう。
〖真知子との出会い〗
私は東京から帰り、北斗の実家から函館の総合病院に勤め始めた。病院には職員用の駐車場が用意されていたが、私は車を買う余裕はなく、バスを利用しての通勤となった。家から最寄りのバス停までは自転車で10分程だったが、雪が降る頃までには車が欲しいと思った。
勤務初日、私はレントゲン室の技師長に連れられ、院内各部署に挨拶に回った。病院の中がこんなに広いとは知らなかった。医局には、数人の医師がいたが、他の医師は既に病棟の患者さんの回診をしていると、頭頂部の薄くなった40代後半と思しき医師が話してくれた。それぞれの医師の机の上には、書類が乱雑に積み上げられており、患者から全幅の信頼を受ける医師の意外な一面に、私は驚いた。
薬局に行くと、一部の人は何やら準備をしているようだったけれど、他の二十人近い薬剤師たちは、立ちっぱなしで雑談を交わしていた。もう就業時間が過ぎているのにと、私が怪訝そうな面持ちでいると、女性の薬局長が話してくれた。
「まだ、外来が始まらないので、仕事が出来ないのですよ。診療が始まって、処方箋が回ってきてからが、私たちの真剣勝負になります。医療に携わる者は全て当然のことですが、万が一でも誤りは許されません。でも、人間ですからいくら注意していても、体調などで間違いを犯さないとは限りません。それなので、薬剤師同士が必ずダブルチェックをしています」
病院勤務初日の私でも理解できた。放射線技師長と薬局を出ようとした瞬間、走りながら部屋に入ろうとした若い女性と私は肩が当たった。無防備だった私は、一瞬よろめいた。
「ごめんない。遅刻してしまい、慌てて走ってしまいました。大丈夫ですか?」
私は大丈夫ですと言うと、放射線技師長の後を追った。ふと思った。今の女性は誰かに似ている。誰だったろうか?
そんな感傷に浸っている余裕はなかった。その後は検査室に向かった。室内には、女性だけかと思われたが、何人か男性の姿も見られた。
病棟に回ると、若い看護婦が二人ずつ組になり、何やら話し合っていた。その棟の婦長がやはり説明してくれた。話している看護婦が昨夜の夜勤者で、日勤の看護婦に患者さんの昨夜の様子を説明しているという。インターホンの音に、ある看護婦が慌てて走っていった。
一通り院内を回った後、技師長は私に今日の仕事の指示を出した。胸部レントゲンの撮影と、その仕事が切れた時間帯は暗室に入り、フィルムの現像をするようにとのことだった。撮影の方法は学校で何度も練習していたので特に問題はなかったが、この病院の暗室に入るのは初めてである。20代の若い技師に、私に要領を教えるようにと技師長は指示してくれた。若い技師は渡辺と言い、丁寧に教えてくれた。
混雑したときは冷や汗もかいたが、そんなこんなで、何とか長い一日が終わった。
「疲れたろう。今日は、もういいから家でゆっくり休んで、また明日元気に頑張ってくれよ。」
技師長は40代後半と思われた。赤ら顔の少し太った、人柄の良さそうな人物だった。
家路を急ごうとして、ハッと気付いた。明日は雨が降るようだと、誰かが言っていた。長靴がないと自転車では革靴が濡れてしまう。通り掛かりの人に教えて貰った商店街は少し遠かったが、周りを散策しながら歩いて行った。ある店に入ると、高齢の女性が愛想よく出迎えてくれ、私の足に合う長靴を探してくれた。傘も勧められたので一緒に購入した。
放射線技師としての初の勤務の日だ。もちろん疲れてはいたが、このまま真っすぐ家に帰るのは何か物足りないという風に、何故か急に気持ちが変わった。
放射線技師たちは背広、あるいはジャケットを着て通勤しているようだ。私も一着しかない背広を着て、今日は出勤した。それで気付いた。私にはネクタイが1本しかなかった。毎日同じネクタイという訳にはいかない。
同じ商店街を歩きながら、紺と黄色のストライブの手軽な値段のネクタイを購入した私は、やっとバス停に向かった。しばらく歩きバス停に着くと何人かが並んで待っていた。最後尾に並んだ私は、時計に目をやると既に6時を過ぎていた。随分歩いたなと感心してしまった。
前に並んだ女性の後から乗り込むと、既に空いている席は二つしかなく、その女性と隣り合わせに座ることになった。何気なく辺りを見渡した私は驚いた。隣の女性は、今朝、薬局の入り口で私と肩が当たった女性だった。
私は、これから生涯勤めるであろう職場の人なら、無視する訳にはいかないと思った。
「あのう、薬剤師の方ですよね。今朝は失礼しました。肩は大丈夫でしたか?」
女性は、「あっ」と小さく叫び、とたんに真っ赤な顔をした。
「放射線の技師の方ですね?今朝は、私が遅刻して、慌てて部屋に飛び込んでしまったものですから。申し訳ありませんでした」
彼女は、顔を私に向けたまま、頭を下げた。
私は、どうして遅刻したのか、その訳を聴こうとしたが止めた。そうだ、今朝、誰かに似ていると思ったが、やっと思い出した。中学生の時、同じクラスで学級委員をしていた中村和子だ。色白で、目の大きい、とても気立ての良い女性だった。私は、密かに憧れていた。だが、高校生になってからは会うことはなかった。
「あのう、今日、僕、初出勤で緊張していたものですから、本当は避けられたのに、僕の方こそすみませんでした」
私が早口で言うと、女性は下を向いて、首を振って笑った。正確には、これが真知子さんとの出会いの初めだった。
放射線技師長は、まだ勤務についたばかりの私を、暫くは就業時間内で帰してくれた。私は、意識的に以前訪れた商店街で時間をつぶし、6時15分頃にバス停に着くように調整した。そうすると2日に一度は、彼女と同じバスに乗ることが出来た。彼女は私と会っても、いやな顔は見せない。私は少し厚かましいかとも思ったが、いつも隣りの席に座った。空いていない時には、近くに立ったまま、特に意味のない天気のことなどを話しかけた。
まだ名前はお互いに知らない。薬局に挨拶に行った時の自己紹介の場には彼女はいなかった。私には名前を聞く度胸はなかった。
「よく会いますね。どこまで帰られるんですか?」
彼女は私の顔を見ながら言った。それだけ言うと、いつかのように顔を赤くして正面に向き直した。
「ぼ、僕、五稜郭から、バスを乗り換えて上磯のバス停で降り、そこから自転車で家まで帰ります。あの、僕は、高橋晴彦と言います。宜しくお願いします」
多分、私の顔も赤く染まったに違いない。真知子さんは少し可笑しそうに、白い歯を手で覆った。それから、少ししてから言った。
「私は、坂本真知子と言います」
こうして、私と真知子さんは、暫くの間、僅か10分にも満たないバスの中でのデートをした。いや、それは私の一方的な解釈で、彼女は同じ病院に勤務する、単なる職場仲間の一人にしか過ぎなかったのかも知れない。10分ばかりだったのは、彼女の家は二人で乗ったバス停の3つ先だったからだ。今日の私は心が高揚し、何故か幸せな気分で満たされた。
私は、一度行きたかった「立待岬」に真知子さんを誘ってみたいと思ったが、なかなか誘う勇気がなかった。
だが、私と真知子さんの二つの心は、少しずつではあるけれど、次第にその距離が近づきつつあるのを感じていた。
【第3章 「立待岬」へのデートの約束】
(上の画像は、立待岬に咲く禅庭花です)
函館の病院に就職し、ひと月が経った頃だったろうか?私は、やっと職場にも慣れつつあった。今は、まだ新米の私は、胸部や腹部などの一般撮影しか許されなかったけれど、暗室に送られてくるフィルムの中には、脳血管を映したものもあった。脳外科の医師が造影剤を使用して映したものだ。私は感動して、放射線の資格しかない自分にも、いつかこのような高度な仕事が出来たらと、密かに憧れた。
真知子さんとは、まだ帰宅の途中のバスの中で短いデートを楽しんでいる。それは私が勝手にそう思っているだけで、彼女の気持ちは分からない。でも、真知子さんは私に会うたびいつもニコニコしている。嫌われてはいないと思っている。
いつも感じていたことだけれど、確かに真知子さんとは帰宅のバスの中で会う。でも、それなら朝の出勤時に会っても良さそうなものだ。なぜ、夕方だけなのだろう?そんな疑問も暫くしてから知ることが出来た。後から、ついでの時に記そうと思う。
ある日から数日続いて、バス停に彼女の姿が見えなかったことがある。私は気付いた翌日から、バス停から少し離れた雑貨屋の近くで、いつもより早くから彼女の姿を待った。いつものバスをやり過ごし、いつの間にか最終便になっていたが、やはり会えなかった。
職場の昼休み時に、私は薬局の受付の前を何度も往復した。いつもなら、ガラス窓から奥を覗くと、彼女が見える筈だった。受付の事務の女性が訝しげに言った。
「どうされました?どなたかにご用ですか?」
私は、何でもありませんと返事をして、そさくさと退却した。職場に戻ると、休憩室の和室で将棋を指している者がいた。私は、傍に座って将棋盤の上をただ眺めていた。
真知子さんのことが気になり、仕事中も上の空だった。私を指導してくれた伊藤さんが、どうかしたのかと心配そうに聞いたが「すみません、大丈夫です」と小さな声で答えた。
それから4~5日が過ぎようとしていた水曜日の帰りのバス停で、私は今日も逢えないと、諦めかけて下を向いて立っていた。突然、後ろから声が響いた。
「しばらくです。高橋さん!」
彼女の元気な声に、ただ私は驚いた。急に安心した私は、ふいに涙ぐんでしまった。
真知子さんは、何かを感じたのか、私に真っすぐ視線を向けて言った。
「あのう、私がここ1週間お休みをしていて、高橋さんが、もしかして心配してくれているかと考えていたのですが・・・・」
私は、涙の訳を繕うふりをして言った。
「花粉症が、まだ治りきらなくて・・・。」
ポケットからハンカチを出して、目頭を拭いながら続けて言った。
「この1週間、どうしたんですか?病院にもいなかったじゃないですか?」
真知子は、悟った。この青年が私をどれほど心配していたのかを。私が元気だと知って、うれし涙を流したこの青年に、真知子は言い知れぬ親しみを覚えた。
「あのう、私がお休みしたのは、インフルエンザに掛かってしまったからです。母と二人で、連休を利用して京都に二泊の旅行に行ったのですが、京都の二日目に高熱を出してしまったのです。全国に流行り始めているのは知っていましたが、マスクをして嵐山など人の集中しないところだけにし、余り人ごみに出かけなければ大丈夫だろうと父も言ってくれ、それに、もう予約もキャンセルできなかったもので・・・。
もしかしたら、私が勤務中に感染していたのかもしれないと思い、とても不安になりました。病院の薬局長に電話をしましたら、幸い感染者はいないと聞き、本当に安心しました」
やっと理解することが出来た。京都でA型インフルエンザに感染し、熱が高かったので向こうの医療機関に入院し、親子共々完治したのでやっと帰ってこられたという訳だった。
医療に携わる者が、旅行に行った先でインフルエンザに感染し、1週間も仕事を休んだことは褒められることではないと、真知子さんは薬局長からきつく叱られたらしい。だが「今日から、またしっかり頑張って借りを返してちょうだい」と、話の最後は肩を軽く叩かれたという。
私は、真知子さん親子に落ち度があったのかは判断できなかったけれど、こうしてまた元気な姿を見られることが、ただただ嬉しかった。
ある日、バス停に私の方が早く着いた日の会話である。
「あ~今日は、私の方が遅かった~。残念!だって、もう5時近くになってから急にミーテングになってしまって。高齢の患者さんが、お薬の飲み方の件で問い合わせをしたら、電話対応をした薬剤師の言葉遣いが上から目線だって、酷く怒って事務長に電話してきたらしいの。それで、患者さんだけでなく、職員同士であっても、言葉遣いには充分気を付けるようにって、薬局長から全員に注意されたの」
確かに目の前の業務が滞るほど忙しいときに、同じことを何度も繰り返す高齢者も中にはいる。それで気をもむことがあるのも事実だ。人に優しく接することは、時間がある時なら簡単だけれど、心に余裕がないときは難しい。
急に、真知子さんは、表情を明るく変えて言った。
「私、いつも家の中にばかりいるものだから、母に言われたの。いい若い者が、休みの日に家の中にいて本ばかり読んでいるなんて、もっと青春を謳歌しなさい。もう少し、外の空気を吸って来なさいって」
そう言い終わると、真知子さんは少し頬を膨らませた。
「何も、母が言うことじゃないわよね。私だって、たまには旅行や、ハイキングにも行ってみたいのに。でも、旅行は、この間の件があるから自粛しないとダメかもね」
真知子さんは、決して私を誘っている訳ではなさそうだった。彼女は、本来、それ程活動的ではなく、どっちかというと時間があれば本を読んでいたいというタイプなのだと思った。
私は、あのインフルエンザの一件以来、真知子さんの私への話し方は、他人行儀ではなくなった気がする。敬語を使うことが少なくなった。私も、同じように変わったらしい。
「真知子さん、僕も東京でレントゲンの夜間学校に行っている頃、寮母さんに言われたことがあるよ。休みの日は、いつも国家試験の勉強ばかりしていたものだから」
「何て言われたの?」
真知子さんは、私の顔を覗き込むようにして聞いた。
「それはね。若い時って、年齢を重ねてからしか分からないようだけれど、あの頃に戻りたいって誰も思うらしいよ。高齢になってから後悔するみたいなんだ。だから、悔いを残さないよう、大いに若い日を楽しんで生きなさいって。でも、僕には、どういうことか分かんなかったよ。いつもいつも職場と、放射線の学校を行き来しているだけ。楽しいことなんか、何もなかったし」
真知子さんは、感心したように笑顔で言った。
「でも、本当に晴彦さんは偉いわ。昼間仕事して、夜学に通うなんて。私は、家から十分な小遣いを貰って、楽しい学生生活を送ったわ。でも晴彦さん、今からでも遅くないわ。まだまだ若いんだし。もし良かったら、その青春の謳歌とやらを、私も一緒にさせて貰えないかしら?」
そう言ってから、真知子さんはいつものように顔を赤らめた。つい、心の内を暴露してしまったというように、恥ずかしさに耐えているかのようだった。だが、私の有頂天になった表情が、余りに嬉しそうだったみたいで、真知子さんは安心したようだった。
私は、前から言い出せずにいた「立待岬」に行ってみないかと誘おうとした瞬間、バスが停まった。彼女が降りるバス停に着いたのだった。
「残念!続きはこの次にしましょうね!さようなら」
真知子さんは、白い歯を今日は隠さず、嬉しそうに言った。
そのあくる日、バスの中で、思い切って言った「立待岬」に行かないかとの私の誘いを、彼女は即オーケーしてくれた。
彼女とは、函館市電の「函館駅前」駅に10時ということで約束した。
【第4章 立待岬でのデート】
私は、昨夜は熟睡できなかった。真知子さんと二人だけの時間を過ごせるということが、まるで世界には私と真知子さんだけが存在しているかのような気持ちだった。少しまどろんだかと思うと、また目が覚めた。明日、寝不足の顔を見られてしまうと思ったら、よけい眠れなくなった。
函館駅前から、3分くらい歩くと市電の「函館駅前」駅に着いた。約束の時間は、10時だったが30分も前に着いた。今日は、薄緑色のポロシャツの上に、少し厚めの白いセーターを着込み、スラックス姿にした。昨日帰りにバスで真知子さんと別れてから、五稜郭の商店街の洋品店で、中年の店員に相談して勧められたものだ。私には、服を選ぶセンスは全くない。
真知子さんは、時間通りにやってきた。昔、東京で働いていた頃、デートでは10分遅れて来るのが女性のマナーだと聞いたことがある。私は、田舎者だ。マナーなんかより、憧れの人に早く逢いたい。時間通りに来た真知子さんの方が、人間として優れていると思った。
もう今日は、5月の半ばだ。天気予報によると18℃を超える陽気のようだ。真知子さんは、刺しゅうを施した茶系のワンピースに、それよりも濃い色のカーデガンを羽織っている。右腕には、やはり薄い茶系のバックを下げている。ネックレスもしないし、ピアスもしていない。だが、良家のお嬢さんだと私にも分かる雰囲気を醸し出している。それから、ハンドバックよりも少し大きめな竹の籠も持っていた。
「今日、お天気に恵まれたのは、晴彦さんの普段の行いが良いせいね!」
真知子さんは、私が緊張しているのに、天真爛漫だった。暫くぶりの外出に心が躍っているようだ。市電は時間通りにやって来た。先に乗った真知子さんは、二人が座れる席を用意してくれた。私は真知子さんの左側に座り、竹の籠を預かった。
何分かすると「青柳町」という駅に着いた。ここが、石川啄木の詠った青柳町だと思うと、高校の通学時に鞄から出して読んだ昔を思い出した。
函館の青柳町こそ悲しけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花
当時、日日新聞の遊軍記者であった啄木は、函館大火に遭い、職も失った。その頃に詠んだものなのかも知れないと、私は根拠のない推測をした。真知子さんが隣にいるのに、不謹慎にも啄木への追憶に浸っていた。青柳町は、函館山の山裾にあるためかなだらかな坂道が多かった。
私は右手の竹の籠を持ち替えて、青柳町を過ぎた頃、真知子さんの左手をそっと握った。真知子さんは、気付かないのか、海の方に目をやっていた。そろそろ谷地頭かと思うころ、真知子さんが言った。
「私、今日、お弁当を作ってきたのよ。偉いでしょう?晴彦さんが持っているのが、そのお弁当よ。良い匂いがしない?」
そう言いながら、私と繋いだ左手に少し力を入れた。
「早く起きて作ったんでしょう?僕も食べていいの?」
私が言うと、真知子さんは少し頬を膨らませて言った。
「さっき、何か考え事をしていたでしょう?私には、晴彦さんの考えていることが分かるのよ。多分、あなたが大好きな石川啄木のことでしょう?」
私は少し困ってしまって、素直に「ゴメン」と謝った。以前バスの中で「函館というと、石川啄木が浮かぶ」と言ったことがある。啄木の滞在した北海道の街をいつか訪れたいと思っている、とも確かに話したことがある。
「私、啄木に嫉妬しちゃう。お弁当、上げるのよそうかな~」
私は驚いた。真知子さんにもこんなお茶目なところがあったのだ。真知子さんは、ニコニコしながら私に向かい、また頬を膨らませた。その仕草が可愛かった。
間もなくして、谷地頭の駅に着いた。
私と真知子さんは、手を繋いで歩いた。途中、立派な家の庭などを見ながら、二人で楽しく歩いた。約1キロも歩いただろうか?坂道を登っていくと、両側にお墓が並んでいた。その中に「石川啄木一族の墓」と書かれた柱が立っていた。
啄木は、函館で亡くなったのではない。啄木の終焉の地は、現在の東京都文京区小石川だ。啄木は、物心両面で支えてくれた函館の歌人・宮崎郁雨に宛てた手紙の中で「おれは死ぬときは函館に行って死ぬ」と書いたという。故人の遺志を尊重し、宮崎郁雨が中心となって、この地に墓を建立した。何かでそう読んだ記憶がある。
私と真知子さんは、立待岬に急いだ。今日は、真知子さんと二人だけの世界だ。それ以外は、今日はもう考えないことにした。
坂道を登りきった先には、海に突き出る形で海抜約30mの断崖がそそり立っていた。立待岬に着いたのだった。目の前には、津軽海峡が広がっていて、遠くに陸地が見えた。海面からの距離のせいか、不思議に波の音は聞こえなかった。
「晴彦さん、今日は天気が良いから、下北半島があんなに近くに見えるわ。本当に、晴彦さんは幸運だわ。こんなに美しい津軽海峡は、めったに見られないもの」
真知子さんが、下北半島を指さしながら言った。決して冷たいという程のことはないが、真知子さんの後れ毛が風になびいていた。私は、この岬の美しい風景を、真知子さんと一緒に見られる喜びに震えた。
「少し先にベンチがあるの。そこでお弁当を食べましょう」
真知子さんはそういうと、私の手を引くように岬の端に歩きだした。何度か家族で来たことがあるという真知子さんは、何でも知っていた。
静寂ではあるけれど、まるでウィーン国立歌劇場におけるクラシック演奏会の主賓席にでも座っているかのようだった。目の前に広がる津軽海峡、沖には海峡を行き来する船舶。これが青春を謳歌するということなのか?東京で働いていたとき寮母さんが言った、また真知子さんの母親が言った「青春を謳歌する」とは、こういうことなのか?
この日は多くの会話をし、とても幸せな時間に私は酔っていた。腕時計を見た。とても時間の流れるのが早い。このまま、時よ止まってくれ!私は心の中で叫んだ。
真知子さんとの二人だけの幸せが永遠に続くものと、私はそのとき信じていた。
【第5章 未来への一抹の不安】
まだ、昼までは少し早かったけれど、私は真知子さんの作ってくれたお弁当をご馳走になった。ありふれた言い方しかできないけれど、とても美味しかった。ゴマをまぶしたおにぎり・鳥のから揚げ・卵焼き・ウィンナーソーセージ・それからトマトとキューリの生野菜。見た目もすごくきれいだった。真知子さんは、使い捨ての紙容器にそれらを載せて、私に「どうぞ」と言って渡してくれた。野菜には和風のドレッシングをかけてくれた。
今でこそ、お弁当の定番かも知れないが、当時はとても珍しかった。
「このお弁当は、私が小学生の頃、家族で五稜郭公園や函館公園とかにお花見に行くとき、いつも母が作ってくれたお弁当なの。だから、私はこのお弁当が今でも大好きなの」
私は幼いころから、決して贅沢な食事はしたことがなかった。母は漁師から、小さすぎて売れない小魚などをいつも貰ってきては、煮たり焼いたりしておかずにしてくれた。真知子さんのお母さんのような洒落たお弁当を食べたことはなかった。
「真知子さん、とても美味しいよ」
私は、おにぎりを頬張りながら言った。真知子さんは、とても嬉しそうだった。
「今度は、おにぎりじゃなく、サンドウィッチにしょうかな?晴彦さんは、どっちがいい?」
「僕は、真知子さんが作ってくれるなら、何でも嬉しいよ」
二人にとって至福の時間が流れた。津軽海峡の沖は、太陽の光を浴びて銀色に輝いている。タンカーらしき船が、水平線の眩しさの中を航行していた。
「真知子さん、お弁当を食べ終え少し休んでから、大森浜に一緒に行かない?」
私が遠慮がちに言うと、真知子さんは笑って言った。
「大森浜に?アッ、分かった。東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる。 ねえ、そうでしょ?」
この啄木の歌は、大森浜で詠んだものと言われているが、一説によると当時は大森浜には蟹はいなかったらしい。それでも私は勝手に、大森浜で啄木は涙を流したと解釈している。生活苦のためか、世に認められぬ自分が惨めだったのか?
暫くして私と真知子さんは、お弁当を食べた後片付けをし大森浜に向かった。来るときに見た啄木一族のお墓を通り、途中から住吉漁港に向かって右折した。後は大森浜まで一直線だ。ここからは、多分10分も歩けば着くはずだ。
「真知子さん、僕が我がままを言い出したものだから、随分と歩かせちゃってゴメンね」
「私は、運動は得意じゃないけど、歩くのは大好きよ。晴彦さんと一緒ならよけいにね!」
真知子さんはそう言うと、私の手を引っ張り、先を歩き始めた。男の私が、女性に手を引かれて歩く姿は自慢にならないけど、真知子さんなら大歓迎だ。私は、前から聞こうとして言い出せないことがあった。今なら、平気かなと思った。
「真知子さん、今更聞きづらいんだけど、僕が今の病院に就職した時には、既に真知子さんは働いていたよね。僕よりお姉さんになるのかな?別に、たいしたことじゃないんで、聞かなかったんだけど」
真知子さんは、一瞬戸惑った表情を浮かべたが、すぐ笑顔になって言った。
「多分、生まれた年は同じで、私が早生まれ。だから、学年は私の方が一つ上になるかも」
真知子さんは、それがどうしたのという風に、私を見つめて言った。
「いや、別にどうでも良いことなんだけど。一応、知っておきたいと思っただけ」
そう答えた後、僕は愚かにも、まだ話題にもすべきでないことを口走ってしまった。
「そういえば、真知子さん、一人っ子だったよね。両親から、何か言われているの?」
真知子さんが気分を害するかも知れないことを、少しのためらいはあったけれど、無遠慮にも聞いてしまったのだ。
いつもニコニコ笑顔の絶えない真知子さんだったけれど、この時ばかりは一瞬顔を曇らせた。
「私の父は、建設会社を経営しているの。私は薬剤師だから、家業は継げないし。父は、いろいろ考えているみたい。いずれお婿さんを貰って、お婿さんに会社を任せたいようなことを、私が中学生の頃言ったことがあるわ。でも、今の私は、そんなことは考えられないわ。私は、好きな人と一緒になりたい」
私は、真知子さんといるときは、心から幸福感で一杯になる。このまま二人で一生を過ごせたら、私の人生はどれだけ輝けるものになるだろう。だが、この時の私は、果たして二人に明るい未来が待っているのだろうかと、少し不安になった。よそう、そのことを今考えるのはよそう!まだ、ずっと未来の話だ。もし、そういうことで悩む日が訪れても、乗り越える方法はきっとある。二人で考えれば、最良の道が必ずある。そう信じることにした。
また、仲良く手を繋ぎながら、あまり意味のないことを話し合いながら歩いていくと、いつの間にか大森浜に着いた。ここには、啄木小公園がある。地元の人が何人か歩いていたが、公園の啄木像には目もくれず真っすぐ海岸に歩いて行った。余り関心がないのかと思った。
啄木の坐位の銅像をみた。本で見るいつもの写真の顔と少し違ったように感じた。啄木が過ごした明治40年頃とは、どういう時代だったのか?また、啄木への感慨に浸り、真知子さんをほんの一瞬だけ忘れた。
二人で啄木小公園から砂浜に降りる途中で、真知子さんは私の顔を覗き込むようにして言った。
「晴彦さんは、本当に石川啄木が好きなのね。でも、今度は、私が行きたいところでもいいでしょう?見晴公園は、秋の紅葉の時期に何度か行ったことがあるけど、人が多すぎて疲れちゃうの。今の季節なら、新録がきれいで、人も多くなく、静かでゆっくりできると思うの。どう、晴彦さん?」
私にはもちろん異存がある筈はない。しつこいかも知れないけど、私は真知子さんと一緒ならどこでも楽しいのである。見晴公園、とても良い名前の公園だ。私は、一刻も早く真知子さんと訪れたくなった。
「了解しました。喜んで、お供させていただきます。嬉しいな、いつにする?」
もう私は、すっかりその気になっている。真知子さんは、目を丸くして言った。
「随分、気が早いのね。私も、母と買い物や、これでも何かと忙しいのよ。でも、晴彦さんを先ず第一に優先するわ」
大森浜の沖を見つめながら話していると、いつの間にか、周りには人の気配がなくなり、二人だけの世界になった。啄木の像の後ろには、さっきまでいた立待岬が見える。
「今日は、疲れたでしょう?僕のせいで、大分歩いたし。そろそろ帰ろうか?」
そう言うと、真知子さんは少し寂しそうに言った。
「まだ日暮れまでには時間があるし、もう少し、晴彦さんとこうして一緒にいたいわ」
真知子さんとは手を繋いでいるので、手繰り寄せれば、彼女は私の腕の中だ。大好きな真知子さんを抱きしめて、口づけをしたいという欲求が血潮となり、私の全身を駆け巡った。だが、私は意気地のない男だ。もし、嫌われたらと思うと、行動に移せない。彼女は私にとって初めての女性だ。私には、女性の気持ちが分からない。迂闊には動けなかった。
それから、二人は帰宅の途に就いた。朝、待ち合わせた函館駅前で別れた。次回のデートの日は決めてなかったが、私は毎日でも二人だけで逢いたかった。
函館駅からの帰りのバスの中で、どうしても気になることがあった。私が長男で彼女が一人っ子のことだ。何とかなる!そう信じようとしたが、一抹の不安を拭い切れなかった。
【第6章 私の職場内での配置転換】
4月に入職し、まだ半年も経たない9月から、レントゲン技師長は、私を「消化管造影検査室」への勤務を命じた。予約がだいぶ先まで埋まっている「消化管造影検査室」を充実させたいと、技師長は私に言った。院内でも問題となっているらしい。
当時の私の病院でのレントゲン技師が携わる業務は、主に以下のようであった。
〇一般Ⅹ線撮影 〇消化管造影検査 〇 血管造影検査 〇超音波検査 〇 シンチグラフィ
私が入ったばかりの時は、CTスキャンの機械はまだ導入されていなかった。高額でもあり、まだ設置されている病院は少なかった。だが2年後には当院にも設置された。
私の勤務している病院の患者数が、外来及び入院患者ともに、ここ数年大きく増加しているらしい。近い将来増築の計画もあるそうだ。確かに、1階の正面受付は人混みで溢れ返っている。
私の命じられた「消化管造営検査室」は、バリウムを使っての胃や腸の画像を撮影するのが主な仕事だ。簡単に言うと、バリウムを患者さんの体内に入れて、色々な角度からの胃や腸の写真を撮る仕事だ。どの検査もそうだろうが、特にこの検査は技師の力量が問われる。医師の確定診断をも左右するからだ。一朝一夕に、医師の求める質の高い画像を撮るのはとても困難だ。
放射線の学校で、「胃や腸のバリウム検査を受けた人の声」というテーマの授業を受けたことがある。バリウムの検査を受けた患者は、主に以下のような思いをしているようだ。
◎患者にとり、胃や腸のバリウムでの検査を受けるのはとてもストレスになる。とても辛いからだ。ゲップをするなと言われても高齢者は我慢できない。
◎胃も腸もどちらの検査の場合も、ガラス窓の向こうから、右に回ってとか左に回ってとか、体の向きを技師に指示される。しかし、それでなくても緊張している状態だというのに、どっちが右か左か分からない。焦らせないで欲しい。
◎胃の検査の場合、逆さのような状態での撮影は、台の上から落ちないかと恐怖で一杯になる。血圧の上昇も気になる。
◎腸の検査おいては、バリウムと空気をおしりから入れられ、お腹が張ってとても苦しい。その上、体の向きを変えるのは本当に辛い。
◎胃も腸も検査が無事済んでも、その後はトイレでのバリウムとの戦いになる。胃や腸の中で、バリウムが固まってしまわないかと不安になる。
◎レントゲン技師は患者の気持ちを考えて、もっと優しく丁寧に接してほしい。
これらの意見はどれ一つとっても間違いではない。だが、技師にも都合があるのも分かって欲しい。時には、多くの患者が後につかえている。悠長に優しくなどとは言っていられない場合もある。もちろん患者が主役であることは承知している。
この難しい造影検査の業務を任された私は、少しでも患者さんの辛さを軽減できるような技師になりたいと思った。だが、突然今日から一人前になれる訳ではない。暫くは熟練の先輩の指導を受けながらマスターすることになる。早く消化器の医師に認められるようになりたい。そして、患者さんに安心して検査を受けて貰える技師になりたい。そう思った。
世の中、日進月歩である。もちろん医学の世界も同じである。だがその進歩は、決してスポットライトを当てられながらのものではない。痺れるような涙ぐましい先駆者の苦労があってこそだ。それは、今度私が担当となる、消化管造影検査もまた同じだ。
〖ある医師の命の信念〗
私は、放射線の学校で「二重造影法」という撮影法を学んだ。それは、それ以前の撮影方法よりも、胃や腸の内壁をより精密に撮影できる方法だ。この撮影法が、日本における胃がんの早期発見を飛躍的に向上させる原動力となったという。その撮影法を研究・確立させた医師については、以下に記す。
その医師は、昭和20年代後半から30年代にかけて、まさに命をかけた凄まじい研究の末「二重造影法」という撮影方法を確立させたのである。その医師の名は、後に順天堂大学教授となった白壁彦夫という。研究当時の、千葉大での凄まじい努力、また功績については「ガン回廊の朝」(柳田邦男著)という本に詳しく記してある。
その「ガン回廊の朝」から、白壁医師の涙ぐましいその姿を覗かせて頂く。
当時、昭和20年代後半から30年代にかけての話しである。白壁医師は、千葉大学の第一内科レントゲン室に所属していた。彼は、夜は毎晩1時ごろまで研究室にこもり、下宿に帰ってからは、持ち帰った医学の文献を読むという生活を日常的にしていた。
外科から切除標本を借り、片っ端からバリウムを詰め、術後のⅩ線検査をした。バリウムの量・空気量・圧迫の有無など考えつく限りを尽くし写真を撮った。即ち正確な診断のための撮影技法の研究に明け暮れたのである。その研鑽が功を奏して、二重造影法という撮影技術を編み出したのである。当時は、まだレントゲン写真から早期の胃ガンを見つけることなど困難な時代であった。
ある日、白壁医師は、胃の不調でやって来た患者に小さなガンを見つけた。二重造影法で初めて見つけた初期のガンである。白壁医師は、自分を評価してくれていた外科教授に報告すると、教授が執刀してくれることになった。だが、いざ教授が開腹したが、ガンは見つからず、教授は手術を諦めた。閉腹と告げた。
しかし、白壁医師は、「いえ、でもお願いします」と青い顔をして懇願した。教授の意見に反論することなどあり得なかった時代である。もし、病巣がなく開腹したとなると、外科の責任、即ち外科の教授の大変な落ち度ということになる。白壁医師は内科である。
教授は、病巣がある筈の部位を何度も触診したうえで、白壁医師に更に繰り返し聞いた。
「なあ、もういいだろう?」
閉腹してもいいだろうという意味である。白壁医師は、緊張して小刻みに震えながら、その場にいた医師たちも信じられないような言葉を口にした。
「でも・・・お願いします」
手術は時間との闘いである。教授が、閉腹と宣言してから5分の時が過ぎている。手術室は息が詰まるような緊張感で包まれた。
「ないよ、君、困ったよ!なあ、いいだろ!」
教授は苛立ちながら言った。それでも、白壁医師は態度を変えなかった。それどころか、驚くような言葉を口にした。
「いえ、先生、切ってください!」
白壁医師の鬼気迫る姿に、教授は覚悟を決めた。手術を再開したのである。
その結果、剔出(てきしゅつ)された胃の臓器には、触診では判らない程の小さなガンがあったのだ。千葉大医学部では、これ程小さなガンの手術は初めてのことだった。本来は外科の貴重な標本となる筈だったが、教授は白壁医師に臓器を差し出した。教授もまた真の医療人であった。
私は、この「ガン回廊の朝」を何度も読んだ。この場面では涙が止まらなくなる。私は医師ではなく、放射線技師である。だが、後世に名を残すような人生でなくとも、医師に頼られる、そして出来る限り患者に寄り添うことのできる技師になろうと誓った。
約1ヶ月が経った頃、レントゲン室に患者のレントゲン写真を取りに来たある外科の医師が言った。
「高橋君、最近の写真は良くなったね。土井君に近づいたよ」
私には到底信じられる訳はなかった。この仕事は奥が深い。1ヶ月程度の経験で一人前になれるなら誰も苦労はしない。この外科医は、私が土井先輩から勤務時間の後も遅くまで指導を受けているのを知っている。また、図書室から土井先輩の推薦の「消化管造影検査」の類の多くの書物を休日に学んでいることも知っている。
私を励まそうとのリップサービスだ。だが、この医師には悪意はない。大分先まで埋められた予約表の緩和のためには、熟練した技師の誕生が一日も早く望まれている。私も少しでも早く期待に応えたいと考えていた。
傍にいた土井先輩は、ニコニコしている。人間としての器も大きい、この先輩の力なくして私の成長はない。
レントゲン技師と消化器外科医との、合同での胃部レントゲンフィルムの読影会がある。その時でも、土井先輩は医師と同等に渡り合う。ある時などは、医師が気付けなかったスキルス性の陰影を指摘し驚かれたこともあった。早く土井先輩の力量に追い付きたい・・私はそう強く願った。私の土井先輩への畏敬の念は更に深まった。
ここしばらく、慣れない仕事での疲れと休日の勉強で、真知子さんとのデートの頻度も少し減った。そういえば、真知子さんと行った2回目のデートの「見晴公園」の話しはまだ書いてなかった。遅くなってしまったけれど、次回報告させて頂くことにしたい。
※二重撮影法とは、陽性造影剤と陰性造影剤の併用による二重のコントラストを利用するⅩ線検査法である。端折って言えば、検査部位においてバリウムと空気を混じり合わせるよう何回も体位交換を行い、検査部位の粘膜にコントラストをつくる撮影法である。このことにより粘膜の細かい異常も発見しやすくなる。
【第7章 見晴公園(香雪園)でのデート】
初めて真知子さんと出会ってから、3ヶ月を迎えようとしていた。今日は真知子さんとの2回目のデートの日である。行く先は、真知子さんの希望で見晴公園となった。函館駅からバスで行くことになっている。待ち合わせは10時である。私は真知子さんと会えると思うと、どうしても早く目が覚めてしまう。新聞を読んで時間を潰そうとしても、集中できない。それで、つい早く来てしまう。私は嬉しくて、多分締まりのない顔をしている。真知子さんには、どう映るのかが心配だ。
約束の10分前に真知子さんはやって来た。
「真知子さん、おはよう。今日は、少し早いじゃないの」
私がそう言うと、少し意地悪そうな顔をして言った。
「おはよう。いつも私より早いのね。今日はね。お昼のお弁当を、一人分しか作らなかったからね、早く来られたの」
真知子さんは私を困らせる。だが、すぐ笑顔にもどる。その時の真知子さんの表情が私には愛しい。定時にバスはやって来た。バスの乗客はまばらだった。前の座席に二人並んで座った。少しすると真知子さんは、さっそく昨日の昼の話をしてきた。
「晴彦さんは病院の廊下ですれ違う時、知らない振りをするけど、私と病院の中で会うのが嫌なの?」
職場の皆は交代で、昼食を職員食堂で取る。何人かの同僚と食堂へ向かう時、廊下で真知子さんにすれ違うことがある。そんな時、真知子さんは小さく咳払いをする。私は知らない振りをして、通り過ぎる。
「真知子さん、誰もいないなら別だけど、他の人も一緒だから、恥ずかしいよ」
「じゃあ、何、私とは病院の中では会いたくないというの?」
最近の真知子さんは、私を困らせるようなことをわざという。私は返事に困って、急いで話題を変えようとした。今日の真知子さんは、ベージュのスラックス姿に白い靴。とてもよく似合う。
「真知子さんは、いつもセンスが良いね。僕は田舎者だから、妹に野暮ったいって言われてるよ」
すぐ仲直りをする。そして特に意味のない話しで盛り上がる。真知子さんは、今日も明るい。真知子さんの横顔を見つめながら、私は今日も幸せ感で一杯だ。
二人で手をつないで入った見晴公園は、新緑一色で覆われていた。吸う空気までもが、美味しく感じる。深呼吸をすると、新鮮な血液が体の隅々までも流れるような気がした。
園内には家族連れや年配のご夫婦が目立った。なかには、私たちのようなカップルも何組かおり、それぞれ自分達だけの世界を闊歩している。
函館というと五稜郭公園が有名だけど、この見晴公園はその五稜郭公園の倍の敷地があるそうだ。そもそもこの公園は、明治時代の豪商岩船家が別荘として造られたものだという。それを岩船家がトイレなどを整備し、一般に開放したものらしい。岩船家は親子三代に渡り私財を投げ打って、この見晴公園を造ったのだそうだ。
別名、香雪園という。大正期に来函した京都の浄土宗知恩院の貫主に「雪の中に梅香る園」という意味で名付けられたとのことだ。
いわれの碑の前では、真知子さんは立ち止まった。
「この公園は、岩船家から呼ばれた、京都の庭師・辻地月が、内地からヒノキとかヒバとか150種くらいを取り寄せたらしいの。数にしたら6000本から7000本くらいらしい。桜の木も200本くらいあるから、少し前に来ればすごい眺めだったと思うわ。もちろん紅葉の季節は、それはとても奇麗なのよ」
さらに真知子さんは続けた。
「その庭師の辻地月という人は、庭師の他にもお茶やお花の師匠でもあったので、公園内の枯山水や園庭には特に力を入れたということみたい。ごめんなさいね。こんな話あまり面白くないでしょ?実は、昨日の晩、百科事典で調べたの」
真知子さんは、少しも悪びれずに、笑いながら言った。
「このカエデ並木を行った先に、芝生公園があるから、そこでお弁当を食べましょう。しばらくゆっくりして、それから園停を見に行きましょう?」
今日の真知子さんはいつもより饒舌だ。女の人は無口の方が良いという人もいるが、その時による。この美しい新緑の中では、無口でいることの方が難しい。真知子さんは、紅葉の季節には何度か来たことがあるが、新緑の季節は初めてだと前に言っていた。今日の私は、真知子さんの言うがままに、素直に付いていくことにした。
ふいに立ち止まって、真知子さんが言った。
「昨日ね、母から明日買い物に行かないかと誘われたの。でも、明日は出かける用事があるから、また今度にしてって言ったの。そしたらね、最近付き合っている人がいるのかって急に聞いたの。何か最近、私が今までと違う雰囲気がするんだって!」
そこまで話すと晴彦の顔を見つめてまた言葉を続けた。幾分、顔が少し上気しているかのようだった。
「私、一度だけど立待岬に行った職場の男性がいると、正直に話したの。そしたら、お前が好意を持っている人なら、そのうち一度お家に呼んだらって言うのよ。どう思う、晴彦さん」
私は返事に困ってしまった。もちろん真知子さんが大好きだ。ずっと一緒にいたい。それが結婚というものなのかも知れない。だが、真知子さんと知り合って、まだ2ヶ月になったばかりだ。それに私はまだ22才。就職したばかりで、仕事もまだ半人前だ。もう少し自分自身に自信が持てるようになってから、真知子さんの両親には会いたいと思った。
真知子さんの母は心配なのだろう。苦労をさせずに育ててきた娘だ。その娘が、一体どんな男と付き合おうとしているのか、一度顔を見たいと考えたのだろう。
「真知子さん、まだ僕は22歳だ。だからどうということはないけど、まだ社会人として若すぎると思っている。まだ、真知子さんのお母さんに会うのは早すぎないか心配だ。あと、2年くらい後なら、自信をもって会えるような気がする。だから、もう少し待ってくれるように、お母さんに話して欲しいんだけど。もちろん、真知子さんのお母さんにぜひ会いたいとは思うけど」
私は大好きな真知子さんとずっと一緒にいたい。本当は、年齢なんかに関係なく、出来ることなら明日にでも結婚したい。真知子さんのお母さんが会いたがっているということは、二人の将来を見据えているということかと思い私は嬉しくなった。
真知子さんは、また私を困らせることを言った。
「やっぱり男の人と女の人は考え方が違うのね」
私には、この意味が分からない。だが、私たちも真知子さんのお母さんも、二人の結婚ということを意識している。友人たちの話では、女性にプロポーズするまでが大変らしい。断られたらどうしようとか考えて、それこそ清水の舞台から飛び降りる覚悟でするものだそうだ。それが、私たちはまだ2回目のデートだというのに、既に親をも巻き込んで結婚を前提にしているかのようだ。
芝生公園では、真知子さんが用意したビニールを芝の上に広げ、二人は座った。
「今日は、真知子さん、サンドイッチなの?美味しそうだね。立待岬で食べたお弁当も美味しかったけど。真知子さんは、料理が上手なんだね!」
私はお世辞ではなく、本当にそう思った。ツナや卵、それにハムとレタスのサンドイッチなどたくさんの種類がある。見た目もキレイだ。真知子さんの手作りの料理が食べられる。こんな幸せな日が訪れるなどとは、数か月前までは夢にも思わなかった。私は余りにも嬉しくて、この幸せが永遠に続くことを祈った。
お腹も一杯になりしばらく休んだ後、園停に向かった。話をしながら歩くと、直ぐに着いた。萌える若葉の中に、園停はあった。
近づくと枯山水の奥にとても古びた園停が見えた。
数寄屋造りの建物の中に入ることが出来るという。私と真知子さんは、入ることにした。畳の部屋には入れないので、廊下を歩きながら中の様子を見学した。前を歩いていた、いかにも品のある高齢の男の人が感心したように呟いた。
「あの欄間は透かし彫りだ。贅を尽くしたとはまさにこのことだ」
確かに素人の私が見ても素晴らしいものだと理解できた。縁側から見る庭の風景もまた見事だった。ずっと見ていたかったが、後ろには何人かの見物客がいたので外に出た。
この日の見晴公園でのデートも楽しかった。でも、人生には幸せな日ばかりは続かないのだということを、間もなく知らされることになるとは予想だにしなかった。
【第8章 二十間坂から元町、そして赤レンガ倉庫への散策】
私は冒頭(第一章)で述べたように、昨夏に古希を迎えた。自分では、まだまだ体力も思考力も衰えていないと確信していた。だが、やはり年齢は噓をつかない。靴下を履くとき、片足立ちで難なくできていたはずが、最近よろめくようになった。また、人の名前が喉元で止まったまま暫く出て来ない。それでも出てくればまだましな方で、酷いときには諦めることもある。
長々と言い訳をしてしまった。実は、前回二回目の最後の2行目「人生には幸せなことばかりは続かないのだということを、間もなく知らされることになるとは予想だにしていなかった」という、この文面の言い訳なのである。時系列的に、私は間違いだったと後から気付いた。私たちの楽しい関係は、まだこの時からしばらくの間は続いたのである。お詫びして訂正したい。
話しを先に進めたい。私はこの病院で働き始めてからまだ2ヶ月しか経っていない。その間に既に2回デートをしている。また、仕事帰りのバスの中で週に2回は必ず会う。デートの回数だけでは、二人の心の距離は計れない。私は、もはや真知子さんのいない世界は考えられなくなっていた。
東京の家具製作会社で働いていた伊藤智之から、レントゲンの学校に誘われなかったら、またこの病院に就職していなかったら真知子さんと会うことは万に一つもあり得なかった。今更ながら、伊藤には感謝してもし切れるものではない。それに人生の不思議なめぐり合わせにも感謝せずにはおられない。
真知子さんとのデートは、1回目が立待岬、2回目が見晴公園(香雪園)だった。そして3回目のデートは函館山の夜景だった。素晴らしい夜景だった。心から堪能して帰ろうとロープウェに向かっていた時、真知子さんはふいに私の胸に飛び込んで来た。とても私の胸は高鳴ったのを覚えている。次のデートは五稜郭にしたいと、その時私は真知子さんに言い、真知子さんも快諾してくれた。
函館山の夜景でのデートから数日経ったある日、真知子さんは空いているバスの中で私に言った。
「晴彦さん、この前、五稜郭に行きたいと言っていたわよね。私、よく考えてみたら私の家から近いし知り合いの人も多いから、出来ればもう少し離れた場所にして貰えたら嬉しいなって思ったの」
最近、病院の中で二人の噂が立ち始めているらしい。私は一度も聞いたことがないが、真知子さんは検査室の親しい友人から聞いたらしい。バスの中かデートの時かは分からないが、誰か病院関係者の人に会ったようだ。真知子さんは、それが気になるらしい。
「真知子さん、僕は噂になっても全然平気だよ。反対に真知子さんとの噂なら、嬉しいくらいだよ」
真知子さんは、また頬を淡いピンク色に染めて言った。
「私だって、別に噂なんか気にしたくないわ。でも、知ってる人に会ったら、挨拶しなきゃならないのが少し恥ずかしいの。ねえ、晴彦さん、五稜郭じゃなくて、二十間坂から元町辺りを歩いて、それから赤レンガ倉庫を見て回るというコースはどう?」
函館は、それ程広い街ではない。何処に行こうとも、誰か知り合いに会う可能性は高い。だが、そのリスクは小さくしたい。まして、真知子さんの家から五稜郭は近い。真知子さんの父の会社の社員も真知子さんの顔を知っている。もちろん私たちの職場の知り合いも多い。私は納得して言った。
「うん、そうしよう。別に誰に会っても恥ずかしいことなんかないけどね。でも、なるべくなら会わないことに越したことはないからね」
それから暫くして、二人は市電函館駅前で待ち合わせをした。私はやはり、待ち合わせの10時よりかなり早めに着いた。真知子さんも気遣いをしてくれて、20分も前に来てくれた。今日は、お弁当でなく末広町辺りで食べようと二人で決めている。
今日もお天気に恵まれた。真知子さんは、いつものようにお洒落な姿で、私には眩しい。私は服装などには無頓着な方なので、うまく説明できないのが悔しい。強いて言えば、薄いブルー系のワンピース姿で、首には細い金のネックレスが着けられている。
市電函館駅前から十字街で降りた。二十間坂までは五分もかからない。二十間坂は明治時代に大火があり、防火帯として18間(36m)に拡張されたらしい。両側の木々の緑が爽やかだ。
緩い登り坂を二人は手をつないで歩いた。真知子さんは健脚だ。私の手を引っ張るように軽やかに、鼻歌交じりに歩く。私と会う時の真知子さんはいつも明るく朗らかだ。
「晴彦さん、この坂道を歩いたのは初めて?」
「うん、初めてだよ。元町の方も行ったことがないし、今日は楽しみだったよ。今日のお昼は、いつもご馳走になってばかりいるから、真知子さんの好きなものを奢るからね」
私がそう言いうと、真知子さんは嬉しそうに私の手を強く握った。前にもそういうことがあった気がする。真知子さんのストレートな気持ちが伝わる。私も、少し強く握り返す。
突き当り近くまで歩くと東本願寺函館別院が見えてきた。明治40年の大火で類焼し、大正4年に日本初の鉄筋コンクリート造りとして建て替えられたそうだ。国指定重要文化財に指定されているらしい。
「あっ、そうだ。見晴公園の時だったか、晴彦さんにお話ししたと思うけど。お母さんがね、また晴彦さんに会いたいって言うの。だからわたし、もう少し待って欲しいと晴彦さんが言ってるって話したら、でも会いたいって。私がどういう人とお付き合いしているのか知りたいみたい」
私は真剣に真知子さんと交際している。誰に後ろ指をさされることもない。真知子さんのお母さんが、私に会いたがる気持ちもよく分かる。
「真知子さん、真知子さんのお母さんに心配をかけるのは可哀そうだから、いつがいいか聞いてみて」
私がそう言うと、真知子さんの表情がパッと輝いた。
「ありがとう、晴彦さん。私も両親に会って欲しいと思っていたの。嬉しいわ。今夜にでも、お母さんに話してみる。お母さんの喜ぶ顔が見えるようだわ」
真知子さんは素直に喜んだ。楽しい会話をしながらの時の流れは速い。二十間坂を通り過ぎ、右に曲がるとカトリック元町教会だった。この教会も歴史がある。初めの教会は安政6年に建てられたという。現在の建物は大正12年に再建されたものらしい。驚くことに大聖堂内の祭壇一式はローマ教皇から贈られたものだという。
函館は素晴らしい。至る所に心を満たしてくれる名所がある。私は真知子さんと一緒に歩くだけでも幸せだ。それなのに歩くたびに、函館は私に感動を与える。この函館で真知子さんと一生を過ごせたら、お金も名誉も要らない。欲しいものは、二人の健康だけだ。それさえあれば、本当に何も要らない。
それから少し先の旧函館区公会堂まで足を延ばした。この旧公会堂は、明治40年の函館大火により焼失してしまったので、住民の集会所や商業会議所として3年後に建てられたそうだ。和と洋の要素が融合した建築意匠に優れ、館内に置かれた家具の保存状態も良いことから国の重要文化財に指定されているらしい。
私は時計を見た。もう11時半を過ぎていた。今日は、結構歩いた。若い二人だから疲れはしないが、だがお腹の虫が泣き出しそうだった。
「真知子さん、もう直ぐお昼の時間になっちゃうから、末広町まで歩いてから食事にしない?」
真知子さんは若くて元気だ。
「私、今朝ね。パン1枚しか食べてこなかったから、美味しいお寿司なんか食べたいな。それに今日は、晴彦さんの奢りだし、遠慮しないでお腹一杯ご馳走になっちゃおうかな」
私は普段無駄遣いをしない。今は車を買うために預金をしているくらいだ。
「それじゃ、末広町でお寿司を食べて、それから赤レンガ倉庫を見て、最後にその辺りでお茶を飲んで帰るというスケジュールではどう?」
私がいかにも物知りという風に話したものだから、真知子さんが不思議そうに言った。
「晴彦さん、元町方面は初めてだと言っていたのに、何で急に詳しくなったの?」
「白状するけど、本屋で『二人の函館街歩きコース』」という雑誌を買って、昨日の晩に読んだんだ」
どうりでという風に真知子さんは頷き微笑んだ。だが少しお気に召さなかったようだ。
「函館は私の街なんだから、晴彦さん、私に任せなさい!分からないことは何でも聞いてちょうだい。でも、今からお寿司を食べるのに、しかめっ面は終わりにして、私が美味しいお店を探してあげるわ」
真知子さんは、私の手を引いて急に急ぎ足になった。末広町までは大した時間は掛からなかった。通りを歩いていくと、幾つかのお寿司屋さんがあった。函館なので、新鮮なネタのお寿司が食べられそうだ。数件のお店を通り越してから、真知子さんが言った。
「晴彦さん、ここにしましょう。大丈夫、私が保証するわ」
確かに店構えもしっかりしていて、高級店のようだ。私は、財布の中身が気になったが、恥ずかしい思いをしないようにと、昨日のうちに信用金庫から軍資金を用意しておいたのを思い出した。
「真知子さん、いつもお弁当をご馳走になってばかりで申し訳ない。今日は遠慮しないで好きなものを食べて」
私は落ち着いた口調で、お金はご心配なくと言わんばかりに胸を張った。真知子さんは、さっそくメニューを覗き込んでいる。
「ああ~ どれも美味しそう!迷っちゃうな~」
私は、真知子さんはやはりお嬢さんだと思った。屈託がない。私など、こんな高級そうなお店入ると、緊張し身構えてしまう。
暫く二人で迷ったあげく、真知子さんが海鮮丼、私は握りにした。初めて二人で食べる寿司だ。今後のために聞いておきたかった。
「真知子さんは、お寿司の中では何が好き?」
真知子さんは間髪を入れずに答えた。
「私は、いくらとウニとマグロの中トロが大好き。晴彦さんは?」
私はそんなに寿司を食べた経験がない。実家では、殆んど食べた記憶がない。東京の家具製作会社の忘年会で食べたくらいだ。だから、何の寿司が好きと聞かれてもうまく答えられない。
「僕は、お寿司なら何でも好きだよ。コハダとかイカなんかが好きかな」
貧乏な生活をしてきたことは恥ずかしいとは思わない。でも、こんなところで、どういう生き方をして来たかが分かってしまう。真知子さんは、お茶をすすりながら、嬉しそうに私を見つめている。
やっと海鮮丼が運ばれてきた。私の頼んだ握りはそれから程なくして運ばれて来た。函館の魚市場からの仕入れたというネタは確かに新鮮で美味しかった。真知子さんは割り箸を持ち、ネタにほんの少しだけむらさきを付けて食べる。上品だ。私は舎利にたっぷりとむらさきを付けて食べる。
お寿司はリーズナブルな料金だった。また、二人で食べに来ようと約束して店を出た。今度は、赤レンガ倉庫に向かって歩く。前夜調べたデータでは、500mと少しだ。10分も歩けば着くはずだ。私が調べたのを知っていながら、真知子さんは私の手を引きながら、次の角を左とか指示を出す。でも、決して嫌味などではなく、本当に屈託のない人なのだと思った。そんなところも可愛い。函館山を背にして歩いて行くと真知子さんが、指を指して言った。
「あそこが金森赤レンガ倉庫よ!」
思いのほか人が多かった。観光客の姿が目立った。潮風が少し強く、真知子さんの前髪がなびいた。
初代渡邉熊四郎が明治時代に開業した「金森洋物店」が起源という。金森赤レンガ倉庫というのが正式な名称らしい。左手に海が広がり、右手には倉庫群が連なっている。私は、真知子さんから手を放し、少し先に走って振り返った。函館山と赤レンガ倉庫、そして真知子さんの姿が調和して1枚の絵画になった。
「真知子さん、素晴らしいところだね。僕はカメラを持っていないけど、近い内に買おうと思っている。真知子さんの姿も撮りたいし」
真知子さんも頷いた。これからの二人の歴史を画像に刻んで行きたかった。真知子さんへの愛の高まりを記録しておきたかったのだ。
赤レンガ倉庫を歩いていくと、七財橋という橋が架かっていた。そこから振り返った景色もまた美しかった。真知子さんも私の真似をして振り返った。
「本当に、素晴らしい景色ね。晴彦さんと一緒だと、余計にキレイに見える気がする」
私は、恥ずかしくなったっが、それでも嬉しかった。この今の気持ちを私は生涯忘れることはないと思った。
しばらく散策してから、赤レンガ倉庫の中のコーヒーのお店に入った。
今日も楽しい一日だった。私はとても幸福な青春を生きている。すべて真知子さんのお陰だ。一緒になったら、きっとこの人を守って生きて見せる。生涯、この人だけを愛し続ける。私は、真知子さんの笑顔を見つめながら、そう心に誓った。
【第9章 真知子さんのお母さんと一緒の食事】
真知子さんのお母さんに心配をかけるのは、私の本意ではない。もちろん初めての顔合わせで、将来を約束される訳でもない。だが、二人の真摯な交際を信じて、温かい眼差しで応援して欲しいと思っている。
ただ、私には一抹の不安があった。初めて立待岬をデートした時に真知子さんが言ったことばである。
「私の父は、建設会社を経営しているの。私は薬剤師だから、家業は継げないし。父は、いろいろ考えているみたい。いずれお婿さんを貰って、お婿さんに会社を任せたいようなことを私が中学生の頃言ったことがあるわ」
正直、この時の言葉が、私を真知子さんの両親に会うのをためらわせる。真知子さんのお父さんは二人の交際を歓迎してくれるだろうか?
いつかは通る道だ。覚悟をした私は、真知子さんの家を訪問する約束をした。
ある日曜日、前日に理髪店に行き、そして一着しか持っていないスーツを着て家を出た。約束の夕方6時少し前に真知子さんの家に着いた。5~6段ある階段を登り、玄関のチャイムを鳴らした。待っていましたとばかりに、玄関のドアが開き、真知子さんの満面の笑みが私の目の前に迫った。
真知子さんのお母さんも玄関に顔を見せて、「さあ、どうぞ!」と家の中に招き入れてくれた。
応接間の椅子に座った瞬間、私と真知子さんの生活のレベルの違いを感じた。広い室内にはグランドピアノが置いてあり、大きなマントルピースは冬の寒さからこの家の住人を守っているかのようだ。私は、貧しさを恥じてはいないが、まだ世間に疎い私は圧倒されて緊張した。
真知子さんがコーヒーを運んできた。決して派手さはないが、その黒く光ったコーヒーカップにも何故か威厳のようなものが感じられた。私の横に真知子さんは座った。今日の真知子さんは普段着という格好で、白のセーターに薄茶のスカートをはいている。
「晴彦さん、ミルクと砂糖はいかが?」
「砂糖を一つだけ・・・・」
私は思うように言葉が出て来なかった。ちょうどその時、ノックをして真知子さんのお母さんが入ってきた。真知子さんは、私のカップに砂糖を入れてくれ、おまけにスプーンでかき混ぜてくれた。その様子を見ながら、真知子さんのお母さんは微笑んだ。その姿からは、優しさが漂って来るような感じがした。また私への第一印象も決して悪いものではなかったようだと私は安心した。
「今日は、生憎、お父さんが仕事関係の会合が急遽入って、夕方出かけてしまったの。残念だわ」
真知子さんは、言葉とは裏腹に少しも残念そうには見えなかった。
「晴彦さんと仰いましたよね?真知子がいつもお世話になってすみません。真知子は幼い頃は体が弱くて、よく病院通いをさせられましたけど、高校生の頃から病気をしなくなりました。それどころか、最近はいつも機嫌が良くて、台所にもしょっちゅう入ってきて私の手伝いをしてくれるんですよ」
真知子さんのお母さんの言う意味は、野暮な私にも分かる。真知子さんのお弁当が美味しい訳もこれで分かった。この話をしてくれた真知子さんのお母さんの真心が伝わってきて、私は嬉しさがこみ上げた。きっと、このお母さんは二人を応援してくれるに違いない。
「晴彦さん、今度は真知子の父親がいるときに、また遊びに来てくださいね」
真知子さんのお母さんは、私を父親にも会わせたいようだ。私は、真知子さんのお母さんが初対面ながら好きになった。やはり真知子さんに相応しいお母さんだと思った。
「今日は、たいしたおもてなしも出来ないけど。夕飯の準備ができるまで、晴彦さん、真知子の部屋で待っていて」
真知子さんのお母さんは、笑顔を真っすぐ私に向けて言った。その一言で私は、真知子さんの部屋に入ることとなった。
「驚いた。今日、初対面なのに、真知子さんの部屋に上げて貰えるなんて信じられない!」
二人だけになった安堵感から、私は思わず呟いた。
「晴彦さん、母はね、晴彦さんが気に入ったのよ。私には良く分かったわ」
真知子さんも、それがひどく嬉しそうだった。
真知子さんの部屋は、とてもキレイに整頓されていた。大きな熊の縫いぐるみが少し不自然のような気がしたが、ピンクのカーテンの部屋には、旅行のお土産やら、たくさんの置物が専用の木製のケースに収められていた。本棚には、やはり薬学の専門書が所狭しとばかりに並んでいる。私の散らかし放題の部屋とは、月とすっぽんである。
私は、真知子さんの家に伺うのは、まだ先にしたいと考えていた。前にも話したように、もっと社会人としての自信を持ってからが良いと考えていた。真知子さんのご両親に少しも恥ずかしくないと思える人間になってからにしたかった。
それが、こうも簡単に真知子さんの家を訪問することになるとは!だが私は後悔どころか、本当に嬉しかった。真知子さんのお母さんを初対面で好きになるとは思いも寄らなかった。
真知子さんの話だと、元町でのデートから帰った夕方に、さっそくお母さんに話したらしい。「晴彦さんが、母に会うことを望んでいる」と。その時の母親は、とても嬉しそうだったという。
「真知子、晴彦さんという方は、何が好きなの?夕飯を一緒に食べたいと思って」
「晴彦さんは、私の作ったお弁当をいつも美味しいと言って、きれいに食べてくれるから、特に好き嫌いはないみたい。お母さんの料理なら、きっと満足してくれると思うけど。でも、お母さん、初対面の人に夕飯を出すの?」
真知子さんのお母さんは、ただ嬉しそうな顔をするだけで何も答えなかったそうだ。
真知子さんの幼い頃からのアルバムを捲っていると、階段の下から真知子さんのお母さんの声がした。
「お夕飯の支度ができたわよ~」
私は、階段を降りる前に、真知子さんを抱きしめて言った。
「今日はありがとう!真知子さんのお母さんに会えてうれしかったよ!」
真知子さんも私の背中に両腕を回し、顔を上げながら言った。
「お母さんが晴彦さんを気に入ってくれたから、もう大丈夫よ。お父さんは、お母さんの言うことなら絶対だから!」
そのまま、二人は初めての口づけをした。彼女の唇は柔らかく、甘い香りがした。
階段を下りながら、真知子さんは「今日は、カレーライスかな?」と小さな声でささやいた。食堂のテーブルに行くと、お母さんが白い皿のご飯の上にカツを乗せ、カレーをよそっていた。
「うわ~ 僕、カツカレー大好きです!」
私は少し興奮したように声を上げた。よく見ると私の皿のカツが、ほかの二人よりもはるかに大きかった。こんなところからも真知子さんのお母さんの気持ちが伝わる。野菜サラダなのかテーブルの真ん中に大皿が置かれていた。
「真知子、晴彦さんにパスタサラダをよそってあげたら。晴彦さん、まだカレーもたくさんあるから、いくらでもお代わりして頂戴ね」
真知子さんは、取り皿に大盛りのサラダをよそってくれた。何と表現したらよいのだろうか。母子でこの私に心からのおもてなしをしてくれている。私は、泣き虫だ。嬉しくて、胸が詰まった。
東京の家具製作会社の寮で、仲間と一緒に食べる食事も旨かった。だがいつもという訳ではなく、そうでないことの方が多かった。一人で食べる食事は、寂しく味気なかった。そんな時、私はいつも10年後の自分の姿を想像していた。小さなアパートだけれども、優しい妻と元気な子供たちがいる。賑やかな家族と一緒の食事は、なにより美味しい。きっとそうなる。今は、その時の喜びを何倍にも大きくするための試練だ。そう思いながら独りご飯を食べていた。
真知子さんのお母さんの料理は美味しかった。カツは柔らかく、サクサクしていた。カレーも何か隠し味が入っているようで、我が家のカレーとは一味違った。私は、食べ過ぎた。お腹が苦しい。
「どう、晴彦さん。お腹いっぱいになった?」
真知子さんは、私の顔を見ながら言った。真知子さんのお母さんも続けて言った。
「晴彦さん、こんな食事で良かったら、時々食べに来てね。主人は、会合や出張で家を空けることが多いものだから、男の人がいると安心だわ。ねえ、真知子」
「私も、お母さんと二人っきりで食べるより、晴彦さんと3人で食べる食事の方がずっと美味しいわ」
私は、お腹の苦しさと闘いながら、精いっぱいの笑みを浮かべた。時刻は、もう8時半を過ぎていた。明日も仕事だ。月曜日は特に忙しい。あまり遅くまで真知子さんのお家にお邪魔している訳にはいかない。私は、遠慮がちに言った。
「もうそろそろ、帰ります。明日も、また仕事ですから。お母さんの料理はとても美味しかったです。また、ご馳走になりに来ます。真知子さんのお父さんにも宜しく伝えてください。今日は有難うございました」
私は、真知子さんのお母さんに深々と頭を下げた。玄関まで真知子さんのお母さんは送ってくれ、真知子さんに言った。
「真知子、少し先までお送りしたら」
玄関の戸を閉めるとき、また私は深々とお辞儀をした。
ああ~良かった。真知子さんのお母さんとは気が合いそうだ。心配なんかすることはなかった。もっと早く来ればよかった。私は、心からそう思った。真知子さんと手を繋ぎながら、五稜郭駅に向かって歩いた。途中、小さな公園があった。私は真知子さんの手を引いて、公園のベンチに二人で座った。
「真知子さん、今日は楽しかったよ。もっと早く来ればよかった」
私がそう言うと真知子さんは、私の肩に寄り掛かった。再び私は、真知子さんの柔らかく甘い唇に自分の唇を合わせた。真知子さんは目を閉じて、私に身を任せていた。
【第10章 きじひき高原へのデート】
私は、真知子さんのお母さんに会い、とても良い感触を得られたと思った。間違いなく二人の未来は明るいと信じて疑わなかった。
安心したというか、何も恐れるものはないと、私たちはその後も二人だけの世界の中で、青春をまさに謳歌していた。立待岬、見晴公園(香雪園)、函館山夜景、元町辺りと楽しいデートを重ねたが、もちろんそれだけでは終わらなかった。
ある時、仕事帰りのバスの中で真知子さんは言った。
「晴彦さん、函館はもう何ヶ所も二人で行ったし、今度は函館以外の、例えば晴彦さんの住む上磯町や大野町方面にも行ってみたいな」
確かに函館は素晴らしい。まだまだ回っていない所も多い。だが、函館ばかりが北海道ではない。私の生まれた上磯町や大野町辺りにも名所はある。(平成18年2月1日に両町が合併して北斗市になる)
「真知子さん、それなら今度はきじひき高原とか八郎沼なんかに行ってみない?」
すかさず私が言うと、きじひき高原までは、バスで行くのかと真知子さんは聞いてきた。
「大丈夫だよ。真知子さん、車はまだ持っていないけど、函館駅前のレンタカーを借りるつもりだから」
私は高校3年の春ごろ車の免許を取った。実家は貧しい。免許取得の経費を親に無心するのは憚られた。私は高校2年生の夏休みからアルバイトを始めた。母の働く小さな漁港で、魚の選別や雑役等の仕事を夏休みの間ほぼ休みなく続けた。
だが、夏休みの期間だけでは自動車教習所の費用を賄え切れなかった。その為、冬休みもアルバイトをせざるを得なかった。魚の種類と大きさに選り分ける仕事は、ゴムの手袋の内側に綿の薄手の手袋を二重にはめても指先がかじかんだ。お金を稼ぐ辛さと、両親の有難さを初めて知った。私は、そのアルバイトのお金で無事、運転免許を取得することが出来た。母は褒めてくれた。
今日は、きじひき高原へのデートの日だった。私は函館駅前でレンタカーを借り。真知子さんと約束したバス停に向かった。車のハンドルを握るのは暫く振りだった私は、交通事故だけは絶対起こしてはならないと自分に言い聞かせた。助手席に真知子さんを乗せるのだから当然だ。
約束のバス停に着くと、真知子さんは待ちかねたように立っていた。今日の真知子さんは、縁の広い真っ白な帽子を被り、スラックス姿である。真知子さんの肌は白い。陽を浴びるとすぐ赤くなる。洒落た帽子を被った今日の真知子さんも眩しい。
真知子さんが乗り込み、荷物を後ろの席に置いた後、私は言った。
「真知子さん、おはよう。暫く振りの運転だから気を付けるからね」
私の声に頷きながら、弾んだ声で言った。
「晴彦さん、私と一緒の日はいつも晴れね!私は晴れ女なのよ。私と一緒にいれば、一生、雨に濡れる心配はないわよ!」
私は、驚いた。真知子さんは、自分で言っている意味が分かっているのだろうか?私は言葉に詰まりながらも、やっと言葉を返した。
「夏なら、濡れても構わないけどね」
「あっ、そうなの。私と、夏は会いたくないってわけ?」
言葉だけなら絡んだ言い方に聞こえるかも知れない。だが、真知子さんの言葉には嫌味がない。
「今日は、お弁当を作ってきたのよ。何のお弁当か当ててみて」
私は、慎重に運転している。真知子さんの話しに真剣に考える余裕はなかった。私は信号で停まったとき、ふと息を吐いてから答えた。
「多分、おにぎりかな。僕は、たらこのおにぎりと鮭のおにぎりが大好き」
真知子さんは笑いながら言った。
「今日はね。お稲荷さんと鶏のから揚げ。それから母自慢の漬け物よ」
昨夜、「明日は晴彦さんときじひき高原に行く」と、真知子さんはお母さんに話したという。その時、お弁当は何にしようかと相談すると、昨夜のうちに油揚げを煮てくれ、母特製の漬け物も用意してくれたという。
「お母さん、晴彦さんがすっかり気に入った見たい。今朝も、唐揚げを揚げながら鼻歌を口ずさんで、まるで母が晴彦さんと出かけるみたいだった。可笑しいでしょ?」
「あれ、油揚げをお母さんが料理してくれ、唐揚げもお母さんが揚げたの?真知子さんは?」
私が意地悪く言うと、真知子さんは頬を膨らませて言った。
「私だって、油揚げにご飯を詰め込んだり、漬け物を切ったり、大変だったのよ!」
私は、車の運転の緊張がほぐれて、思わず笑ってしまった。
「真知子さんとお母さんの合作のお弁当を食べられるなんて、幸せだよ。本当に嬉しいよ。ありがとうね。真知子さんのお母さんの誕生日、いつかは知らないけど、その時にはお花でも届けようかな!」
私はフォローしたつもりだったが、また失敗してしまった。
「晴彦さん、私はまだ一度も、お花もプレゼントも、晴彦さんから貰ったことなんてないんですけど」
「ああ、そうだったね。僕は給料が安いんで、高級なものは上げられないけど、何が欲しい?真知子さん」
真知子さんは、私のこの一言が嬉しかったらしい。笑顔が弾けた。
「私、安物でもいいから、お揃いの指輪が欲しい!」
一瞬ドキっとしたけれど、私は即座に答えた。
「じゃ、近いうちに買いに行こう!」
すっかり真知子さんの機嫌も直り、二人はたわいもない話をしていると、いつの間にかきじひき高原に着いてしまった。長い時間運転をしたが少しも疲れなかった。車という同じ空間で、同じ空気を吸ったのが何故かとても嬉しかった。遠くには函館山と津軽海峡が見えた。
また、壮大に広がる大沼・小沼の風景と悠然とそびえ立つ駒ケ岳を一望することができた。
私は、まだカメラを買っていなかったが、この日は真知子さんが持ってきた。三脚を立てて、函館山や駒ケ岳をバックに二人の笑顔溢れる姿を何枚も撮った。
昼の時間になり、二人でベンチに座り、真知子さんとお母さんの手作りのお弁当をご馳走になった。お稲荷さんは、程よいご飯の量で、味付けも最高だった。もちろん唐揚げも美味しいし、唐辛子をほんの少しまぶした白菜の漬け物も後を引く美味しさだった。
食事が終わったころ、私はいつも聞こうとして忘れていたことを思い出した。
「真知子さん、いつも思っていたことなんだけど、真知子さんと帰りのバスは一緒になるけど、朝は会ったことがないよね。どうして?前から不思議だなって思っていたんだ」
真知子さんは、なぜ今更という感じの顔をして言った。
「叔父がね、父のすぐ下の弟なんだけど、私たちの勤めている病院のすぐ近くの会社で働いているの。管理職をしていて、いつも定時には帰れないから、朝だけ少しだけ遠回りをして迎えに来てもらっているの。本当は、晴彦さんと会うようになってからは、お断りをしたいと思っているんだけど、私の方から頼んだことだし、言い出せなくって」
私はようやく喉のつかえが取れた。あまりに簡単な理由で拍子抜けをしてしまった。まだ、夕方までには大分時間がある。私は、八郎沼に寄ることを提案すると、真知子さんもぜひ行ってみたいと言う。
冬までには車を買いたいと思っているなどと話しているうちに八郎沼に着いてしまった。大した距離はなく、レンタカーの運転にも慣れたせいだ。八郎沼はスイレンの葉で覆われ、真っ赤な花が葉の間に幾つも咲いていた。
私と真知子さんの、楽しいデートはその後も続いた。生きる喜び、生きる楽しさに私は埋没していた。
それから数週間後の9月に、私の職場の配置換えがあり、私は「消化管造影検査室」に配属となった。その後は、第6章で述べたとおりである。
私は、慣れない仕事で毎日疲れ、休日は消化管造影検査の専門書の勉強をしていた。当然ながらデートの頻度は減った。真知子さんは、私の気持ちを尊重してくれ、バスの中での短い逢瀬だけで満足してくれていた。指輪を買うという約束も先延ばしにしていた。
私は真知子さんの深い愛情を感じた。いつかこの人を必ずお嫁さんにしたい、私は心の中で誓った。
【第11章 初めてのペアリング】
私は9月より消化管造影検査室配属となった。私は少しでも早く、この仕事のプロにならなければと考えた。医師の正確な診断に役立つ仕事をしなければと、私は休日も専門書を読み続けた。
平日は、土井先輩にお願いし技術的な指導を受けた。土井先輩は、将来の放射線科を担う器の大きな人だ。きっと辛い思いして得たに違いない、貴重な知識と技術を欲しげもなく私に提供してくれたのだった。
それだけではない。検査を受ける患者さんの心理までをも丁寧に教えてくれた。思いやりを込めた、たった一言の言葉掛けが患者さんの不安と恐怖を和らげると、真剣な眼差しで自らに言い聞かせるように土井先輩は話してくれた。
土井先輩のような技師に検査をして貰えたら、患者さんも安心して身を任せることが出来るに違いない。私は土井先輩に心から尊敬の念を抱いた。
そう言えば、真知子さんとはしばらくデートもしていない。
今朝も疲れから10時過ぎに起きだし、遅い朝ご飯を食べると、私は病院から借りてきた分厚い専門書を開いた。だが、開いては見たものの、真知子さんの顔が浮かんで集中できない。困った私は、電話器の前でしばらく悩んだが、思い切って真知子さんの家に掛けてみることにした。鼓動の激しさを感じつつダイヤルを回すと、真知子さんの明るい声が聞こえてきた。私は、ホットして言った。
「もしもし、あのう勉強するのが疲れちゃって・・・」
そこまで言うと、私に任せなさいと言わんばかりに真知子さんは言った。
「どうしたの?疲れちゃったの?私が上磯までポットにコーヒーを入れて届けてあげる」
私は、普段着のまま上磯の駅に向かった。
真知子さんは優しい。真知子さんの届けてくれたコーヒーを、漁港の堤防でペンキの剥げた長椅子に座って飲んだ。その前に、私は彼女のスカートが汚れないように、ポケットから少し色あせたハンカチを取り出し、真知子さんの座る位置に置いた。
「真知子さん、僕は普段あまりコーヒーは飲まないんだけど、このコーヒーは香りもいいしコクがあって美味しいよ」
私は自分の味覚が正しいのか自信はなかった。
「へえ~ 晴彦さん、なかなかコーヒー通なんじゃない。私もこのコーヒーが大好きで、いつもこのメーカーに決めているの。これインスタントなのよ。そうは思えないでしょ?」
真知子さんは、函館で名の売れている洋菓子店のクッキーをバックから取り出した。
「勉強して頭が疲れたときは、甘いものが良いのよ。残ったら持って帰って後で食べてね」
私の手を取り、私の右手にクッキーを乗せてくれた。
「このコーヒーにクッキー、とても合うよ。ありがとう、真知子さん」
港も今日は日曜日だ。遠くで何人かが釣りをしていたけれど、誰も二人など眼中にはなく、竿先の彼方を見つめているようだった。
真知子さんは、いつかのように私の肩に上体を預けた。私は日中にも拘わらず、真知子さんの体を引き寄せ、口紅が薄く引かれたピンクの唇に自分の唇を重ねた。
二人は暫くそうしていた。私は、これが青春なのだと心に言い聞かせた。これが青春を謳歌するということなのだと自らに言い聞かせた。彼女と唇を合わせることは、世界で一番素晴らしい人を私一人が独占し、これからの人生を彼女守って生きていくのだという覚悟の儀式のように思われた。
私を心から信頼し、私の胸に身を委ねる彼女はたまらなく愛しい。だが、いつまでもこうしている訳にはいかなかった。私は、時計を見た。時計の針は、もう直ぐ午後1時を指している。私はいつかの約束をふと思い出して言った。
「真知子さん、もう午後1時だよ。お腹すいたでしょ?これから、通りの食堂でお昼を食べて、それから指輪を買いに行こう!」
私は真知子さんに耳元へ優しく言った。
「エッ ほんとう!うれしい!」
真知子さんは私から身を離し、私の顔を覗き込むようにして言った。それから、再び私の胸に顔をうずめた。少しして顔を上げた真知子さんの頬には涙が光っていた。
上磯駅前は、私の庭のようなものである。よく行く中華屋さんに入った。真知子さんは味噌ラーメンを食べたいと言った。私は、中華丼にした。暫くして味噌ラーメンと中華丼は運ばれた。真知子さんは美味しいと言いながら麺をすすった。彼女は食べ方も上品だ。私のように大きな音を立てたりはしない。ふと、私は財布の中身が気になりだした。これから二つの指輪を買おうとしている。まだ給料を貰ったばかりだけれど、当然大金など持ち合わせている筈はなかった。
貴金属を売っている店の前は何度か通ったことがある。だが、入るのはもちろん初めてだ。この店には真知子さんの気に入る指輪はあるだろうかと、私は心配になった。店のドアを開けて、私は真知子さんを先に入れた。真知子さんは、とても嬉しそうだ。お嬢さん育ちの真知子さんには、私のように財布の中身を心配することはないのだろうか?
陳列棚の奥にいた20代と思しき女性は「いらっしゃいませ」と言いながら、笑顔で二人の前に歩み寄った。
「ご婚約かご結婚の指輪をお探しですか?」
私が言葉に詰まっていると、真知子さんが答えてくれた。
「いえ、まだ婚約をしている訳ではないんです。でも、二人揃いの指輪が欲しいと思いまして」
女性店員は金額の張る指輪から順に、二人を案内した。それらの指輪に付けられた値札を見ると、私の給料ではとても手が届かないものばかりだった。私の顔色を見た真知子さんは店員に向かって言った。
「あのう、先ほどお話ししましたように、結婚指輪とか婚約指輪とかじゃないんで、高価なものじゃなくても良いんです。ちょっと他のも見せて貰っても良いでしょうか?」
奥の隅にある陳列棚へと真知子さんは私の手を引いた。
「この金額くらいで、私たちに合う指輪が欲しいんですが」
真知子さんが、女性店員に指で示した指輪の値札は、1万円に満たないものだった。いつも思うことだけれど、いかなる場所でも真知子さんは物怖じしない。何の知識も度量も持ち合わせていない私は、末広町でのお寿司屋さんの時のように、真知子さんに任せるしかなかった。男として少し情けないと思った。
安物と言える指輪でも、二人にとっては貴重なものである。真知子さんは、いくつもの指輪をケースから出して貰ったりしたが、なかなか決められなかった。女性店員は、他にお客がなかったためか、二人の我儘に愛そう良く接してくれた。
暫くしてから、やっと二人の指に合うお揃いの指輪に巡り合えた。可愛いケースに入れて包装してくれ、赤と青のリボンもサービスで付けてくれた。私はレジに行き財布を開いて思わず慌てた。
「赤いリボンの指輪は、晴彦さんからのプレゼントとして頂くわ。青いリボンの指輪は、私からのプレゼント。だから、お金はそれぞれ出し合いましょう!」
真知子さんは私の財布の中が見えたのか、とにかく私は半額の支払いで恥を掻かずに済んだ。お店を出ると、真知子さんは私に寄り添いそっと腕組みをして来た。私の胸は思わずキュンとなり、私はますます真知子さんが愛しくて堪らなくなった。
それから二日後、病院からの帰りにいつものバス停で私が待っていると、真知子さんは私の姿が見えたのか走って来た。今日もバスの席は空いていて、二人は仲良く並んで座った。
「あのね、あの日晴彦さんと上磯駅で別れて帰った夕方にね、台所で指輪のことを母に話したの。そしたらとても喜んでいたわ。その晩、父は会合とかで遅くなるらしかったけど、私たちのこと話したみたいよ」
真知子さんの表情は明るかったので、私の危惧していたことは、単なる杞憂かと安堵したのだった。
不思議なことに、その頃から真知子さんの様子が変わった。帰りのバスで会うことが少なくなり、会っても真知子さんの表情は暗く沈んだ様子だった。私が掛ける言葉も上の空のようで、下を向いて今にも泣きだしそうだった。
私は、ただオロオロするばかりで、何が何だか分からなくなった。
【第12章 こころの叫び】
月日の流れるのは早い。もう10月も半ばだ。私はもう半月近くも真知子さんと言葉を交わしていない。病院の薬局の奥に一瞬その姿を捉えることはできたが、顔を合わせることはなかった。
函館は8月から9月によく雨が降る。だがこの頃に何度もデートをしたり逢ったりしたが、雨に降られることはなかった。だが、10月に入り真知子さんと逢えなくなってからはよく雨が降った。
私はひとりバス停で真知子さんを待ったが、今日も真知子さんは来なかった。空いている席に座った私は、ぼんやり外を眺めていた。すると窓ガラスに水滴がしたたり落ちて来た。今日もまた雨である。
9月の初旬に、きじひき高原に行った時の真知子さんの言葉を思い出した。その時彼女は弾んだ声で言った。
「晴彦さん、私と一緒の日はいつも晴れね!私は晴れ女なのよ。私と一緒にいれば、一生、雨に濡れる心配はないわよ」
確かに彼女と一緒にドライブしたきじひき高原の時も、彼女の家に初めて伺った時も雨は降らなかった。二人でペアリングを買った日もそうだった。だが、彼女の言う通り、真知子さんのいない私一人の時には、どうしてこうも雨が降るのだろうか。この雨は、真知子さんが泣いているのか、真知子さんの涙なのか。それにしても真知子さんは一体どうしてしまったのだろう?
先月、上磯までコーヒーを届けてくれた日に彼女が言ったことばを私は思い出した。
「あのね、あの日晴彦さんと上磯駅で別れて帰った夕方にね、台所で指輪のことを母に話したの。そしたらとても喜んでいたわ。その晩、父は会合とかで遅かったらしかったけど、私たちのこと話したみたいよ」
その時の真知子さんの声は、確かに弾んでいた。それから彼女に何があったのだろう?真知子さんに心変わりがあったとは思えない。私は家に帰り、深夜に寝床に入ってからも考えていた。ふと思った。私が危惧していた、彼女のお父さんが原因ではないのだろうか?
私は、仕事中も気になって仕方がなかった。ある日の水曜日、私は5時ちょうどに私服に着替えて、職員通用口の近くで真知子さんの姿を待った。どうしたのかと訝しげに見つめる職員の姿もあったが、それどころではなかった。
暫くすると、真知子さんは通用口に現れた。私の姿を見ると驚いて、一瞬立ちすくんだ。私が「一緒に帰ろう」というと、頷いてハイヒールに履き替えた。バス停まで二人とも無言だった。少し待つとバスが時刻通りに現れた。バスの中は空いていたが、私はもちろん真知子さんと並んで座った。
真知子さんの表情は暗く沈んだ様子だった。私が掛ける言葉も上の空のようで、下を向いて今にも泣きだしそうだった。私は、どうしていいのか分からず、オロオロするばかりだった。真知子さんの降りるバス停が近づいた時、私は予め考えていた言葉をやっと伝えた。
「真知子さん、今度の日曜日、市電函館ドック前で午後2時に待っているよ。必ず来てね!」
他に客は数人いたが、私は真知子さんの横顔に少し大きな声で言った。真知子さんは小さく頷いたように見えた。それから日曜日までが長かった。早く真知子さんから事の真相を聴きたかった。だが、真知子さんを疑う気持ちは微塵もなかった。バスの中の真知子さんは、私の胸の中で思いっきり泣きたがっているのが私には分かったからだ。
ちょうどその頃、私の父が出勤途中で交通事故を起こし、救急隊の力により近くの総合病院に入院したのだった。幸い大きな怪我ではなかったが、それでも2週間の入院を余儀なくされた。私は仕事帰りに父の病室に寄り、洗濯物を届けたりと持ち帰ったりと、心の余裕を少し失いかけていた。
私の一方的にお願いだったので、約束とは言えなったが、真知子さんは必ず来ると私は信じていた。
(画像は、函館港です。ウキペディア様から拝借致しました)
真知子さんと会う日の午後、赤く腫らした瞼のまま、私は市電函館ドック前で降りた。私の告げた2時にはまだ随分時間があった。私は最近食欲がない。当然だった。母はそんな私に気付いたのだろう。今日も、出かけるならご飯を食べてからにしろ、と命令口調で言った。既に成人になった息子であっても、母は言葉を掛けずにはいられなかったのだろう。
雨が今にも降りそうだった。私は、折り畳み傘を2本用意して来た。辺りを散策していると、釣りをしている人が結構あちこちにいた。釣り人同士の会話から、狙いはアイナメやサバのようだった。私も釣りが大好きで、幼いころから近くの漁港の堤防でよく竿を振った。雑魚ばかりだったが、持ち帰ると母は焼いてくれたり煮てくれて、おかずの足しにしてくれた。あの頃が妙に懐かしくなり、私は目頭を押さえた。
漁港を歩いていると、時は確かに流れていた。真知子さんが市電から降車する時間が近づいた。私は市電函館ドック前に急いだ。何人かの釣り人が降り、最後に真知子さんが降りてきた。私は、精一杯の笑顔で声をかけた。
「真知子さん、今日は来てくれてありがとう」
真知子さんの綺麗にまとめられた髪の、その後れ毛が風でなびいた。真知子さんは、厚手のセーターにスカート姿だったが、いつもの華やかさはなかった。私に向けられた瞳には輝きがなく、視線は彷徨っていた。
私は、真知子さんの手を握り、どこに行くという当てのないまま歩き出した。結局先ほどの堤防の辺りに向かった。私は独り言のようにつぶやいた。
「毎日がつまらない。あれ程頑張ろうとしていたレントゲンの仕事もつまらなくなった。僕は、真知子さんが傍にいないと何もできないし、生きている意味が分からなくなってしまう。毎日、真知子さんはどうしたのだろうと、そればかりを考えて夜もよく眠れない」
私が話していると、真知子さんはいきなり嗚咽し始めた。私は驚いて漁港の傍の小さな公園に真知子さんの手を引いた。長椅子に座ろうとした真知子さんを止めて、私は自分でアイロンをかけた青い縞模様のハンカチを敷いた。
真知子さんは泣き続けている。私は、どうしていいのか分からなかった。ただ、真知子さんは私が嫌いになった訳ではないと知った。
「真知子さん、どうしたの?僕は、心に大きな穴が開いたようで、毎日が辛くてしょうがないよ!」
私が言い終わる前に真知子さんは体を私の方に向け、私の胸に顔を埋めた。大粒の涙が溢れているのが分かる。今まで我慢していた辛さを、そして悲しさを、ありったけ私の胸に吐き出しているかのようだった。
私は真知子さんの体を抱きしめたまま、泣き止むのをじっと待った。ポケットからティッシュを取り出し、真知子さんの頬をそっと拭った。
どの位そうしていただろうか?少しは気が晴れたのだろうか?真知子さんの泣き声が消えた。
「真知子さん、お父さんに何か言われたの?」
私の質問の答えではなかったが、真知子さんはやっと言葉を発した。
「私は、晴彦さんが大好き。死ぬまで一緒にいたい・・」
真知子さんは赤く腫らした眼差しで、私に言った。
「真知子さん、どうして仕事帰りにバスに乗らないの?」
私の問いに今度は黙ったままだった。多分、私を傷付けたくないのだろうと思った。私は、踏み込んだ言葉を発した。
「真知子さん、僕と結婚してくれる?」
やはり真知子さんは答えなかった。だが、私を見つめる瞳が、どうして私をそんなにいじめるのというふうに答えていた。
私は、また独り言のように話し出した。
「僕は、何度も誓ったんだ。真知子さんを一生守って生きて行くって。そして必ず幸せにして見せるって!真知子さんと僕はまだ大人の関係はないけれど、僕はとっくに決めていたんだ。真知子さんは世界で一番素晴らしい僕のお嫁さんだって。僕には真知子さんしかいない。真知子さんと結婚できないのなら、僕は生涯独りで生きる。真知子さん以外の女性なんて考えられない!」
真知子さんは、また私の胸に顔を埋め号泣した。それでも私は、私の心の奥底に仕舞い込んでいた熱情を止められなかった。
「僕の家は貧しいけれど、父も母も、僕と妹を精いっぱいの愛情で育ててくれた。お腹が空くことはあったけれど、寂しいとか、誰かが羨ましいなんて一度も思ったことなんてなかった。父と母が僕を産んでくれたんじゃなくて、僕が父と母の子どもに産まれるように神様に頼んだんだ。
真知子さん、僕のように、僕と真知子さんの子どもに産まれたがっている子がいるんだよ。僕はそう信じている。僕はその子を守ってあげたい。もし、僕と真知子さんが結婚しなければ、その子の小さな願いを夢を潰してしまうんだ!」
私は、何の根拠もない、だがいつも心に思っていたことを、真知子さんに叫ぶように話した。真知子さんは、私の胸の中で何度も頷いていた。真知子さんも私と同じなのだ。いつか私の顔中は涙と鼻水でくしゃくしゃになっていた。真知子さんは私の体にもたれていた体を起こし、香水の香りのするハンカチで私の顔を拭ってくれた。その顔は、やはり涙で溢れていたが、瞳はいつの間にか澄み切っていた。
「よく分かったわ。私たちの子どもに産まれたがっている可愛い子を裏切るなんてできないわ。私、頑張る!」
真知子さんが、何に対して頑張ろうとしているのかは不明だったが、私たちの心に綻びは微塵もなかった。真知子さんはいつもの笑顔を取り戻した。
「晴彦さん、今日はありがとう」
潮の香りのする風が二人の頬を撫でて行った。夕闇がせまり、灯台の白い明りが沖の船の姿を波の上に浮かび上がらせている。私と真知子さんは抱き合って口づけをした。信じ合えた喜びに、私は真知子さんの体を強く抱きしめた。いつの間にか西の空は茜色に染まっていた。
【第13章 査問委員会の当事者となって】
3日前、函館ドック前で会った時、私は真知子さんへの想いを激白した。だがそれは、私の独り相撲ではなく、真知子さんの私へのそれも同じだった。私たちの愛に、いささかのブレもなかった。二人の進むべき道は完全に一致した。この先に如何なる苦難が待ち受けていようとも二人の愛の力で乗り越えていける筈だった。
しかし、どうしたことだろうか?真知子さんは、またバスに乗らなくなった。お互いの気持ちに疑う余地はなかった筈だ。真知子さんは、何に悩んでいるのだろう?何に苦しんでいるのだろう?なぜ、私に打ち明けてくれないのだろうか?
ここしばらく、朝起きてから四六時中、そのことばかりを考えていた。
ある日、その日の最初の胃部レントゲン検査の患者は60代後半と思しき女性だった。女性は見るからに上品そうで、少しやせ形だった。消化器内科医の指示で、胃潰瘍の疑いとのこと。私はいつものように撮影を始める前に自分の名前を告げ、検査上の簡単な注意を説明した。私の話が終えると、看護婦が一時的に胃の動きを止める筋肉注射をし、少しして私は撮影を開始した。
順調に撮影は進んだ。胃底部の噴門近くに潰瘍らしい病巣が見られた。私はその部位を通常より数枚余計に撮った。更に、別の部位を撮ろうとした私は、撮影台の傾斜を、患者の体が多少逆さになるような位置にして撮影をした。撮影台を元の位置に下げ、続いてスポット撮影をしようとした瞬間だった。患者の女性はいきなり体制を崩し、撮影台から床に転げ落ちた。
私は慌てて駆け寄ったが、患者は意識を失っていた。近くにいた看護婦は脈をとり血圧を測定してくれた。私は焦りながらも、主治医の医師に連絡をした。僅か数分だったと思うが、私には何時間にも長く感じられた。医師の呼びかけに、患者は間もなく意識を取り戻したが、頭部外傷が疑われ入院することとなった。
このとき内科の医師は、「一過性の脳貧血からの転倒による頭部打撲」との診断を下した。
この件については即座に、院長始め事務長など幹部には知れ渡った。当院には「安全管理対策委員会」があり、この委員会には、副院長を始め各診療科の部長や検査科・放射線科・栄養科等の責任者が集う。「安全管理対策委員会」はその日の夕刻に開催された。今回は特に、私と現場にいた看護婦が招集された。
途中、司会役の内科部長が私に質問した。
「この患者の胃部レントゲンの撮影した高橋君、自分では過失があったとか、配慮が欠けていたとかの認識はなかったか?当時の状況を説明したまえ」
私は、こういう会議には不慣れだ。ましてや、会議は私への『査問委員会』の様相を呈している。真っすぐに内科部長に視線を向け、興奮から上ずった声で返事をした。
「今回の患者さんに対して、特に普段と異なる行動をとったということはありません。患者さんは、ご高齢で、少しやせていましたので、ゆっくり撮影しました。格別普段と違うのはその辺だけです。胃低部噴門近くに潰瘍の病変が見られましたが、他には特に気が付いたこともありません。ただ私の担当した患者さんということで、とても残念に思っています」
それだけをやっと話した。続いて、内科部長は看護婦に質問した。
「患者さんに筋肉注射をしながら気付いたことなどはなかったか?それから、高橋君の撮影時の行動に何か不自然なこととか特に気になったことなどなかったか?」
看護婦はこの道30年以上のベテランで、院内で知らないものはない。ただ、准看護婦なので婦長とかの役職はない。
「私が筋肉注射をしたときは、少しやせた感じであまり体力のない方のような気が致しました。顔色ですが、濃い目のお化粧をされておりましたので良く分かりませんでした。ですが、こういう高齢者の方は珍しくなく、今までも多くの方が、何事もなく撮影を無事終えておりました。ですので、私は看護婦の立場からも特に心配はしておりませんでした。
高橋技師は、自己紹介をし、撮影時の注意を丁寧にお話しされ、操作も普段より優しく行っていました。今回の事故は、私の個人的な意見と致しましては、当院には落ち度はなかったと思われます」
最後に脳外科医師の診断上の意見が付け加えられた。
「病名は急性硬膜下血腫であるが、軽症であり手術の必要はない。数日入院させて様子を見たい」
委員会は、脳外科医の診断に安心し、また准看護婦の意見に納得したのか、私への「注意義務違反」等の過失はないと結論づけた。
会議の後、技師長と私は、その日のうちに女性の部屋を見舞った。ベットの中の女性は眠っていた。傍の椅子には、配偶者とみられる男性と娘さんと思われる女性がいた。男性は静かな口調ではあったが、私たちに向けてこう言った。
「今回の私の妻の怪我は、医療事故だと私は考えている。明日にでも、こちらから責任者の方に事情を聴きに来るつもりだ。その時は、正直に話してくれ」
いかにもこの私に一方的な過失があったかのような言い方をした。技師長と私は「どうかお大事にして下さい」とだけ告げて早々に退室した。
廊下から部署に戻る途中、技師長は気にすることはないと私を励ましてくれた。だが正直、私は朝から真知子さんのことを考え、落ち込んでいた。私は不安だった。集中力を切らすことなく、充分な配慮を患者に向けていたと自分自身に対し自信をもって言いきれるのかと。
その二日後の昼過ぎ、技師長あて院長秘書から電話が入った。院長が、技師長と私を呼んでいるという。技師長と私は急いで院長室に向かった。ノックして入った部屋の中には、先日のレントゲン台から落ちた高齢の女性の夫という男性と娘と思われる女性がソファーに座っていた。
私と技師長は、二人に向かって頭を下げながら丁寧に詫びた。詫びたというのは、自分たちに過失があったという意味ではなく、例え落度はなくともこのような予期せぬ事態を招いた当事者であることに対しての詫びであった。
女性の夫という男がコーヒーを一口飲んでから言葉を発した。
「私は、北海道議会議員の成田です。今回の妻の一件は、直接担当されたレントゲン技師の方に責任があると思っています。それで、今日は院長先生の前で、真実を話していただこうと思ってやって来ました。技師の方は、この件についてどうお考えですか?」
すかさず、技師長が答えてくれた。
「この度の奥様のお怪我に対し、心よりお見舞いを申し上げます。一日も早く快復されることを願っております。今回の事故につきましてですが、私どもは日々患者さんに対し、細心の注意を払いながら、患者さんへの的確な診断のお役に立つため、医師の指示に従い可能な限り丁寧な仕事をしております。奥様には大変お気の毒な事でしたが、通常の検査中に貧血を起こされたことが原因と認識しております」
今度は娘と思われる女性が、やや感情的になって口を開いた。
「今まで、家の中の掃除など家事を一人でこなせるほど、母は丈夫だったのです。その母が、胃のレントゲン中に撮影台から落ちたということは、技師の方の操作に重大な誤りがあったとしか思えません。単なる貧血による転倒での怪我、で終わらせる訳にはまいりません。貴院の方で、非を認めて下さらないのであれば、残念ですが訴訟に頼る以外はありません。明日にでも弁護士の先生の所に伺う所存です」
院長は困惑した顔を成田議員に向けて言った。
「成田先生、いつもお世話になっておりながら、この度は奥様に大変不幸な出来事が当院内で起きましたこと、誠に遺憾に思っております。一日も早いご快復を願い、奥様専属の医療チームが昼夜を問わず精一杯務めさせていただいておりますので、どうか穏便にお願いいたします。もちろん、治療費等は結構でございます」
院長の言葉を聞いた成田議員は「今日の所は、ご挨拶ということで」と言いながら娘と共に院長室から出ていった。
後に残った技師長と私に向かって院長は言った。
「大丈夫だから、私に任せておきなさい。このことで職員が仕事で気後れするようなことがあったのでは、この病院の未来はない。職員の皆は頑張って働いてくれればいい。万が一何かトラブルがあった時は、私が責任をもって対処する。だから、何も心配せずに明日からまた頑張って欲しい!」
院長室を出て職場に戻ると、技師長は涙を流した。技師長が言うには、前職の病院で技師長自身が同じようなトラブルに遭ったそうだ。その時誰も味方になってはくれず、四面楚歌状態だったという。技師長は独りさみしく辞表を出したのだそうだ。私も院長の言葉に、この人のためにも頑張らなくてはと心に誓った。
真知子さんとのこと、父の入院のこと、撮影中の患者さんの怪我のこと、私は多くのストレスを抱えて辛かった。せめて真知子さんから「私がいるから大丈夫!」とでも、一言って貰えたらこんなストレスは、簡単に吹き飛ばせた筈だ。
世の中、思うようにはならない。今ごろ、真知子さんは涙を流してはいないかと私は案じた。
砂山の砂に腹這ひ 初恋の いたみを遠くおもひ出づる日 (啄木)
恋とは、人を愛するとは、何と辛いものなのだろう。真知子さんと私は心で結ばれている。そう思ってはみても、切ない気持ちは深まるばかりだった。
【第14章 真知子さんから別れのことば】
あれはいつ頃だったろうか?中学1年生の時だったような気がする。ある日曜日、暫くぶりに父親に誘われ、近くの海岸に魚釣りに出掛けた。父親は、まだ成長過程の私より遥かに体も大きく、腕力も敵わなかった。餌を沖に投げる距離が段違いだった。
さほど大きくはなかったけれど、カレイやハゼが10枚くらい釣れた。父親の針に掛かった魚ばかりだった。暫くして、全くアタリが無くなった頃、父親は煙草をくわえながら、独り言のようにしんみりと語りだした。
「人生には、苦しくてどうにもならないときが必ず来る。自分の力では、努力ではどうにもならない。そんな時は、じっと時間が過ぎるのを待つしかない。じっと耐えるしかない。ただそうして嵐が過ぎるのを待つしかないことがある」
当時の私には、何のことかさっぱり分からなかった。父親は、確かにその頃元気がなかった。珍しく魚釣りに誘ったのは、私と過ごすことで、一時でも辛さを忘れたかったのかも知れない。
今の私も、あの時の父と同じように、じっと時が流れるのを待つしかないのだろうか?だが、私の場合は、何もしないことは自分を追い詰めることにしかならない。複数の困難が重なると私は混乱して委縮してしまう。だが、複数の悩みも整理してみると、意外と明るい道筋が見えることがあると、何かの本で読んだのを思い出した。
今、私の身に起こっている問題は3つある。
〇真知子さんのこと。真知子さんが最近私を避けているかのようだ。どうしたのか、その訳を知らなくてはならない。逃げてはいけない。真知子さんへの愛が誠なら恐れてはならない。
〇父親の入院のこと。治療については医師を信じる以外にない。幸い、もう直ぐ退院だ。治療費も、通勤災害ということになった。何も心配はない。後は、退院したら家族で支えて上げよう。父親のことは心配ない。
〇胃部レントゲン撮影時における患者の事故のこと。病院は私に対して何ら責任を問うてはいない。だが、私の心の中における「本当に、自分には全く落ち度はなかったのか?」その思いが私を苦しめる。あの日は、確かに朝から真知子さんのことで頭が一杯だった。
この中で②の父親のことは、大丈夫だ。心配すること無い。③の件に関しては、病院長に任せるしかない。私が出しゃばっても、事態を悪化させることにしかならない。今後は、尚一層慎重に仕事をすることで、今回の事故からの教訓としよう。
私は、やはり真知子さんとのことが何より大切だ。二人がお互いを大切にし、周囲から祝福されるよう、そんな関係を一日も早く築くこと。そのことに今は集中すべきだ。そのための苦労は厭わないこと。もし、誰かに反対されても、逃げることなく地道に説得していくこと。そう考えた私は、再び真知子さんに会うための方法を考えた。
病院関係者のいる場所で、真知子さんを誘うのをためらった私は、やっと父が退院する日の午後に早退した。父の退院の手続きをし、衣類や身の回りの物をまとめ、父と母と私で家に帰った。父は暫くぶりの我が家に、心から喜んでいるかのようだった。
私は、「用事があるから」と両親に言い、午後4時半過ぎに家を出た。行く先は、真知子さん家の近くだ。真知子さんが帰って来て会えたら、渡すつもりで短い手紙を書いた。
「真知子さん、どうしたのですか?真知子さんに逢えずに、僕がどれだけ寂しい思いをしているか、どれだけ悲しい思いをしているか、知っていますか?
僕たちの気持ちは一つの筈です。話してください。事情を話してください。真知子さんも苦しんでいるのが私には分かります。二人できっと良い方法を探しましょう。
次の日曜日、この前行った市電函館ドック前で午前10時に待っています」
私は腕時計を見た。もう直ぐ6時になる。周りはすっかり暗くなっていたが、道路わきの街灯が辺りを照らしていてくれた。父が退院する午後は、秋時雨が降っていた。「きっと逢える」。私は、自分に言い聞かせるように呟いた。今は、すっきりしない空模様ではあるけれど、雨は降っていない。
それから少しして、私は真知子さんの姿を目にすることが出来た。だが、驚いた。真知子さんは、家の前でなく、若干離れたところでタクシーから降りたのだった。私に会わないように、毎日帰宅時にタクシーを使っていたのだ。
私は、真っすぐ真知子さんの元に駆け寄り、上着の内ポケットから手紙を取り出すと、真知子さんの手を取り渡した。真知子さんは、一瞬ビックリした表情をし、うつむきながら、みるみるうちに大きな涙を浮かべた。
私は真知子さんの涙をハンカチ優しく拭いながら、言った。
「雨が降っていないから、必ず会えると思っていたよ。手紙、読んでね」
そう言うと、私は振り返らずに五稜郭の駅に急いだ。真知子さんの近所の目を意識したからだ。
それから、やっと日曜日が訪れた。この前ここで逢ったときは、お互いの気持ちに綻びは微塵もないことを確認し合えた。今日も、きっとそうなると私は信じて家を出た。
今日も約束の時間より早めに着いた。空を仰ぐと雲の間から、僅かに陽が射している。真知子さんと逢う日だ。雨が降る訳がない。
漁港で時間を潰し、15分前に市電函館ドック前に戻った。やがて市電が現れ、真知子さんが降りてくるのを私は待った。釣り人がこの前のように何人か降りてきた。次は、真知子さんが降りてくる。そう思って、元気にお早うと言葉をかける準備をした。
「えっ 何で?どうして?」
私は一瞬パニックになった。真知子さんが降りて来ないのである。市電が走り去る後姿を、まるで夢の中の出来事のように眺めていた。頭の中を整理しようと暫くそうしていたが、疲れてベンチに崩れ落ちた。
「真知子さんが、来ないなんてあり得ない!」
私は、心の中で何度も叫んでいた。私の思考は空回りし続けた。どの位、時は過ぎたのだろうか?私はベンチから立ち上がり、歩き出そうとした。その時、次の市電が到着した。私は、振り向きもせずに、背中を丸め高齢者のように足を引きずって漁港に向かった。
ふいに後ろから女の人が叫ぶ声が聞こえた。
「晴彦さ~ん 待って~!」
驚いて振り向くと、そこには真知子さんが立っていた。真知子さんは、私の元に走り寄った。
「わたし~」
それだけ言うと、私に抱き付いた。私はそのまま真知子さんの肩を抱きしめていた。しばらくして、無言で真知子さんの手を引き漁港に向かった。二人で港の片隅に置かれた古いベンチに座った。私はいつものように、彼女の座る位置にハンカチを敷くのは忘れなかった。
「どうしたの?時間を間違えたの?」
私は優しく小さな声で聞いた。真知子さんは首を振って答えない。本当に、真知子さんはどうしてしまったのか?
「真知子さん、僕たちの気持ちはこのままずっと変わらないはずだ。僕には、この先も真知子さんしかいない。僕は、真知子さんと結婚して、僕たちの子どもに産まれたがっている子と一緒に楽しく暮らしたい」
真知子さんは、ハンカチを顔に当てて頷いている。真知子さんの本心は私と同じなのだ。なら、どうして、私を避けるようなことをするのか?真知子さんは苦しんでいる。何に苦しんでいるのだろう?
暫くすると、真知子さんはぽつりと言った。
「もう逢えない・・・。晴彦さん、私は弱い女。ごめんなさい、本当に・・・ごめんなさい」
真知子さんは、よろめくように立ち上がり、溢れる涙のまま私にささやいた。
「晴彦さん、私を許してください。こんな私を大切にしてくれて、本当にありがとうございました。もし、今度生まれて来たときは、何があっても晴彦さんに付いていきます」
真知子さんは、市電函館ドック前に歩き出した。私は止めようと、真知子さんの体の前に立ちはだかったが、真知子さんは首を横に振り、嗚咽しながら私の横を通り過ぎた。
私は、意気地なしだ!なぜ、抱きしめて離さなければ良いではないか?
そうしたかった!だが、私が強引に真知子さんを引き留めても、真知子さんを追い詰めるだけだ。余計苦しませるだけだ。今は耐えよう。私は呆然と真知子さんの後姿を見送った。
【第15章 旧友からの東京の病院への誘い】
ある日技師長から、院長秘書から聞いたという話しをしてくれた。院長秘書は、仕事柄しょっちゅう院長室に出入りする。そのとき院長と成田議員との話しのやり取りを聞いたという。
秘書の話しによると成田議員は、当院とその時の当事者の私を、本当に訴訟に持ち込もうとしたらしい。成田議員は、知り合いの紹介である弁護士に相談した。しかし、弁護士は調査により「医療事故」あるいは「医療過誤」のいずれにおいても勝訴の見込みは殆んどないとの結論を出したそうだ。
医療事故において、医療機関側に「過失」があったと認められる場合は、民法上の「債務不履行」または「不法行為」に基づく損害賠償責任を負うことになるらしい。だが、通常の事故と違い、医療事故はその過失の有無についての判断が非常に難しく、簡単に責任を問うことができないのだそうだ。
そうしたことから、成田議員は訴訟を諦めたとのことだった。
技師長と私はこの話に疑問を持った。成田議員からしたら、訴訟をしようとしている相手側に自らの不利な情報を持ち込むことなど通常あり得ない。考えられるのは、今回は訴訟を諦めるという条件で、和解金即ち示談金の交渉を有利に運ぼうとしているのではないかと考えた。
しかしその後、議員の妻が退院し日常の生活に戻ると、普段、議員自身も糖尿病や慢性腎不全の疾患で世話になっている病院と争うことが忍びなくなったという。妻の撮影台からの転落の一件は、この病院に落ち度は全くないとは納得している訳ではない。だが、病院長も心から妻を気遣ってくれ、治療費の免除と見舞金も用意してくれた。見舞金の金額は、弁護士によるとこの件での見舞金としては高額との見解であったそうだ。そうしたことから、この件はもう水に流そうと成田議員の方から申し出たそうだ。
成田議員も男だと技師長は褒めていたが、それから数日後に再び成田議員は病院長を訪れたという。この件も、院長秘書からの情報だ。
「院長先生、妻もすっかり良くなり、家事でも買い物でも、何でも一人でやっています。一時はどうなるかと、私も不安から当院に対して随分と冷たいことを申してしまいました。お恥ずかしい限りです。
ところで、院長先生。妻もこの病院には高血圧症や膝関節痛などでお世話になっておるんですが、妻の言うのには、当院にはもう来たくないと申しているのです。どうしてなのかと聞きますと、あの時のレントゲン技師がいると思うと、病院に向かう足がすくんでしまう、こう言うのです。
院長先生、私は北海道議会議員に33才で初当選し、次期議長候補とまで噂されるようになりました。ですが、私が道議会議員になれましたのは、妻の父親の地盤を受け継いだからです。そうした訳で、妻には頭が上がりません。
こんな恥ずかしい話をする自分が惨めではありますが、院長先生、何とかならんでしょうか?」
院長は、しばらく間をおいてから言ったそうだ。
「何とかならないかという意味は、奥様のあの時の担当技師のことでしょうか?」
院長はしばらく考えていてから、口を開いたそうだ。
「成田先生には、当院はひとかたならぬお世話になっております。当院が幾つかの拠点病院に指定されたのも、成田先生のご尽力があってこそだと普段から感謝致しております。先生の申されたことは検討させて頂きます」
苦渋を湛えた表情で院長はそう答えたのを、ちょうどコーヒーカップを下げ、変わりのお茶を運びながら秘書は聞いたのだという。
それから半月も経った頃、技師長と私は事務長室に呼ばれた。院長が学会出張で留守のため、事務長が依頼されたとのことであった。
「忙しいところ申し訳ない。院長先生が学会で留守なので、代わりに私が仰せつかったのだが、二人に来てもらったのは高橋君の転勤のことなのだよ。
前の胃部レントゲン撮影時の事故の件とは、関係がないと初めに断っておく。高橋君には、来月一杯で、つまり今年いっぱいで、系列の旭川の病院に転勤していただくことになった。旭川病院の方でレントゲン技師が足りなく、優秀な技師を1人でも良いから何とかしてくれないかという依頼がしばらく前からあったのだが保留していた。それが、先日また何とかして欲しいと旭川の事務長から泣きつかれてね。
院長先生も、高橋君の普段の努力をご存じで、残念だと仰られていたよ。この転勤は左遷ではなく栄転だから、旭川病院でも頑張って欲しい」
私は帰宅してから北海道の地図を見た。函館からだと旭川まで約450キロの道のりだ。真知子さんと再び交際が始まっても、そう頻繁に逢える距離ではない。
この前市電函館ドック前で会ってから、既に1週間近くになる。レントゲン室での事故のことや、旭川の病院に転勤することになったことは伝えていない。もしかしたら、もう噂になり、真知子さんの耳に届いているのだろうか?いずれにしても、その件も含めて話し合わなければと思った。
だが、待ち伏せのような真似はもうしたくなかった。とにかく二人で話し合いたい。火曜日の晩、私は真知子さんへ手紙を書いた。
「真知子さん、1週間前に函館ドック前で会ったばかりですが、僕は毎日でも逢いたいです。真知子さんから、もう逢えないと言われましたが、そう簡単にこの想いを消すことなどできません。
時々、薬局の受付の前を用事がないのに通ります。もしかしたらガラス窓の奥に、真知子さんの姿が見られるかも知れないと思ってです。
真知子さんが苦しんでいるのは、私には痛いほど分かります。将来の伴侶と決めた人ですから、傍にいなくても真知子さんのことは何でも分かります。
私は約3週間前に胃のレントゲンの撮影中、患者さんをケガさせてしまったことはご存じですか?そのことと因果関係があるかは知る由もありませんが、来年1月から旭川病院に転勤ということになりました。
9月頃まではバスの中で週3日は会い、時々デートもしました。旭川の病院に行けばそう簡単に逢えなくなってしまいます。ここのところ真知子さんと逢ってはいませんが、同じ病院の中にいるというだけで、真知子さんと一緒だという喜びがあります。
真知子さん、僕は心から真知子さんが大好きです。ずっと一緒にいたいのです。真知子さんは、この次もし生まれて来たときには、何があっても僕に付いて来てくれると言っていましたが、なぜ今は駄目なのでしょうか?
もう一度、逢ってください!もう一度、今後のことについて話し合いましょう!きっと、二人にとって最良の道がある筈です。負けないで、二人で力を合わせて乗り越えましょう!
二人初めてデートした立待岬に行きませんか?市電函館駅前で、次の日曜日10時に待っています。必ず来てくれると信じています」
真知子さんは、どんな気持ちでこの手紙を読んでくれるだろうか?私は、さぞ真知子さんが悲しむだろうと、ポストの前でしばらく迷った。だがこのまま、うやむやにしたまま函館を離れることはできない。真知子さんの本心を確認しないことには、この先に私の人生はない。
辛い日々の中で、私は昔の家具製造会社の仲間で、現在は東京の有名な病院でレントゲン技師として働いている伊藤を思い出した。今の私には、心を許して話せる友達は伊藤しかいなかった。
伊藤にだけは苦しい胸の内を分かって欲しかった。昼休みに公衆電話から伊藤の病院に電話をした。公衆電話では長電話は出来ない。再度、夜の8時ころに電話をすることにした。伊藤は、私とは反対にとても元気そうで、覇気が感じられた。
その晩、約束の時間に電話をすると、伊藤は待っていたかのように電話口に出てくれた。電話ではあったが、しばらくぶりの会話に伊藤の声は弾んでいた。少し世間話をしただけだったが、伊藤は私が深刻な悩みを抱えているのを即座に察したようだ。
「高橋、今日の高橋の声は昔のお前の声じゃない。いかにも辛くてしょうがないという声だ。俺に出来ることなら何でもするよ。言ってみろ!」
私は、何の遠慮の必要のない伊藤に全てを話した。胃部レントゲン撮影時の事故のこと、真知子さんのこと、旭川の転勤のこと、私は理性を失い感情に任せ、脈絡のない話を一方的に話した。伊藤は黙って何度も相槌を打ちながら、真剣に聴いてくれた。
私が一通り話してやっと心が軽くなった頃、伊藤は言った。
「高橋、お前が真知子さんという人を本当に好きなんだということが良く分かったよ。もし、その真知子さんとまた仲良くなれるなら、旭川の病院に行くことを勧めるよ。だが、もし、真知子さんとお前の本意でなくとも、一緒になれないのなら俺の病院に来ないか?正直、うちの病院でもレントゲン技師が足りなくて困っている。お前さえ決心が付けば、俺が働けるように技師長や事務長に頼んで、必ず採用して貰えるようにするよ。これでも俺は、少しはこの病院では信用があるんだ。必ず大丈夫だよ」
伊藤は、真知子さんと一緒になれないのなら、東京に出て来いと言う。傷心の私にはどうして良いか分からなかった。
【第16章 別れの青函連絡船】
真知子さんは、来てくれるだろうか?
約束の日曜日、私は何と9時過ぎに市電函館駅前に着いてしまった。昨夜は少しも眠りに就いた気がしなかった。ウトウトしては目が覚め、その度ごとに真知子さんが来てくれるように祈った。
何をするでもなく、近くをウロウロして時間の過ぎるのを待っていた。どうして楽しい時間は過ぎるのが早く、そうでない時は遅いのか?腕時計を何度見ても、時計の針はいくらも進まない。
私が真知子さんに伝えた10時まであと数分という時、私のすぐ近くに国産の高級車が滑るようにして停まった。私に縁のない高級車には興味がなかった。私は、また腕時計を見てため息をついた。
「お早うございます!」
運転席から、何と真知子さんのお母さんが降りてきた。私は思わず挨拶も忘れ、真知子さんのお母さんの顔を見つめた。
「晴彦さん、ここは車の通りが激しいので、少しお話し出来る所まで付き合ってもらっていい?」
真知子さんのお母さんは、助手席のドアを開けてくれた。高級車はやはり内装が違うなと、革張りの椅子に身を沈めながら一瞬思った。こんな時に俺は何を考えているのだと自分を叱った。真知子さんはどうして来ないのだろう?なぜ、お母さんなのか?真知子さんのお母さんは、私に何を話そうとしているのか?
車の中の真知子さんのお母さんは何も話さなかった。5~6分も走っただろうか。青函連絡船の乗り場近くの、港のよく見える空き地に車を停めた。やっと真知子さんのお母さんは口を開いた。
「晴彦さん、ごめんなさいね。本当は真知子が来ればよかったんだけど、昨夜から食事も摂らないで部屋の中から出て来ないんです。
夕飯だよと下からいくら呼んでも来ないものだから、真知子の部屋に行くと、ベットの中にうずくまって泣いていたんです。どうしたのと聞くと、明日、晴彦さんから会わないかと誘われているけど、私はもう晴彦さんとのことは諦めているので、行けないと言うのです。
でも、晴彦さんを待たせたら可哀そうだから、とにかく会ってきたらと私が申しますと、真知子は私にしがみ付いて泣きじゃくるのです。
真知子が余りにも可哀そうで私もついもらい泣きをしてしまいました。真知子は、どうしても晴彦さんを諦めようと、無理をしているのが母親の私には分かりました。
晴彦さんは既に察しておられると思いますが、あなたたちに辛い思いをさせているのは、私ども夫婦の勝手な事情です。晴彦さんと真知子に悲しい思いをさせて本当に申し訳ないと思っています。薄情な親だということも分かっています。
今日は、晴彦さんにお詫びに来たのです。真知子にも断って来ました。真知子は何も言いませんでしたが、あなたに申し訳ないと伝えて欲しいと願っているのが親の私には分かりました。
正直に言えば、私も晴彦さんと真知子が結ばれるのを楽しみにしていました。真知子の伴侶に晴彦さんは相応しい方だと喜んでいました。
私の力が及ばなく、こういう結果になってしまい、晴彦さんと真知子には本当に申し訳なく思っています。親の都合で二人に悲しい思いをさせておきながら、私がこんなことを言うのはどうかとも思いますが、真知子はあなたを心から慕っています。真知子は苦しんでいます。どうか真知子を責めないでください。そして、どうか、真知子とのことは運命だと思い、忘れてください。私たち夫婦をいくら恨んで頂いても覚悟しております」
私は、ただ静かに聞いていた。真知子さんのお母さんも本当は私たちの味方なのだ。だが、なぜ私たちの未来を奪おうとしているのだろう?真知子さんのお母さんの頬には大きな涙が溢れている。
「ここでお別れさせていただきます。今までありがとうございました。真知子さんに、くれぐれも宜しくお伝えください」
私は、そう言って車から降りた。真知子さんのお母さんは心配そうに、お家の近くまで送らせてと言ったけれど、私は大丈夫ですからと断り、あてもなく歩き出した。
それから数日後、私は東京の伊藤へ電話した。伊藤は、真知子さんとのことは諦めたのかと確認した。そうだと伝えると、間違いなく採用されるよう頑張るから吉報を待てと言って電話を切った。直ぐにでも行動に移す気配がした。
私は、真知子さんと別れた後の北海道には何の未練もない。だが私は長男なので、上磯に住む両親と妹の許しが必要だった。最近の私のやつれた表情から、家族は私の東京行きを認めてくれた。次の日の朝、台所にいた妹に、迷惑をかけて申し訳ないと頭を下げると、妹は両親に聞こえないように小さな声で私に言った。
「お兄ちゃん、家のことは心配しなくて大丈夫!私が結婚しようとしている人は、次男だから、きっと養子に来てくれる!両親のことは、私がちゃんと面倒見るから心配しないで!」
こんなに妹が頼もしいと思ったことはない。涙もろい私は、瞼を熱くした。
数日後伊藤から、もし問題があれば伊藤が全責任を負うという条件で採用が決まったとの連絡が入った。私は伊藤に感謝しつつ東京行きを決心した。翌日私は、12月末日をもって退職との辞表を技師長に出した。技師長は、驚いたようだったが、私の再就職先の病院名を聞くと納得してくれただけでなく、むしろ応援してくれた。
伊藤の話では、年明け早々からの勤務となるらしい。私は、12月28日の青函連絡船の切符を購入した。少しでも早く函館を離れたかった。
師走は慌ただしい。忙しい日々であっという間に今年も残すところ僅かとなった。私は各部署に退職の挨拶回りをし、翌日から有給休暇を取った。
真知子さんには、どうしても見送りに来て欲しかった。最後の別れをしたかった。だが、直接真知子さんに伝えることを私は躊躇した。真知子さんが働いている時間帯に、具体的には平日のお昼頃に真知子さんの家に電話をした。期待した通り、真知子さんのお母さんが受話器を取ってくれた。
私が、北海道から離れ内地に行くことになった旨を伝えると、真知子さんのお母さんは急に涙声になり、いつ北海道を発つのかと聞いた。
「明後日の午前11時発の青函連絡船で東京に行きます。新年から、またレントゲン技師として東京のある病院で働くことになりました。もし、出来ましたら真知子さんに伝えて頂けたらと思いまして」
この声を聞くのも最後だと思った私は、蚊が泣くような小さな声で呟いた。
「真知子さんのお母さん、色々お世話になりました。どうか、いつまでもお元気で・・・」
最後の方は声にならなかったが、電話を切ると、もう終わったという思いが体中を駆け抜け、男のくせにまた涙を流した。
いよいよ内地への出発の朝、私は家族からの見送りを再度断り、青函連絡船の乗り場にひとり向かった。年の暮れの函館港は混雑していた。
私が青函連絡船の乗り場近くを歩いていると、紺のオーバーコートを着て、ハンドバックと茶色の紙バックを持ち、辺りを誰か探す素振りで立っている真知子さんが目に入った。私は走って駆け寄った。
「来てくれたの?ありがとう!」
私は真知子さんの瞳を見つめて言った。出航までにはまだ随分、時間が残されている。なるべく人混みを避け、私と真知子さんは隅の方に置かれたベンチに座った。私も、大きな荷物を両手に下げているので、今回はハンカチを真知子さんに敷いてあげることはできなかった。
人の目を気にする余裕は、今の私たちには無かった。私は、住所を書いたメモ用紙を真知子さんの手に握らせた。いきなり、真知子さんが人目も憚らず私に抱き付いてきた。私も、堪えきれなくなり涙を流した。
話すことはたくさんある筈だった。お互いを慰め合う時間も十分あった筈だった。だが二人は何も言えず、抱き合っていた。暫くそうしていた。ふと真知子さんは体を起こし、嗚咽を堪え、心の底から絞り出すような声で私に言った。
「晴彦さん、ごめんなさい。私を許してください。東京へ行ったら頑張ってね。素敵な人がいたら、私のことは忘れてい・・・・」
最後は聞き取れなかったが、真知子さんの言いたいことは私には分かった。真知子さんは、ふと思い出したように茶色の紙バックから何やら取り出した。
「私の編んだ手袋とマフラー、冬の東京も寒いでしょ?風邪引かないでね。それに、今朝作ったサンドイッチ、船の中で食べてね」
青函連絡船は私たちに少しの気遣いもみせずに、無情にも汽笛を鳴らした。私は、真知子さんに話す最後の言葉を考えて来たが、そんなことは忘れていた。
「真知子さん、一生忘れないよ。いつかまた函館で会うことがあった時は、笑顔で挨拶しようね」
私の差し出した右手の甲に、真知子さんの涙が落ちた。私は桟橋を真っすぐ進み、連絡船に乗り込んだ。振り返るのが怖くて、後ろを見なかった。
いよいよ出航という時、真知子さんは立ち上がり白いハンカチを振った。残酷な時の流れだった。白い航跡波の長さと真知子さんの姿が反比例して、いよいよ姿が見えなくなってきた。それでも、真知子さんの降るハンカチが左右にゆれているのが微かに分かった。
「もう、いいよ~。真知子さん、ありがとう!さようなら~」
周囲の客の存在も目に入らず私は大声で叫んだ。その時、霞んだ視野の先で揺れていた白いハンカチがいきなり私の視界から消えた。
【第17章 真知子さんの親友との出会い】
私は函館で真知子さんと別れて、既に半世紀近くが経った頃、東京のマンションを引き払い、函館に帰って来たのだった。函館の病院での勤務は短かったが、佐々木とは時々食事をしたりした仲だった。その佐々木に真知子さんのことを尋ねた。
佐々木は、真知子さんが定年まで独身で通し、その頃乳ガンが見つかり手術をすることもなく、暫くして亡くなったらしいと教えてくれた。真知子さんと私とのことを知らなかった佐々木は、感情の起伏のない世間話という風な感じで教えてくれたのだが、私が途中から涙声になり急に電話を切ったのを不思議に思っていたらしい。
実家では妹夫婦が跡を取っており、私は函館の大森に小さな戸建てのアパートを借りた。私が佐々木に電話してから暫く経った頃、今度は佐々木から電話があった。
「いつだったか、お前が内地から帰ってきて間もない頃、坂本真知子さんについて俺に電話をかけて来たことがあったよな。その時、彼女が亡くなったと話したら、急にお前は動揺して、すぐ電話を切った。俺は、きっと二人の間に何かあったのかと推測した。
驚いたことに、彼女が亡くなる寸前まで親交があったという人が偶然見つかったんで、お前が喜ぶかも知れないと思ったから電話したんだ」
私は、驚愕した。乳がんで亡くなったという事実だけでは、確かに私は辛かった。彼女が、私と青函連絡船の乗り場で別れた後、彼女はどう生きて来たのか?どうして独りで生きたのか?亡くなる間際のことなど、知りたいことが沢山あった。
「その人は、俺たちが働いた病院で、真知子さんと同期に入職した栄養課の吉田さんという人だ。彼女は栄養課長を最後に定年退職し、その後は市のボランティアの活動をしていて、今でも続けているらしい。
どうして彼女を知ったかというと、これが全く世間は狭いというやつなんだ。先日、従兄の法事があったんだが、その後の会食で五稜郭近くに住む従姉と世間話をしていたんだが、そしたら、お前が言っていた坂本さんと親しかったという友人を知っているという話になった。俺はびっくりした。
つまりこういうことだ。坂本真知子さんと親しかった吉田幸子さんは、俺たちがいた病院の栄養士だった。職員の数も多く、俺も覚えてはいなかったが、真知子さんと吉田さんは同期だったので、特に仲が良かったらしい。その吉田さんと俺の従姉は、その頃から生け花教室の仲間で、二人でよくお茶を飲んだり食事をしたりする間柄だったそうだ。それで世間話をしているうちに、坂本真知子さんの悲しい話を吉田さんから従姉は聞いたらしい。従姉は、真知子さんとお前の話を聞いて涙を流したそうだ。
とにかく、従姉から吉田さんに取り次いでもらうから、お前一度吉田さんに会ってみないか?もしかしたら色々真知子さんのことが分かるかも知れない!」
佐々木は、既に従姉から真知子さんと私のことを聞き、同情からか昔のよしみからか、この私のために尽力してくれているようだった。吉田さんとなるべく早めに合わせられるよう、従姉に頼んでみるという。
それから、2週間も過ぎただろうか?佐々木から電話があった。「来週の日曜日に、市電函館駅前に10時に待ち合わせということにしたが、大丈夫か?」という内容だった。佐々木は、お互い顔が判らないだろうから、彼女には白のハンドバックを下げてくるように頼んだということだった。話が済んだ後で、佐々木は不思議なことを聞いてきた。
「高橋、お前、確か一度も結婚したことがないって言っていたよな」
おかしなことを言うやつだと思った。
「残念だが、そのとおりだ」
私の返事に何故か安堵したようだった。
次の週の日曜日、市電の待ち合わせ場所に着いた私は、昔、ここで真知子さんと待ち合わせをしようとしたが、真知子さんは現れず、真知子さんのお母さんが来たことを思い出した。
「あの頃に戻れたら・・・・」
暫くすると、確かに白いハンドバックを下げた白髪交じりの女性が近づいてくるのが見えた。私から、声をかけた。
「吉田さんですか?高橋です。今日は、お忙しいところ、申し訳ありません。本当にありがとうございます」
そういうと、吉田さんは私の顔をまじまじと見つめて言った。
「今日は、真知子さんへ大きな喜びを差し上げられる日となります」
私は、吉田さんの言っている意味が分からないまま、近くの茶店に吉田さんを案内した。
席に着くと吉田さんは、バックを開けて分厚い封筒を取り出した。白かった封筒が薄茶色を帯びている。驚いたことに、その封筒のあて名は私だった。
「その手紙は、私宛てになっていますが、どういうことですか?」
吉田さんは、私が若干興奮しているのを感じたようだ。
「今日は、私は特に用事はありませんので、時間はたくさんあります」
私はコーヒーを二つ頼んだ。今度は、吉田さんは待ち切れないというふうに言った。
「今日は、この私にとっても、とても嬉しい日です。真知子さんとの約束を、良い意味で果たせたのですから」
私は、吉田さんの言う意味がさっぱり分からず、狼狽しながら言った。
「吉田さん、先ほどから私には吉田さんの言っている意味が分からず混乱しています。私は、真知子さんのことが知りたくて、今日、こうしてお会いしているのです。もちろん、吉田さんの貴重な時間を頂いて申し訳なく思っておりますが」
吉田さんは、大きな目を私に真っすぐ向けながら言った。
「この手紙は、坂本真知子さんが高橋さんあてに書いたものです。手紙の中身は知りません。でも、真知子さんはガンで衰弱した身体に鞭打ち、渾身の力を込めて高橋さんのためにしたためた手紙です。
当時は、ガンの病名告知はありませんでしたが、真知子さんはナース室での担当医師と看護婦の会話で偶然にも知ってしまったのです。悲しいことにガンは進行していて手術が出来ないということも知ってしまいました。
それから数か月のうちに、真知子さんはすっかり体力を失くし、若い日の真っ白な肌と大きな瞳は見る影もなくなりました。彼女は自身の命がそう長くないと悟ったある日、見舞いに訪れた私に一通の手紙を託したのです。それが、この手紙です。
高橋さんに読んでもらえることが彼女の命を懸けた願いだと分かりました。今日、その願いが叶えられるのだと思うと、私も今夜から安心して眠れます。そして、いつか真知子さんの傍に行っても笑顔で会うことが出来ます。
この手紙を私に託すとき、真知子さんは言いました。『決して、吉田さんから晴彦さんを探すというようなことはしないで欲しい。もし高橋さんから連絡があった時だけ渡して欲しい』とのことでした。それでは連絡がなかった場合はと聞きますと『その時は燃やして欲しい』と言いました。
私は、彼女の必死の形相に、それ以上何も言わずに受け取りました。私も、古希を過ぎた身、この手紙がいつも気になっておりました。このまま高橋さんにお渡しできずに、将来真知子さんの世界に行ったとしたら、何と言い訳をしたら良いのかと、そればかりが気がかりでした」
私は吉田さんと別れる前に、住所と電話番号を教えて貰った。吉田さんは「ようやくの肩の荷が降りました」と言って、私に深々とお辞儀をして別れた。真知子さんの手紙を手提げカバンに入れ、私は吉田さんの後姿に深く頭を下げ、姿が見えなくなるまで見送った。
【第18章 真知子さんからの手紙(前半)】
高橋 晴彦様
晴彦さん、お久し振りです。今から書き記すこの手紙を、いつどこで晴彦さんは読んで下さるのでしょうか?あなたと函館でお別れしてから、もう40年近くの歳月が流れました。
晴彦さんはどのような気持ちで、この手紙に接して下さるのでしょうか?唐突と思われるでしょうか?
あの別れの日からから今日まで、私の心の中ではあなたとの楽しい思い出が少しも色あせることなく、今でも生き続けています。
今、私はベッドの中にいます。私の体は、ガンの病魔に全身が蝕まれており、私には余り長い時間は残されていないと自覚しています。まだ意識の鮮明なうちに晴彦さんに手紙を書いておくようにと、もう一人の私が急き立てます。
生涯を独身で過ごした私の想いを晴彦さんに分かって欲しくて、またあなたの後を付いて行けなかった弱い女の心も知って欲しいと思っています。長い手紙になるかも知れません。数日を要してでも丁寧に書き進めたいと思っています。
遠い昔のことですから、晴彦さんは覚えていて下さるかと案じながら書いています。
私は晴彦さんと病院からの帰宅時にバスの中で会話をするようになりました。初めは同僚としての仲間意識からのものでしたが、少し経った頃から私は日記を付け始めました。もしかしたら、私と生涯を共にする人になるかもと知れないと、不思議な予感がしたからです。でもその日記も、晴彦さんと青函連絡船でのお別れの日が最後となりました。晴彦さんのいない函館で日記を書き続ける意味がないからです。
もう、あれから40年近くの歳月が瞬く間に流れたのですね。今日まで、私は晴彦さんとの思い出を支えとして生きて来ました。
この手紙を書き終えたら、ある人にこの手紙を委ねるつもりでいます。その人は私たちと同じ病院で働いていた、栄養士の吉田幸子さんです。吉田さんとは同じ年に入職し、姉妹のようなお付き合いをさせて頂きました。私たちは何事も隠し立てをすることなく、恋愛のことや職場の人間関係のことなど何で話し合いました。もちろん晴彦さんとの辛い別れのことも話しました。
きっと吉田さんは私の願いを快く引き受けてくれると確信しています。ですが私は余りにも身勝手だと知りながら、以下のようなことをお願いするつもりです。
-吉田さんへのお願い事-
この手紙は、私が生涯ただ一度愛した高橋晴彦さんへ宛てたものです。この手紙を吉田さんに預かって頂きたいのです。その扱い方ですが、以下のようにお願いいたします。
〇 将来、吉田さんご自身が健康に自信を無くされたときは処分(焼却)して下さい。
〇 もし、晴彦さんから私のことについて知りたいと連絡があった場合、次のいずれかの方法を取ってください。
A 晴彦さんが生涯独身であった場合は、この手紙を渡しください。
B もし一度でも既婚者であったなら手紙は処分して下さい。
以上のようにお願いするつもりです。この手紙が晴彦さんに届く確率など私は少しも心配しておりません。もし晴彦さんにその意思があるならそれ程困難なことではないと思ったからです。世間の人から見たら嘲笑の的となることでしょう。でも、そんなことはどうでも良いのです。もし叶わなかったとしたら、高い空の上で、晴彦さんと私は縁がなかったのだと諦めます。
ここから先は、晴彦さんが生涯独身を通され、吉田さんに私の生き様を知りたいとお尋ねになられたということを前提に書き進めます。
もう既に38年近くも過ぎたことですから、晴彦さんはもうお忘れになっているかも知れません。市電函館ドック前で、2度目にお逢いした時、あることを申し上げました。それは、「今度生まれて来たときは、何があっても晴彦さんに付いて行きます」との言葉です。
昔、あなたから借りて読んだ伊藤左千夫の「野菊の墓」を、私は涙を流しながら読みました。民子さんが2つ年上だからというだけで、大人たちの醜い邪推から引き離されたふたり。民子さんが亡くなった時に胸に抱いていた政夫さんからの手紙は読む者を感動させます。
映画でも見ましたが、やはり本で読む方が好きでした。小説の中の二人が、まるで晴彦さんと私のような気がしたからです。民子さんが、亡くなる間際に政夫さんの母に話した「私は、これでいいんです」という言葉の裏に、民子さんの本心が隠されているのだと思いました。
「私は、この現世では、政夫さんと添い遂げることが出来なかったけれど、きっと来世では結ばれると信じています。ですから、私は、死ぬことがちっとも怖くはないのです」
病に蝕まれた今の私には、この時の民子さんの気持ちが痛いほど分かるのです
ある時、私の精神が闇の中を彷徨い、気が付いたときには五稜郭の石垣の上に立っていたことがありました。私が、我に返って思い留めることが出来たのは、晴彦さんのことを思い出したからです。いつかあなたがこの函館に戻られて、私の醜い最期を知ったとしたら、そう考えたら急に恐ろしくなり、外泊許可をもらった、かつて晴彦さんと一緒に働いた病院に戻りました。私は、静かに死を受け入れることに致しました。私も、民子さんと同じ心境になったのです。
忘れもしない昭和49年の12月28日、函館の青函連絡船の乗り場で、ベンチに座ったままの私を振り返りもせず、青函連絡船に乗り込む晴彦さんの悲しそうな後ろ姿を、昨日のことのように覚えています。私は、あなたに付いて行かなかった自分を今でも悔やんでいます。
出航の汽笛が鳴った瞬間、私はハンドバックのまま、船に飛び乗りたい衝動に駆られました。連絡船が動き出すと、船内の通路を貴方は走り、私の前に立ってくれました。私は白いハンカチをバックから取り出しました。力の限り振りました。振り続けました。
あなたの姿が小さくなった頃、あなたが何かを叫んでいるのが分かりました。そのとき、私は全身の力が抜けて倒れ込んでしまいました。近くの何人かの男の人が救護室に運んでくれました。
あの時差し上げたマフラーはくたびれて、もはやゴミとして処分されたことと思います。東京でも、きっと元気でいて欲しいと願いながら急いで編み上げたものです。
晴彦さんに付いて行かなかった私をさぞ恨んでいるかと思います。私は弱い女です。あなたに責められても返す言葉がありません。でも、私は心から晴彦さんを愛していました。私がこの手紙を書き始めたのは、あなたの意思に沿えなかった弱い女ですが、私なりに晴彦さんの愛に応えようと努力したことを知って欲しいからです。私も晴彦さんと同じように辛かったことを知って欲しかったからです。
賢明な晴彦さんですから、父に反対されていることは容易に想像できたでしょう。晴彦さんとペアリングを買った晩に、母に台所で話すと、母はとても喜んでくれたとお話ししたと思います。ですが、それから1週間くらいしてから、私と父との間に悲しいやり取りがあったのです。
晴彦さんと上磯の漁港でコーヒーを飲んだ後、二人でペアリングを買いましたね。母は私たちのことを認めていました。父はいつも忙しくしていて、母と落ち着いて話すこともなかったので、あの日の晩初めて私たちのことを話したそうです。
それから暫くして、私は母に呼ばれました。土曜日の夕方で、私は仕事から帰り、自室で雑誌を見ながら寛いでいた時でした。階段を降り1階の居間に行くと、父は新聞を広げていました。どうやら、私を待っていた様子でした。
【第19章 真知子さんの手紙(後半)】
私がソファーに腰を下ろすと、父は新聞をたたみ、テーブルの隅に置かれたB5番の大きさの封筒を掴みました。おもむろに封筒を開けて、随分と厚い書類の束を捲りながら言ったのです。
「これは、昨日ある興信所から届いた、真知子が一緒になりたいと言った高橋君の身元調査だ。私は昨夜、その書類の隅々までに目を通した。
私は高橋君がどうのこうのというつもりはないが、お前と高橋君では生まれた世界が違う。はっきり言ってお前には相応しくない。高橋家の嫁になることに私は反対だ。
お前には、好きになった人と結婚して幸せな家庭を築いて欲しい。それは、どこの親も同じだ。だが、この調査を見る限り、お前の結婚相手としては不相応だ。高橋君の実家ははっきり言って貧しい生活をしている。それに、高橋君は、長男だ。お前が結婚したら、いずれ高橋君の家に入り、義理のご両親の面倒をお前が見ることになるだろう。私はお前に辛い人生を送って欲しくない」
幼いころから、私を誰よりも愛してくれた父。幼い日、高熱にうなされている私を、深夜の吹雪の中を救急外来のある病院まで運んでくれた父。忙しい合間を縫って、遊園地や旅行にもよく連れて行ってくれた。目の中に入れても痛くないと言いながら、大切に育ててくれた父。周りの友達から、羨ましがられたのを昨日のように覚えています。
そんな父を出来ることなら悲しませたくない。私は、愚かな女です。晴彦さんを忘れることが出来るのかを試そうとしました。そのため、仕事帰りに会わないようにタクシーで帰っていたことがありました。私にはとても苦しい試みでした。毎日、暗闇の中で生きているような気がしました。
私には晴彦さんがいないと生きていけない。やはり私は晴彦さんなしでは生きていけない。私の晴彦さんへの愛慕の念を抑えきれなくなった頃、晴彦さんは市電函館ドック前に来るようにと私に伝えてくれました。漁港で、晴彦さんは熱い胸の内を語ってくれ、私はやはりこの人と生涯を共にしたいと強く願いました。
次の日から、私はあなたにも両親にも内緒で、仕事の帰りに不動産のお店を回りました。私は家を出て、アパートで独り暮らしをしようとしたのです。晴彦さんと一緒になるための布石のつもりでした。それとささやかな父への抵抗でした。市電青柳町の近くに私は適当な物件を見つけ、両親にも内緒でアパートを借りようとしました。生活に必要な物を少しずつ買い揃えたりしました。
ある日、買い物をして大きな荷物を家の中に入れようとした時、母に見咎められました。理由を問われた私は正直に、晴彦さんと一緒になるためにアパートを借りたと言いました。母は私の味方でした。母は「お父さんを私が説得するからもう少し時期を待ちなさい」と言いながら頬を涙で濡らしていました。
父に何とか二人を一緒にさせて欲しいと、母は何度も懇願したようでした。いつもの父なら母の言うことに従順な筈でしたが、私たちのことには首を縦に振らなかったそうです。それから間もなく、父は珍しく早く帰った夕食の後、私に声を掛けました。
「真知子、お母さんから聞いたが、アパートを借りるんだって?この前話したとき、分かってくれたと思ったが、まだ晴彦君と会っているようだね。会社を経営するということは、何十人という社員とその家族を養うということなのだ。情けに流されたり、情に溺れたりしていては、いつ多くの人々を路頭に迷わせてしまうかも知れない。『坂本建設』」の存続が、関連会社を含め数百人の命を守ることになる。決して私一人の会社ではないのだよ。
私は、ここ5~6年の間、この会社を受け継いで欲しいと思う数人の社員を育ててきた。もちろんお前の婿になって、この家と会社を守って欲しいと願ったからだ。いずれお前には話すつもりでいたが、忙しさにかまけて言いそびれていた。数人の候補の中から、私は二人に絞った。そのどちらかを、お前に選んで欲しいと思っていた矢先だった。
何としても、私の選んだ二人のどちらかと結婚してほしい。二人とも、家柄も人柄も申し分ない。そして人の上に立って、会社を牽引していく経営者しての資質も十分だ。これは命令などではない。父の頼みだ。私の一生に一度の頼みだ
私がこれまで築き上げてきた『私の命』とも云える会社をどうしても守って行かなければならない。一人娘のお前が高橋君と結婚して、この家を出て行ったなら、この家も私の会社もどうなると思う。そうなるといずれ他人の手に渡ってしまうことになってしまう。この私が一生を掛けて築き上げた「坂本建設」だ。他人に渡すくらいなら死んだ方がましだ!」
普段、弱さなど微塵も見せない父が、目に涙を溜めていました。母は父の脇でオロオロし、母の目にも涙が溢れていました。その後、父は信じられない行動に出ました。何と、会社では威厳があり社員から尊敬の眼差しを受けている、その父が娘の私に土下座をしたのです。
「私の勝手だということは、重々承知している。だから、こうして頭を下げている。どうか父の言うことを分かって欲しい」
私は父の土下座の姿が哀れで、2階に走りました。
しばらくして、母が私の部屋にやって来ました。ベッドで横になっている私の傍に静かに座って言いました。
「真知子、お母さんはお前たちを一緒にさせてあげたかったけれど。ごめんね。力になってあげられなくって」
私は答えようがなくて、横を向いたままでした。
「真知子、もし、お前が親の反対を押し切り、この家を出て晴彦さんと一緒になったとして、本当に幸せになれると思う?子供が出来ても、この家の敷居を跨げない。それだけではなく、孫の七五三の晴れ姿も、小学校・中学校またその上の入学式の成長した姿も、私たちに見せられない。私の勝手かも知れないけれど、孫の顔が見られないなんて、これ以上お前の母として悲しいことはないわ」
本心からそう言ったとは私には思えませんでしたが、母はそれだけ言うと階段を降りて行きました。私は混乱して何も分からなくなってしまいました。
結局私は両親に逆らえませんでした。これまでの両親の深い愛情に背けなかったのです。函館から私は離れられなかったのです。本当に、晴彦さんにはどうしたら償えるかとそればかりを考えて、毎日を過ごしました。
晴彦さん、市電函館ドック前で、2回目に逢ったときの言葉を繰り返します。
「今度、生まれて来たときは何があっても晴彦さんに付いて行きます」
叶うなら、次の世では両親よりも誰よりも、晴彦さんを信じ愛します。そして、可愛い私たちの子と共に楽しく暮らしたいと、心から望んでいます。
私の晴彦さんに伝えたいことは、もうこれで全部です。二人の一緒にいた時間は短かったけれど、私が一番嬉しく、思い出に残っているのは、上磯でペアリングを買った時です。あの日から、私は晴彦さんと夫婦になったつもりでいました。
それから、今振り返って涙が出てくるほど辛い晴彦さんの言葉があります。それは晴彦さんが函館ドック前で言われた二つの言葉です。
一つ目は、晴彦さんが私に言った「真知子さんと結婚できないなら、僕は生涯独りで生きる」と言われたことです。私の我儘で、あなたを不幸にしてしまうのが忍びない思いで一杯でした。その時、私も生涯独りで生きて行く決心をしました。
二つ目は、もし別れることになったら、私たちの子に産まれたがっている子どもの夢と願いを葬り去ることになってしまうという言葉です。私は、とても罪深い女となってしまったのです。当然、私は今後結婚することも、子供を持つことも諦めました。その資格を、私が自ら放棄してしまったのですから。
晴彦さん、私は幸せでした。人生の長さから見たら、二人でいられたのは本の一瞬だったかも知れませんが、私の人生の全てだったと思っています。
それから、今思い出したことですが、私は何度かお手紙を出しましたが、ご返事を頂けませんでした。もう、晴彦さんには私よりも大切な人が出来たのかと、とても悲しい思いをしましたが、今になって分かりました。晴彦さんは、いつまでも二人の思い出をひきずらないで、私に幸せになって欲しかったのだと。
私の命の炎はもう直ぐ消えてしまうでしょう。でも、悲しくありません。そして悔いもありません。私は「野菊の墓」の民子さんのように、静かに逝きます。私は、次の世で晴彦さんと必ず一緒になれると思うと、逆に嬉しいのです。
本当に幸せな、そして楽しい時間を有難うございました。この辺で、終わりにします。晴彦さん、本当にありがとうございました。
さようならは言いません。
平成24年4月吉日 高橋真知子
文の最後に書かれた名前が「高橋真知子」になっていたのが、私には言葉にならないほど嬉しかった。読み終えた私は、震える手で手紙を封筒に戻した。
【最終回 真知子さんのお墓参り】
私は、お花とお線香を持って真知子さんのお墓に向かった。お墓は津軽海峡が見下ろせる函館山の麓にあり、いつか二人で行った立待岬の近くだった。
お寺の名前と場所は吉田さんから聞いていた。境内には入ってみたもののお墓の場所が分からない。住職の住居だと思われる建物の玄関のインターフォンを押した。
「こんにちは。ご免ください」
中から、「はい、ただいま」という声がして、住職の奥様と思しき年配の女性が出てきた。
「申し訳ありません。五稜郭の坂本建設の家のお墓参りに来たのですが、お墓の場所が分かりません。教えて頂けませんでしょうか?」
私がお願いすると、女性は笑顔で丁寧に教えてくれた。女性の言う通りにコンクリートの通路の突き当りを右に曲がって、少し進むと辺りの墓石より一回り大きなお墓が目に入った。確かに坂本家代々の墓と記されている。墓石は掃除がなされたばかりなのかきれいだった。少し先の方に水汲み場があった。沢山の桶も用意されていた。私は手桶に水を汲み、彼女の墓の前にゆっくり進み出た。
線香に火を点け手向けた後、菊とユリの花束を供え、墓石に水をかけた。私は合掌した。
「真知子さん、こんにちは。遅くなっちゃってごめん。僕は真知子さんに出会い、短かったけれど青春を謳歌することが出来たよ。その思い出だけで、本当に幸せな人生だったよ。ありがとう!
真知子さん、僕はもう古希を過ぎたよ。あと何年寿命があるか分からないけど、いつか真知子さんと逢う時も20代前半のままだね。青函連絡船で別れた時から逢っていないからね。お互い覚えているのはあの頃の姿だからね!」
真知子さんに話かけていると、後ろに人の気配がした。振り返ると住職だった。
「お墓参り、ご苦労様です。大変失礼ですが、今日お参りされたのは、どなたの供養ですか?」
私は立ち上がり、坂本真知子さんの供養に来ました、とそれだけを言った。すると住職は記憶を呼び戻すかのような表情をした後、私の目を見ながら言った。
「もう10年近くなると思うが、娘の真知子さんが病で亡くなられた後、葬儀が済んでもご夫婦揃って、毎日のようにお線香を上げに見えられていましたよ。私が、仏さんもさぞ喜んでいることでしょうと言うと、お父さんは涙を流しながら、私にこう言いました。
『私は、娘が若い頃、親のくせに娘にとても酷いことをしてしまいました。娘が心から好きになった男の人と無理やり別れさせてしまったのです。それから、いくら縁談を勧めても生涯、娘は首を縦には振りませんでした。
あの時、二人を一緒にさせていたら、米寿を迎えようとしているこの齢になってまで苦しまずに済んだものを!私は、二人の若い者の幸せを奪った愚かな、罪深い人間です』
と、こう言ったのです。私は、坂本さんに言いました。
『娘さんは、決してご両親を恨んだりはしておりません。娘さんは、ご夫婦に大切に育てられて、一緒に生きられてとても喜んでおられますよ。別れた男の方も決してあなた方ご夫婦を恨んだりしていないと思います』
こう言うと奥様とふたり、私に深々と頭を下げられました。ですが、それから一年も経たないうちに、ご主人と奥様は後を追うように亡くなられました。ところで、あのう、大変失礼ですが、もしかしてあなたは、真知子さんとお付き合いをされていた方ですか?」
私は一瞬返事に困ったが、そうですと答えた。
「やはりそうでしたか。真知子さんも喜ばれておられると思いますが、真知子さんのご両親もきっと喜んでいると思いますよ。もし出来ましたら一言ご挨拶をいただけたら、お二人ともきっと胸のつかえが取れると思うのですが」
住職の思いがけない言葉に、私は真知子さんのご両親に挨拶していなかったことに気付いた。私は住職にお礼を言って、もう一度真知子さんのお墓の前にひざまずいた。
「真知子さんのお父さん、初めまして。高橋晴彦と申します。お母さんには2度ほどお会いし、夕飯をご馳走になったり、本当にお世話になりました。真知子さんとは一緒になれませんでしたが、私は少しもお二人を憎んだりしたことはありません。ですからご安心下さい。真知子さんを産んで頂いて、そして大切に育てて頂き有難うございました。現世では真知子さんとは結ばれませんでしたが、来世ではきっと一緒にさせて下さいね」
そこまで言ってから、また続けた。
「真知子さん、もうこれで大丈夫だね。何も心配することはないね。また直ぐお墓参りに来るからね」
私の心は清々しさで溢れていた。ふと空を見上げると夕焼けで西の空が真っ赤だった。
〖あとがき〗
長い間お読みいただき有難うございました。心から感謝申し上げます。
この「函館物語」を書く前は大雑把な構想はありましたが、各章ともパソコンの前に座ってからは指の勝手な動きに任せました。ですので、とても脈絡と整合性に不安を抱き、途中、読み返しながらということがしょっちゅうでした。そして実際に誤りが何ヶ所かあり、恥ずかしいのですが修正させて頂きました。
あるプロの作家の方は、推敲を100回くらいなさるそうです。私は書き終えた後5~6回推敲してアップしてしまいますので、いつも後から読み返すと修正すべき所が何ヶ所も出て来ます。書いているときはその世界にのめり込み、感情が高ぶっていますので、冷却期間を4~5日おいて何度か推敲されることをお勧めします。出来れば、もっと長い方が理想です。